介護の現場では、医療ケアを必要とされる方も多くいます。
本来介護職が携わる事は出来ない業務ですが、「痰吸引」と「経管栄養」は喀痰吸引等研修を受けることにより、特定の条件のもと、実施出来るようになりました。
当記事では、喀痰吸引等研修の情報をまとめました。
実務者研修修了による免除もあるので、その関係性もお伝えします。
喀痰吸引等研修とは

喀痰吸引等研修は、介護士が「痰吸引」「経管栄養」のスキルを学ぶ研修。
修了する事で、一定の条件下のもとこれらの医療ケアが実施できる様になります。
これらは本来「医療行為」にあたり、介護士は行うことが認められてません。
しかし「社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正」により、研修を修了した方は、特定の条件のもと「痰吸引」と「経管栄養」が実施できるようになりました。
ただ内容を考慮すると、ある程度経験のある介護士向けですね。
喀痰吸引等研修修了で可能な医療ケア

喀痰吸引等研修は、講義や演習による「基本研修」。
現場の利用者相手に指導を受ける「実地研修」の形で行われます。
さらに研修種類は、第1号、2号、3号研修と分かれています。
どの研修を受講したかで、可能な行為や対象が異なるので注意しましょう。

研修修了後は、内容に応じて、特定の条件下で下記医療ケアが可能になります。
特定の条件下とは、「医師の文書による指示」や「業務手順書の作成」。
「看護職員との連携」などといった内容です。
長くなるので、詳しく知りたい方は下記をご覧ください。
※厚生労働省(介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について )
喀痰吸引等を行う為の手続き

喀痰吸引等研修は、研修修了のみでは痰吸引等を行えません。
痰吸引等を行うには、研修修了後に都道府県知事に申請。
「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受ける必要があります。
さらには行為を行う就業先が、「登録特定行為事業者」の登録を受けてる必要があります。
介護福祉士は痰吸引等を行える?

介護福祉士の資格のみでは、喀痰吸引等は行えません。
他の場合と同じく、基本研修と実地研修が必要です。
ただし、平成28年度以降に介護福祉士を取得した方は、基本研修が免除になります。
これは実務者研修に「医療的ケア」として、基本研修の内容が含まれる為。
介護福祉士の場合、必要研修を終えた後に社会福祉振興・試験センターに申請します。
これにより可能な「喀痰吸引等行為」が介護福祉士登録証に記載。
登録喀痰吸引等事業者において、喀痰吸引等が行えるようになります。
介護士が医療ケアに関わるメリット

介護士が医療ケアに関われるようになった経緯は、現場での必要性があっての事。
経口摂取が難しく「経管栄養」の対応が必要、あるいは定期的な「痰吸引」を必要とする。
介護施設には、そんな方がたくさんいらっしゃいます。
こうした方々は、特に特別養護老人ホームなどに多く見受けられます。
介護度の高い方を中心に対応する施設にお勤めの場合、活躍機会も多くなります。
対応力の高い介護士として、現場のニーズに応える事ができるでしょう。
評価にもつなげやすい資格ですね。
喀痰吸引等研修の内容

研修の内容は、基本研修+実地研修となっており両方修了する必要があります。
どちらかのみの形は不可ですので、注意しましょう。
「実地研修」では、介護現場において看護師の指導を受けます。
加えて「第1号研修~第3号研修」までの種類があり、以下の違いがあります。
- 吸引・経管栄養を実施できる対象と内容
- 研修内容
順を追ってご説明します。
基本研修の内容(講義とシミュレーション)

基本研修の内容は、「講義・演習」+「筆記試験」となっています。
テキストにそった講義を受け、シミュレーターを使用して各行為の演習を行います。
これは、シミュレーターという専用の人形模型を使った練習です。
講師の指導のもと、人形と液体を使い、経管栄養や吸引の手順を学びます。
初任者や実務者のそれと同程度と考えてOK。
実務者研修修了者は「内容・費用の免除」がある
.jpg)
基本研修の内容は、実務者研修における「医療ケア」に相当します。
そのため実務者研修修了者は、基本研修は免除になります。
しかし実地研修を終えなければ、医療ケアは行えないので注意です。
どちらが先でも、費用・内容の免除を受けられます。
実務者研修は介護福祉士に必須なので、先に受けるのがオススメ。
実地研修の内容(現場での指導研修)

実地研修は、現場での看護師による指導です。
利用者様相手にケアを実施するので、本番とも言える内容ですね。
- 口腔内の喀痰吸引
- 鼻腔内の喀痰吸引
- 気管カニューレ内部の喀痰吸引
- 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
- 経鼻経管栄養

喀痰吸引が3項目、経管栄養は2項目。
以上『計5項目』について、指導を受けます。
口腔内の吸引が20回以上、他は10回以上です。
ただし実施内容や回数は、後述の種類により少し異なります。
※参考「厚生労働省(喀痰吸引等研修)」より
喀痰吸引等研修の「第1~3号研修の違い」

喀痰吸引等研修は、「第1号研修~第3号研修」があります。
これらの違いは、医療ケアを実施できる対象と内容、研修時間等です。
| 対象 | 実施できる内容 | |
|---|---|---|
| 第1号研修 | 不特定多数 | ・喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ内) 3項目 ・経管栄養(胃ろう及び腸ろう・経鼻) 2項目 |
| 第2号研修 | 〃 | ・喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ内) 3項目 ・経管栄養(胃ろう及び腸ろう・経鼻) 2項目 上記のうち、4つまでを選択 |
| 第3号研修 | 特定の人のみ | ・喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ内) 3項目 ・経管栄養(胃ろう及び腸ろう・経鼻) 2項目 特定の人が必要な行為のみ |
大きくは「第1・2号研修」と「第3号研修」に分けることが出来ます。
第3号研修は、「講義及び演習で9時間」となってます。
第1・2号研修について
1号と2号研修は、不特定多数の方に学んだケアが実施できます。

1号研修は、5項目全てを実施できるオーソドックスな内容。
もちろん実地研修では、全ての項目で指導を受ける必要があります。
対して2号研修は、実地研修において5項目から4つを選択し学びます。
実施できるのは、選択した内容のみです。
第3号研修について

第3号研修は、「特定の利用者」に対し「その利用者の必要となる行為」を実施する為の研修。
利用者は個別性の高い方が対象であり、筋萎縮性側索硬化症などを想定。
ただしこれに限定するものではありません。
実施できる内容は、その方が必要とする行為に限られます。
参考:厚生労働省「介護職員等による喀痰吸引等制度Q&A」及び「喀痰吸引等制度について」
喀痰吸引研修を受けるには

喀痰吸引研修の具体的な受け方、費用日程についてお伝えします。
「喀痰吸引等研修講座」へ申し込みをする

喀痰吸引等研修は、各自治体や病院など様々な場所で行われてます。
また実務者研修等を行う一部の介護スクールでも、喀痰吸引等研修を受講できます。
その場合、様々なコースも用意されてます。
- 基本研修+実地研修
- 基本研修+実地研修先の紹介を受けない
- 実地研修のみ
こんな感じですね。
研修種類や免除などにより、選ぶべきコースが異なるので注意。
研修種類は、1号2号が探しやすいです。
基本研修からなら、まずは介護スクールを探すと良いですよ。
数自体は少ないので、実務者研修がまだなら先に受ける事をオススメします。
実地研修の受け方

実地研修は、「登録喀痰吸引等事業者」や「登録研修機関」で受ける事になります。
これは下記の様な施設です。
事業の一環として、痰吸引等の業務を行う事業者。
要件を満たし都道府県知事に登録された所。
※介護関係施設や障害者支援施設等が対象、医療機関は含まれない。
基本研修、実地研修を行う、都道府県知事に登録された機関。
医師や看護師等が研修業務に従事している。
勤務先がこれらに該当する場合、そこで研修が受けられます。
実地研修を受けるには、スクールの紹介や探すなどして、これらを利用する必要があります。
お住まいの地域で確認してみて下さい。
「研修費用」「日程」について

研修費用や日程は、選んだコースにより異なります。
スクールによる差の大きい部分ですが、簡単な目安をお伝えします。
特に費用は、スクールやコースによる差が大きいですね。
調べた限りですと、「基本研修と実地研修のセット」で安くて10万円~という感じ。
.jpg)
先程もお話ししましたが、まだの方は「先に実務者研修を受けた方が楽」と思います。
こちらの方が講座が活発に開かれており、選びやすいです。
免除もあるし、介護士としての総合評価も考えると優先度が高いと思いますね。
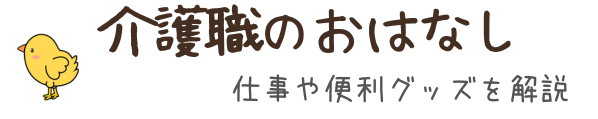
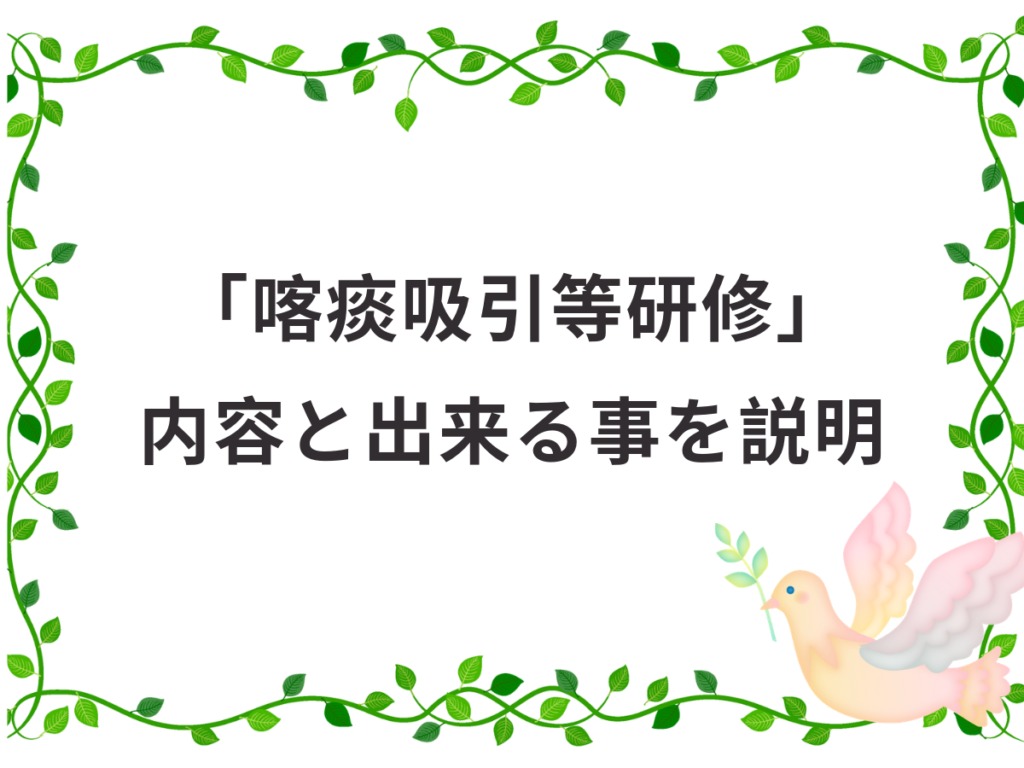
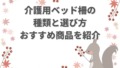

コメント