福祉用具の販売・貸与の仕事で活躍する「福祉用具専門相談員」。
そうした方々が、専門知識や技術を高める為の資格が福祉用具プランナーです。
当記事では「福祉用具プランナー」について、資格取得方法を中心に詳しく解説します。
細かな点にも注目し、ご紹介していきます。
福祉用具プランナーとは

福祉用具プランナーとは、テクノエイド協会が認定する福祉用具の民間資格です。
福祉用具を必要とする高齢者や障害者に対し、必要な福祉用具の選定を援助。
または使用計画の作成や利用の支援、使用状況の評価まで行う福祉用具の専門家です。
福祉用具関連でお仕事をされてる方が、さらに技術・知識を高める為の資格ですね。
「福祉用具の業務経験者」に向けたスキルアップ資格

福祉用具プランナーは、既に福祉用具の選定相談、利用指導の業務に関わってる人向けの資格。
また当資格は、講習を受講し取得するのも特徴です。
eラーニングの「座学」、講習での「講義」「実技」。
そして「認定試験」といったステップで、学習と資格取得を進めていきます。

先述の通り、当資格は「福祉用具専門相談員」等の資格や経験を持つ方向けの資格です。
資格取得に必要な認定講習にも、上記等の参加条件が設定されてます。
「福祉用具専門相談員」との違い

福祉用具プランナーに似た資格として、下記資格があります。
- 福祉用具専門相談員
- 福祉用具用具選定士
福祉用具専門相談員は、介護保険指定の福祉用具貸与等の事業所で必須となる資格。
講習を受ければ、誰でも取れる公的資格です。
福祉用具専門相談員の経験ありきな面もあり、上位資格である点が違いですね。

もう1つ似た資格として、福祉用具用具選定士があります。
こちらも福祉用具専門相談員の経験者を対象とした、日本福祉用具供給協会による民間資格。
研修を受ける事で取得できます。
カリキュラム自体は選定士の方が少なめですが、プランナーの方が研修数が多い様子です。
日程等比較して、取得しやすそうな方を選んでも良いかもしれませんね。
福祉用具プランナーを「活かせる仕事」と「取得メリット」

福祉用具プランナーは、主に福祉用具専門相談員として活躍されてる方向けの資格です。
下記メリットに魅力を感じたら、取得検討してみると良いでしょう。
- 福祉用具専門相談員としてのスキルアップ
- 福祉用具の選定、使い方等の知識取得
- 資格取得後に継続的な学習機会がある
福祉用具の知識や使い方、選定方法などについて、より理解を深める事が出来ます。
他には介護関係職やリハビリ職など、福祉用具に携わる仕事でも知識を活かせます。

福祉用具プランナーは、どちらかというと学習やスキルアップを目的とした資格です。
その為、給料や年収アップには繋がりにくいです。
しかし知識や信頼の獲得には役立つ資格であり、仕事でのプラス評価には期待できます。
義肢装具士の国家試験の指定試験機関を務めるなど、しっかりした実績があります。
資格取得後にも、セミナーや研修などの学習機会が多いのも特徴。
ただ後述する更新制度もあるので、その点デメリットに感じる方もいるかもしれません。
福祉用具プランナーになるには

福祉用具プランナーになるには、福士用具プランナー認定講習を受講する必要があります。
講習の全科目を履修し、認定試験に合格する事で資格取得する事が出来ます。
福祉用具プランナー認定講習の受講条件
.jpg)
福祉用具プランナー講習の受講条件には、「受講資格」「実務経験」「eラーニング受講条件」の3つを満たす必要があります。
- 指定福祉用具貸与(販売)事業所において、福祉用具専門相談員として業務に従事
又は従事した経験のある者 - 福祉用具関連業務に従事、又は従事経験のある下記の者
【保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、
社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、介護支援専門員、建築士】 - その他、特に認定講習受講の有効性があると当協会が認める者
- 認定試験実施日において、福祉用具専門相談員業務または福祉用具関連業務に
2年以上従事した経験がある者
- 自宅または職場等でeラーニング学習に必要な環境・機材を確保できる
(インターネットに接続可能である等) - 一般的なパソコン等の操作ができる
- 受講者個人用のeメールアドレスを所持している
要約すると、「福士用具専門相談員などの資格を持って、関連業務を2年以上経験する事」。
「eラーニングでの学習があるので、環境準備や操作が出来るよう」にという事ですね。
認定講習の「参加申し込み方法」と「スケジュール」

福祉用具プランナー講習は、下記3機関で行われます。
- テクノエイド協会
- 介護実習・普及センター
- 教育機関
教育機関における講習は、専門学校などの学生向けとなってます。
その為、一般的には前者2つを利用して講習を受ける事となります。
講習は各機関で年1回の開催ですが、開催時期は機関により異なります。
ただ「2カ月程度のeラーニング学習」+「7~9日の集合講習」という形は共通してます。

詳しいスケジュール等は、下記ページもご覧ください。
講習の実施機関への案内もあるので、その先で申し込み方法も確認できます。
参考までに2023年の開催場所は、【東京、神奈川、北海道、愛知、沖縄】等。
受講料は実施機関で異なる可能性がありますが、テクノエイド協会の内容を紹介します。
- 集合講習受講料(31,000円)
- eラーニング受講料・福祉用具プランナーテキスト代(21,000円)
福祉用具プランナー認定講習の「カリキュラム内容」

福祉用具プランナー認定講習は、合計100.5時間のカリキュラム。
その内容は、大きく「eラーニング講習」と「集合講習」の2つで構成されます。
| 講習種類 | カリキュラム例 | 合計時間 |
|---|---|---|
| eラーニング講習 |
| 48時間(2カ月程度) |
| 集合講習 |
| 52.5時間 (認定試験1.5時間含む) |
福祉用具プランナー認定試験の内容は?

福祉用具プランナー認定試験は、集合講習の最後に行われます。
ただ内容や合格基準、合格率などの詳細は記載がなく不明です。
しかし、当資格が「講習を通しての学習がメイン」である事。
「補講や再試験を受け付けている」事も考えると、試験合格率は高いものと思われます。
福祉用具プランナーの「資格更新手続き」「指定研修」

福祉用具プランナーは2015年度より「登録制」となり、5年毎の更新が開始されました。
資格の更新手続きは、下記いずれかの条件で行う事ができます。
| 更新条件 | 内容・注意事項 |
|---|---|
| 指定研修の受講 | 指定研修のうち、いずれかを修了 |
| 指定資格の取得 | 資格の取得・更新日以降に下記いずれかを取得 作業療法士、理学療法士、看護師 |
プランナー認定講習の | 講師実績が5年間ない場合、講師登録は抹消される |
特別資格の保持者 | 下記いずれかの資格保持者
|
更新手続きは、福祉用具プランナー情報システム内のマイページから行えます。
※ログインが必要な為、ID・パスワードの入力必要有
指定研修の確認や更新手続きの案内も、こちらで確認出来ます。
「認定カード発行料 3,200円(税込)」も必要です。
さいごに

今回は福祉用具プランナーの資格を解説しました。
大きくは、福祉用具専門相談員として働く方向けのスキルアップ資格ですね。
福祉用具関係の民間資格としては、知名度がある方の資格かと思います。
テクノエイド協会も福祉用具に関する長い活動実績があり、信頼性も高い資格です。

当ブログでは、他にも介護や福祉用具、資格に関する情報を発信してます。
良かったら、他記事もご覧ください。
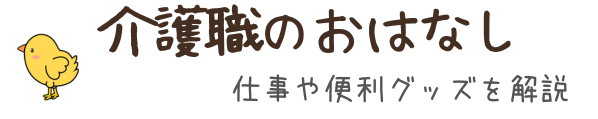
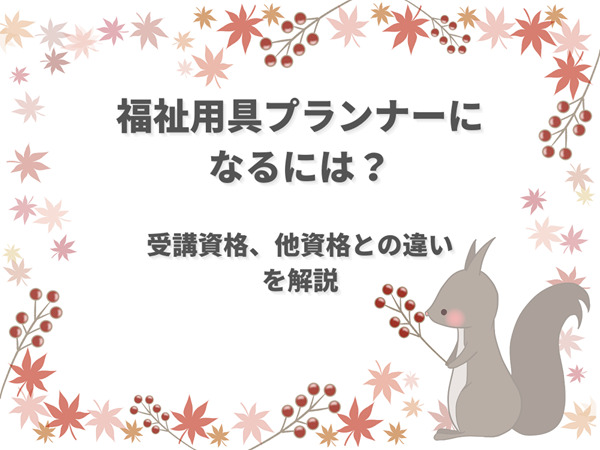


コメント