社会福祉士になる為には、社会福祉士養成施設に通う必要があります。
この養成施設には「一般」と「短期」の2種類があり、入学対象者が異なります。
そして、中には養成施設に通う必要のない方もいます。
当記事では、「社会福祉士養成施設とは何か」を詳しく解説します。
社会福祉士養成施設とは

社会福祉士養成施設とは、社会福祉士を目指す人の専門学校です。
国家試験受験資格の1つに、「社会福祉士養成施設の学習課程の修了」が定められてます。
言い換えると、社会福祉士の受験資格を得る為の学校ですね。
「一般養成施設」と「短期養成施設」の違い

社会福祉士養成施設には「一般」と「短期」があり、学習期間や対象者が異なります。
好きに選べるワケではなく、大学での履修科目や実務経験で通うべき学校が違います。
また「福祉系大学で指定科目を履修した方」は養成施設に通う必要はありません。
| 養成機関に通う必要がない |
|
|---|---|
| 社会福祉士短期養成施設 (卒業まで6カ月以上) |
|
| 社会福祉士一般養成施設 (卒業まで1年以上) |
|

短期養成施設は、卒業までの期間は6カ月以上が目安。
主に福祉系大学で基礎科目を履修した方、福祉事務所等で実務経験がある方が対象です。
一般養成施設は、卒業まで1年以上かかります。
一般大学や高卒者など、上記条件に該当しない方はこちらに通う必要があります。
一般養成施設だと1年6カ月程度が目安となるようです。
社会福祉士養成施設の入学条件

養成施設の入学条件は短期と一般で異なり、下記のような条件が設定されてます。
- 大学や短大の卒業者
- 相談援助の実務経験者
社会福祉士の受験資格には、養成施設と別に相談援助の実務経験も必要です。
その必要年数は「何年制の大学・短大を卒業したか」で異なります。
4年制の場合は実務経験は必要なく、大学等を卒業してない場合は4年の経験が必要です。
⇒社会福祉士の受験資格解説

簡単に言うと、それぞれ試験資格を得るための該当者が入学できるという事ですね。
そして国家試験の受験資格を満たす際は、まず実務経験面の条件から満たす必要があります。
※実務経験の条件を満たさないと入学できない
詳細は学校で異なる可能性がありますが、上記2種による選考が明記される事が多め。
通信講座や夜間学習も対応してる?

社会福祉士養成施設は、通信課程の学校が主流です。
スクーリングや実習はありますが、自宅でテキストを読んでの学習が中心です。
社会人の方でも、働きながら通う事が出来ます。
⇒WAM NET(社会福祉士養成施設)
社会福祉士養成施設での学習内容

社会福祉士養成施設では、「社会福祉士養成科目」と呼ばれるカリキュラムを学習します。
通信学習や授業の他、現場に赴いての実習も行います。
通信課程に入学した場合でも、スクーリングや実習が必要なので注意しましょう。
学習カリキュラム

社会福祉士養成施設では、一般で「全22科目(1200時間)」。
短期で「6科目(660時間」の学習カリキュラムが組まれてます。
現在は厚生労働省よりカリキュラム見直しが発表されており、新カリキュラムの導入が進んでます。
通信課程においては、実習時間の60時間増となります。
学習内容は「社会福祉士養成科目」とも呼び、福祉学校の「基礎科目」「指定科目」に該当。
福祉学校の科目履修者が短期や学習なしで済むのは、こうした理由からです。
通信課程でもスクーリングや実習がある

社会福祉士養成施設は通信制が主流ですが、在宅学習だけで修了する事はできません。
スクーリングと実習に参加する必要があります。
- スクーリング【少なくて5~6日程度】
- 相談援助実習【2施設以上かつ240時間以上】
スクーリングは学校に通っての面接授業ですね。
後述の実習を受ける必要がある場合、その指導のため10日以上に増える可能性があります。

相談援助実習とは、福祉施設等の現場で社会福祉士の仕事を実践で学ぶモノで、スクーリングとは別の扱いです。「実務24日以上かつ180時間」と定めがありますが、今後は240時間に増えます。
実習の現場は、福祉事務所や老人ホームなどが対象です。
養成施設と連携してる施設で行い、指導内容は現場や指導者でも異なります。
スクーリングの日程などは、養成施設により異なります。
通信制を選ぶ際も、通いやすい学校を選ぶよう意識しましょう。
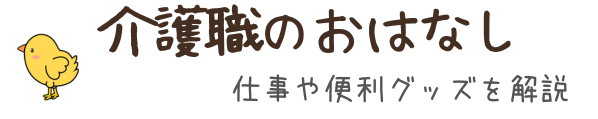
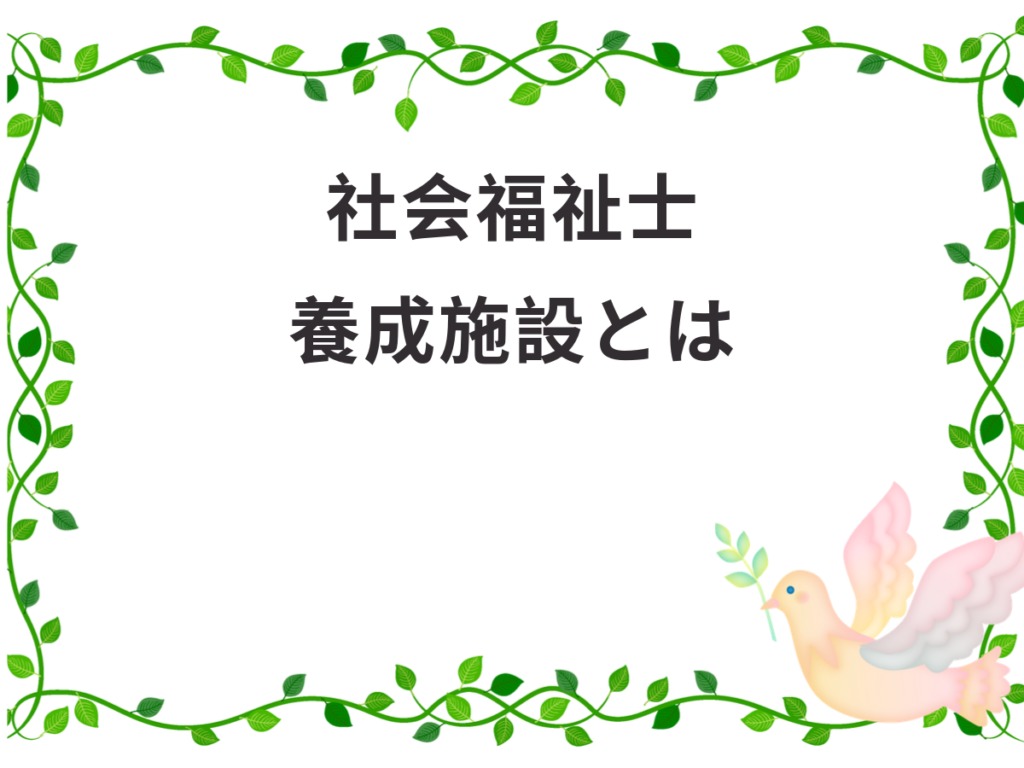
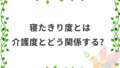

コメント