現在私たちには住みやすい家でも、年を重ねるとそれが変わってきます。
「お風呂場やトイレ、階段が辛い」等が分かりやすい例でしょうか。
高齢者や障がい者達の為、住まいの提案をするのが「福祉住環境コーディネーター」。
福祉・建築等を総合的に学んだ、福祉に関係した住宅改修の心強い味方です。
今回は、福祉住環境コーディネーターの検定試験の下記情報をまとめました。
- 各級の試験内容と受験資格
- 取得メリット
- 試験難易度と勉強方法(テキストや過去問、通信講座)
検定試験は2・3級までは、パソコンでの在宅試験も可能。
合格率も低くは無いので、ぜひこの機会に取得に挑戦してみて下さい。
福祉住環境コーディネーター検定試験とは

福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障害者の住環境について提案するアドバイザー。
東京商工会議所による民間資格で、福祉住環境コーディネーター試験に合格する事で取得出来ます。
取得には対応した級の検定試験を受ける必要があります。
2級までは誰でも受験できますが、1級は2級の取得が受験条件です。
住みやすい住環境を提案するアドバイザー

福祉住環境コーディネーターは、その人らしい生活が送れるよう住環境のアドバイスをします。
高齢者や障がい者に対し、個人に合った住環境を提案できるよう学習。
医療・福祉・建築について、体系的で幅広い知識を身につける事を目指します。
各分野を総合的に学ぶ為、それぞれの専門分野に理解を持った調整役という役割も持ちます。
主に福祉用具専門相談員、建築士などの方がスキルアップの為に取得してます。
福祉住環境コーディネーターの取得メリット

福祉住環境コーディネーターの2級以上に合格すると、自治体により「住宅改修が必要な理由書」が作成可能です。当資格はこれを目当てに受験する方が多く、分かりやすい取得メリットですね。
住宅改修において、介護保険による助成を受けるには、審査を通過する必要があります。
審査では「申請者にとって必要な工事なのか」等をみられ、「住宅改修が必要な理由書」は工事の必要性を証明する大事な書類です。
資格を活かせる仕事

福祉住環境コーディネーターという職種は少なく、単独で持っていても活かすことは難しいです。
その為、主に福祉・建築関係者が仕事や知識の幅を広げる為に取得してます。
例えば、下記の様な方のスキルアップに役立ちます
- ケアマネージャー
- 福祉用具専門相談員
- 建築士や宅地建物取引士
- その他介護・医療専門職
ただ資格自体の認知度は高く、2級については毎年2万人ほどの受験者がいます。

介護関係者が活かすとなると「福祉用具専門相談員」などですね。
受験者で最も多い職種です。※公式サイトの調査より
「手すり」や「スロープ」といった福祉用具の設置も住宅改修に関わり、その知識を活かす事が出来ます。
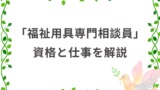
他にも、ケアマネなどの相談援助職も、スキルアップに繋がるでしょう。
建築関係などの仕事でも、福祉関係の知識が求められる場面があります。
受験申込方法

受験の申し込みは、「インターネット」で行います。
申し込みには、Eメールアドレスが必要です。
東京商工会議所ホームページより、希望する級の案内に従って進めて下さい。
※2・3級は年2回、1級は年1回の試験です
1級は会場受験となり、申し込み方法も湧かれています。
各級の受験料は下記
- 【1級】12,100円
- 【2級】7,700円
- 【3級】5,500円
福祉住環境コーディネーターの試験内容

福祉住環境コーディネーター検定試験の内容を説明します。
※2級と3級は共通点が多いので、2つに分け紹介します。
出題範囲は、後ほど公式テキストと共に紹介します。
「福祉住環境コーディネーター2級・3級」の試験内容と合格基準

福祉住環境コーディネーターの2級と3級は、パソコンを使っての試験です。
全国のテストセンターで受検するCBT。
また自分のパソコンで受検するIBT方式の2つから選ぶ事が出来ます。
福祉住環境コーディネーター2級・3級の試験内容
| 試験日 | 年2回 ・7月頃 ・11月頃 |
|---|---|
| 申込期間 | ・4月下旬~5月下旬 ・9月上旬~10月上旬 |
| 受験資格 | 誰でも |
| 試験内容 | マークシート方式 2時間 |
| 合格基準 | 100点満点中70点以上獲得 |
2級・3級は誰でも受験可能です。
試験問題は、正しい回答を選ぶ「マークシート方式」。
合格基準は100点中70点以上の獲得となってます。
試験回数は年2回で、両方とも同時期に実施。
「福祉住環境コーディネーター1級」の試験内容と合格基準
福祉住環境コーディネーター1級は、2級合格者のみ受験可能です。
※受験の申込登録時に2級証書番号が必要

他級と違い、1級は会場受験で行われます。
試験は11月下旬のみ年1回なことにも注意して下さい。
福祉住環境コーディネーター1級
| 試験日 | 年1回(11月下旬) |
|---|---|
| 申込期間 | 9月上旬~10月上旬 |
| 受験資格 | 2級合格者のみ |
| 試験内容 | ・マークシート方式 2時間(前半) ・記述式 2時間(後半) |
| 合格基準 | マークシート・記述式各100点満点、それぞれで70点以上獲得 |
1級ではマークシート方式に加え、記述式の問題も出題されます。
合格基準は100点満点中、70点以上の獲得が必要。
福祉住環境コーディネーター試験の「合格率と難易度」
検定試験の難易度を見てみましょう。
下記は、公式による各級の合格者データです。
※2020~2022年分
| 3級 | 約38~66.8% |
|---|---|
| 2級 | 約34%~67% |
| 1級 | 約5.6~17.7% |
※参考「東京商工会議所 検定試験情報(受験者データ)」より

福祉住環境コーディネーターの合格率は、3級でも約6割。
2級でも同程度でしたが、1級だと10%台となります。
難易度で言えば、2級までなら勉強すれば合格を狙える範囲ですね。
1級への合格はかなり難しいと言えます。
年別の振れ幅も見られますが、一層気を引き締めて勉強に臨む必要がありそうです。
福祉住環境コーディネーターの試験勉強情報

ここからは福祉住環境コーディネーターの勉強方法を紹介します。
試験勉強には、主に公式テキストを使用します。
各種各級のテキスト情報と共に、出題範囲や過去問もご紹介します。
3級のテキストと過去問

3級の試験は、「公式テキストに該当する知識」と「それを理解した上での応用力」が問われます。
| 3級の出題内容 |
|
|---|
過去問は様々な所から出版されてます。
例えば下記は、過去6回分の試験問題を収録。
解説には公式テキストの参照ページも記載され、テキストとの相性もバッチリです。
2級のテキストと過去問

2級の試験は、「3級の範囲および2級公式テキストに該当する知識」。
「それを理解した上での応用力」が問われます。
2級の勉強に加え、3級での内容理解も必要です。
| 2級の出題内容 |
|
|---|
2級も同じく、下記過去問が使いやすいかと思います。
ユーキャン通信講座なら「2級・3級」の学習に対応

もし2・3級の合格を目指すなら、通信講座でも学習可能です。
ユーキャンの通信講座だと、1つの講座で2・3級の両方に対応してます。
標準学習期間は6ヵ月、3級であれば1~2ヵ月で合格も狙えますよ。
東京商工会議所の情報では、2・3級の合格者の「勉強期間は2~3カ月」。
1日あたりの「勉強時間は30~1時間」という方が、最も多かったとの事。
1級のテキストと過去問

1級の試験では、「2級・3級の範囲および1級公式テキストに該当する知識」。
及び「それを理解した上での応用力」が問われます。
また記述式問題については、下記の様な内容となってます。
| 1級の出題内容 (マークシート方式) |
|
|---|
記述式試験では、実務能力(課題に対する提案力)などの、総合的判断力が問われます。
公式テキストに準拠するものの、法令制度については最新情報の理解を前提として出題。
下記の過去問であれば、記述問題にも対応してます。
福祉住環境コーディネーターは介護士に必要?
当ページでは介護職員を中心に情報発信してますので、「介福祉住環境コーディネーターが介護士に必要か」について考察します。
正直、介護士業務だけでは、なかなか住環境まで関わる事は少ないです。
ただ高齢者の生活をより側で観察し、支えているのも介護士です。
高齢者の生活を知ったうえで、アドバイザー的な立場もとれる可能性もあります。
確実に役立つとは言いませんが、決して無駄にはならない知識です。

世の中には、「介護士としての経験を活かせる職種」という物も存在します。
「ケアマネ」や「福祉用具専門相談員」ですね。
2番目に受験者に多い職種は「介護福祉士」でした。
介護福祉士取得後どうスキルアップすべきかは、結構多い悩みだと思います。
もし総合的な介護職としてのスキルアップを考えた時、この資格も選択肢に入ると思いますよ。
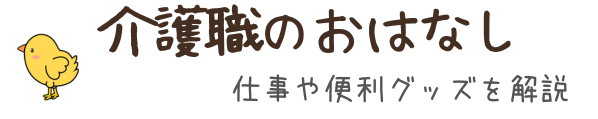
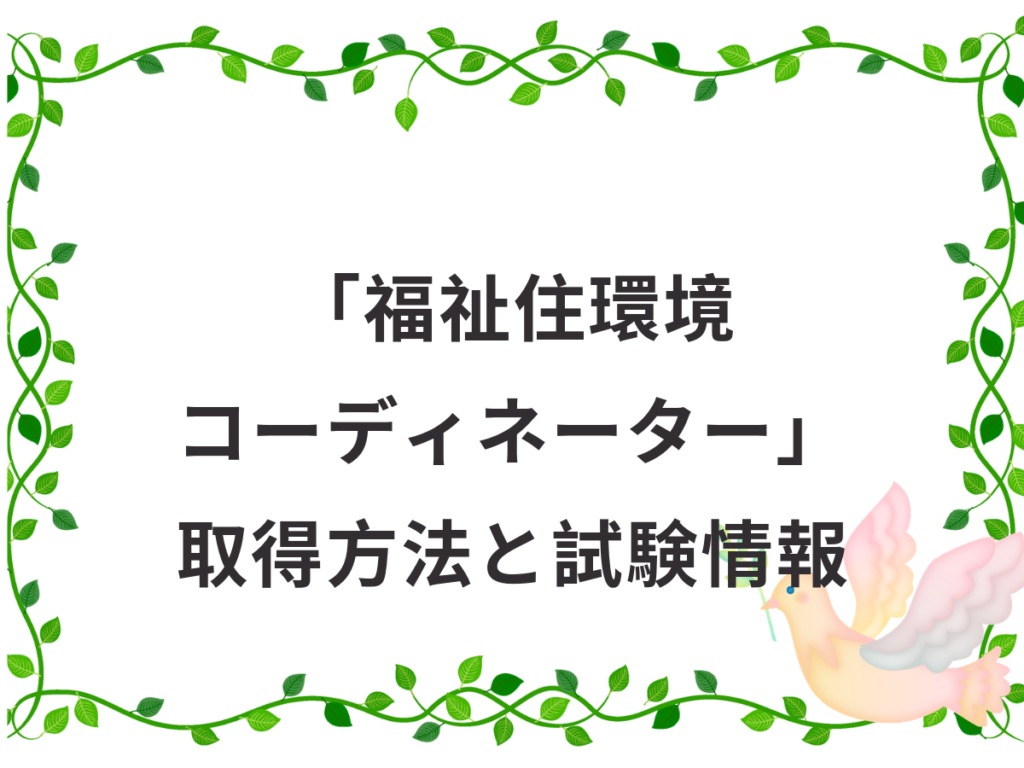


コメント