「社会福祉士」は福祉において、幅広く活躍できる国家資格です。
相談業務を中心としながら、社会福祉施設や行政機関など様々な職場で活躍する資格です。
ただ社会福祉士国家試験の受験資格は、少々複雑なモノとなってます。
「社会福祉士の受験資格や仕事内容」を中心に解説。
社会福祉士とは何かから、勉強方法まで網羅的に分かりやすく説明します。
社会福祉士とは

社会福祉士とは、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく名称独占の国家資格。
「ソーシャルワーカー」とも呼ばれ、相談・援助を主とした福祉の専門家です。
国家試験に合格する事で取得でき、社会福祉士として登録して名乗る事ができます。
福祉に関する相談・援助の専門家

社会福祉士は簡単に言うと、生活に困ってる人の悩みを解決に導く人です。
身体・精神上の障がい、環境ハンデ等を抱える人等が、日常生活を問題なく送れるよう手助けします。
こうした方々が必要とするサービスや援助を受けられるよう、サポートする人ですね。
社会的に困ってる人の相談を聞き、必要機関との連絡や調整をする。
または解決に向けた提案やアドバイスをしたりします。
高齢者や児童福祉などの狭い分野に限らず、福祉の中で幅広く活躍できる資格です。
社会福祉士の仕事内容

社会福祉士の仕事は、先述したような相談業務が基本です。
働く職場によりその対象は異なり、高齢者や児童、失業者など様々。
下記の様に、仕事内容も多岐にわたります。
- 地域包括支援センターの総合相談業務
- 医療現場の患者や家族を支援する「医療ソーシャルワーカー」
- 福祉事務所の「ケースワーカー」

社会福祉士は業務独占の資格ではなく、資格を持たずともこれらの仕事に就く事は可能です。
しかし福祉職種の資格要件に設定されてる事も多く、幅広い業務に携わることが出来ます。
配置が人員基準や加算条件となってる環境もあり、実質に必須という事も少なからずあります。
社会福祉士が働ける職場

社会福祉士は、その専門知識から幅広い職場で活躍しています。
- 老人ホームなどの「介護施設」
- 病院などの「医療現場」
- 「地域包括支援センター」や「社会福祉協議会」
- 「福祉事務所」や「各種相談所」
介護・医療現場だけでなく、行政機関でも働くことが出来ます。
福祉関係であれば、幅広い勤務先を選ぶことができますね。
少し前の資料ですが、厚生労働省によると社会福祉士の多くは「社会福祉施設」で働いてます。
介護施設や障がい者支援施設、児童福祉施設などですね。
※参考「厚生労働省(社会福祉士について)」
転職活動の面でも有用な資格です。
社会福祉士の受験資格

社会福祉士の受験資格を得るには、大きく下記2種の条件が必要です。
- 社会福祉士養成施設の学習課程を修了
- 相談援助の実務経験
「通うべき養成施設」や「実務経験の必要年数」は、人により異なります。
下記は社会福祉士の受験資格を得るルート図。

最長の場合、「一般養成施設で1年以上の学習」と「4年間の実務経験」が必要です。
複雑に見えますが、「社会福祉士の養成施設」と「相談援助の実務経験」に注目すればOK。
「自分がどれだけの学習・実務経験」が必要かを考えると分かりやすいです。
それぞれの条件を見ていきましょう。
「相談援助の実務経験」を積む

社会福祉士の受験資格にまず必要なのが、相談援助の実務経験です。
その必要年数は、何年制の学校を卒業したかで決まります。
後述する「養成施設の入学条件」にも関わるので、まずこちらを満たす必要があります。
| 実務経験の必要年数 | 該当者 |
|---|---|
| 必要なし |
|
| 1年 |
|
| 2年 |
|
| 4年 |
|
4年制大学の場合は、一般大学でも実務経験は必要ありません。
また社会福祉主事養成機関は、2年制の扱いとなり2年間の実務経験が必要です。
相談援助の実務経験について

対象となる実務経験については、分野ごとに施設種類と職種が決まっています。
以下に例を挙げます。
| 児童分野 | 児童相談所の保育士、児童指導員、職業指導員など |
|---|---|
| 高齢者分野 | 介護支援専門員、生活相談員など |
| 障害者分野 | 生活支援員、ケースワーカーなど |
| その他の分野 | 更生施設の生活指導員、保健所の精神保健福祉相談員など |
| 現在廃止事業の分野 | 知的障害者デイサービスセンターの相談員など |
基本的には、該当分野における「相談援助の業務」が対象です。
長くなるので、詳しくは公式HPでご確認ください。
社会福祉士の養成施設を卒業する

社会福祉士養成施設とは、社会福祉士となる為の専門学校です。
社会福祉士養成施設には、学習期間が6カ月以上の「短期養成施設」。
学習期間が1年以上となる「一般養成施設」があります。
自分が「どの社会福祉士養成施設に通うべきか」は、下記表をご覧ください。
| 養成機関に通う必要がない |
|
|---|---|
| 短期養成施設 |
|
| 一般養成施設 |
|
社会福祉士養成施設について、詳しくは下記記事もご覧ください。

ここでいう福祉系大学は、受験資格における「指定科目」と「基礎科目」を履修できる学校です。
上記科目は養成施設での学習内容となり、科目履修者には免除があります。
社会福祉主事養成機関とは、社会福祉主事任用資格を得る為の学校です。
これはケースワーカーや生活相談員として働けるようになる資格ですね。
査察指導員とは福祉事務所で、生活保護の受験資格を調査する職員です。
その他には「児童福祉司」、「身体(知的)障がい者福祉司」も実務経験として認められます。
社会福祉士の国家試験内容について

社会福祉士の国家試験は、年1回のペースで2月上旬に行われます。
試験内容は5択の選択式で、全18科目。
その一部は「精神保健福祉士の内容」と共通してます。
社会福祉士国家試験の「出題内容と合格基準」

社会福祉士国家試験の形式は、5択の選択問題です。
出題数は150問で総時間は240分。
配点は1問1点の150点満点です。
試出題される試験科目は、下記の18科目。
- 【共通科目 11科目】
- 人体の構造と機能及び疾病
- 心理学理論と心理的支援
- 社会理論と社会システム
- 現代社会と福祉
- 地域福祉の理論と方法
- 福祉行財政と福祉計画
- 社会保障
- 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
- 低所得者に対する支援と生活保護制度
- 保健医療サービス
- 権利擁護と成年後見制度
- 【専門科目 7科目】
- 社会調査の基礎
- 相談援助の基盤と専門職
- 相談援助の理論と方法
- 福祉サービスの組織と経営
- 高齢者に対する支援と介護保険制度
- 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
- 就労支援サービス、更生保護制度
合格基準は、問題の総得点の60%程度で、上記18科目全てで得点がある事です。
合格ラインは試験毎に難易度補正が入り、それにより上下します。
.jpg)
試験科目には共通と専門があり、「共通」の11科目は精神保健福祉士との共通科目を指します。
既に精神保健福祉士の資格を持ってる方は、共通科目が免除となります。
その場合、専門の7科目67点満点の試験となります。
科目免除を受けた場合、試験の費用もその分安くなります。

受験方法について

社会福祉士の受験申し込みは、「社会福祉振興・試験センター」より可能です。
まずはホームページより「受験の手引き」を取り寄せて下さい。
インターネットか郵便はがきで請求することができます。
必要書類を用意し、受験申込期間内に提出しましょう。

また受験資格を満たした方法により、必要書類が異なるので注意して下さい。
期間に間に合うよう、申し込み手続きは早めに進めましょう。
受験申込期間は、9月上旬~10月上旬が目安となってます。
※ご自身でも必ず確認してください。
申込期間前に「受験の手引き」の配布が始まるので、早めに入手しましょう。
社会福祉士試験の合格率・難易度

社会福祉士試験について、過去の受験者と合格者の推移は次のようになっています。

近年の合格率は、25%~30%程を推移しています。
稀に30%を超すこともありますが、合格率はおよそ30%弱と考えてよいでしょう。
※参考「厚生労働省(第34回社会福祉士国家試験合格発表)」
決して無理な合格難易度ではありませんが、時間をかけた学習は必須です。
次項で学習情報も紹介するので、合格を目指してしっかり勉強しましょう。
社会福祉士の試験対策・勉強方法方法

社会福祉士の国家試験対策は、主に下記2つの方法で勉強する事となります。
- テキストや問題集で独学勉強する
- 通信講座などの社会福祉士講座を受講
学習にオススメなテキストや問題集、通信講座などの学習情報をお伝えします。
独学勉強に使える「テキスト」「問題集・過去問」

社会福祉士の国家試験においても、独学では下記書籍を使用します。
- テキスト(参考書)
- 問題集
- 過去問
どの試験対策においても、テキストを読みつつ問題集をとき知識を固める。
過去問で腕試しをする、という流れで進めるのがポピュラーです。
まずはテキストと問題集を用意し、学習を始めましょう。
.jpg)
使用するテキスト・問題集は、同一のシリーズを使うと混乱が少ないです。
福祉関係の試験対策本は、中央法規の書籍が定番ですね。
手始めの学習には、下記の社会福祉士国試ナビがオススメ。
オールカラーの分かりやすい解説で、知識のインプットにオススメ。
これから学習を始める方の参考テキストとなります。
上記書籍とリンクした社会福祉士試験の問題集。
読んで覚えた知識を書いて定着させるのに使います。
その他にも、「共通科目」「専門科目」それぞれに特化したワークブック等もあります。
また同出版社で過去問も発売してます。
5年分750問の大ボリュームで、解説も掲載。
試験前の確認に使用しましょう。
社会福祉士の試験対策講座(スクール・通信講座)

社会福祉士の勉強には、通信講座による試験対策講座もあります。
通信講座を使うメリットは、学習方法が分かりやすく質問等に対応してる事。
学習教材も一緒に入手できる事などですね。
今回は、ユーキャンの社会福祉士講座をご紹介します。
| 受講費用 | ・一括払い 59,000円(税込み) ・分割払い 4,980円 × 12回(12ヵ月) 計59,760円(税込み) ・送料無料 |
|---|---|
| 支払い方法 | ・郵便局 ゆうちょ銀行 ・クレジットカード ・コンビニエンスストア |
| 教材 | 【メインテキスト】5冊 【副教材】チェック&ドリル2冊、問題集、 ガイドブック資料集、DVD等 |
| 受講、学習期間 | 平均学習期間7ヵ月 |
| 添削課題 | 全6回 |
| 返品 | 教材到着後8日以内であれば可能 |
ユーキャンの社会福祉士講座は、7カ月の学習で合格を目指す内容です。
社会福祉士試験は出題範囲が広く、効率的な学習が必要になります。
教材も豊富で質問も受け付けてるので、勉強しやすい環境が整いますね。
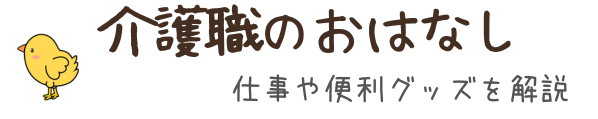



コメント