介護用の尿とりパッドについて情報を解説します。
昼や夜でのサイズ選びやパッドの種類、オススメ商品等の情報をまとめてます。
「パッドの使い方や選び方が分からない」と言う方は、参考にしてみて下さい。
記事の内容
- 尿取りパッドの種類と使い方
- パッドの選び方とオススメ商品
- 尿漏れの原因と対策
尿取りパッドはオムツに比べ安価なので、経済負担も軽く出来ます。
介護負担の軽減にも繋がるので、オムツ類を使用するならぜひ使用して下さい。
基本的な事から尿漏れ対策まで、総合的にお話ししていきます。
尿取りパッドとは

尿取りパッドとは、尿を吸収する使い捨てのパッド。
オムツやパンツの中に装着する事で、汚染を防いでくれます。
尿失禁時は尿取りパッドの交換のみで済み、高齢者や介護者の負担軽減にも繋がります。
※便失禁や尿漏れ時は、オムツや下着も交換しましょう
尿取りパッドのしくみ

上記は実際の尿取りパッドを広げた画像です。
吸水部の両サイドには立体ギャザーが付いており、尿漏れを防ぎやすいデザインになってます。
パンツ類に装着した時のずれ防止機能ですね。
またオムツ類と比べ安価なので、オムツ代の節約になり経済的です。
種類は色々とありますが、特別記載がない限り基本は男女兼用です。
商品により尿の吸収量や大きさも異なり、尿量や場面に応じ選ぶ事が出来ます。
尿とりパッドの基本的な使い方

尿取りパッドの使い方は簡単で、オムツやパンツの中に装着するだけです、
下記は、尿取りパッドの基本的な装着方法です。
尿取りパッドの使い方
- パッドの立体ギャザーをしっかり立てる
※ずれ止めテープがある場合、シールを剥がす - オムツ(リハパン)の立体ギャザーの内側に装着
- お尻から前にかけ、脚の付け根にそうよう引き上げる
パッドの立体ギャザーは、装着前に手でしっかり立たせます。
またオムツやリハビリパンツ自体にも、吸水パッドや立体ギャザーがあります。
尿とりパッドは、それらのギャザーの内側に装着して下さい。

上記は、テープ付オムツを広げた図。
このギャザーの中に収まるよう、パットを広げて設置します。
裏面のシールを剥がし、パンツの陰部にあたる位置に装着し固定します。
汚れた時は、尿取りパッドのみを交換すればOKです。
使用後は再利用せず、ご家庭で破棄して下さい。
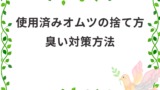
介護用尿取りパッドの種類と使い方

続いて、尿取りパッドの種類を見ていきましょう。
各尿取りパッドの違いは、主に尿の吸収量です。
また男性用や女性用、少し違った使い方をする物など…
特徴的な形状の種類も存在します。
種類による「尿の吸収量」の違い
.jpg)
尿取りパッドは、どのメーカーも排尿1回分を150mlとして設計してます。
※パッケージ等にも、「〇回分吸収」といった表現が使われます。
尿吸収量により、商品名には下記表現がよく使われます。
商品選びの際に参考になるかと。
| 吸収量が少ないタイプ (150~400ml) | レギュラー、スーパー |
|---|---|
| 吸収量が多いタイプ (600ml~) | ワイド、エクストラ 夜用(ナイト) |
排尿〇回とは言いますが、尿量はその時々により違います。
要介護者の生活リズムや尿量を見て、必要なモノを選ぶようにしましょう。
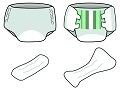
また尿とりパッドは、吸収量の多いほどサイズも大きくなります。
吸収量が少ないタイプは長方形ですが、吸収量が多いパッドはひょうたん型のワイドタイプが主です。

これは吸収量600mlのワイドタイプのパッド。
前やお尻にフィットしやすく、鼠径部にあたらない様にデザインですね。
基本的にはお尻側に広い方をあてますが、男性の場合は広い方を前にした方が尿漏れしにくい場合もあります。
尿取りパッドの「女性用」「男性用」の違い

介護用の尿取りパッドは、基本的に男女兼用です。
しかしながら、中には「女性用」「男性用」といった商品もあります。
- 女性用…所謂女性用ナプキン
小型薄型で長方形の尿取りパッド - 男性用…前方を広くガードする三角形が特徴
いずれも薄型で、少量の尿漏れが気になる方向けの商品ですね。
吸水量も100c以下のパッドが多くなります。
※上記は、男性用の20ccのパッド
性別を指定したパッドは、総じて「失禁が少ない方向けのパッド」です。
裏面にズレ止めテープがある商品も多く、シールを剥がし下着に貼り付ける使い方も可能。
リハパンだけでなく、普通の下着に使用する事も可能です。
吸水面が広い為、男女兼用で使えるといった感じですね。
「フラットタイプのパッド」の特徴と使い方

ここからは少し変わったパッドを紹介。
フラットタイプは、立体ギャザーが無く平面な長方形をしてます。
主な用途は、オムツ交換時にシーツを汚さないよう敷く形になります。
フラットタイプの用途
- 交換中の失禁対策
- 便失禁時のオムツ交換で
- 陰部洗浄時に
こんな時に敷いておけば、ベッドを汚れから守る事が出来ます。
またギャザーが無いので、オムツ等に装着するにはあまり適してません。
似た用途で使える介護用品に防水シーツもあります。
個人的には、防水シーツがあればフラットタイプは不要かと。
尿失禁があったりやオムツ交換が必要なら、ぜひ防水シーツを利用するようにしましょう。

「両面吸収パッド」の特徴と使い方

もう1つ、変わった商品に「両面吸収パッド」があります。
これは防水フィルムが無く、両面から尿を吸収できるパッド。
通常の尿パッドと併せて使用し、補助する役割を持ちます。
両面吸収パッドは、通常の尿取りパッドとしては使用しません。
防水フィルムが無いため、吸収した尿が下へ零れ落ちてしまいます。
尿取りパッドを補助し、尿漏れ防止に使うのが主ですね。
介護用尿取りパッドの選び方

それでは尿取りパッドの選び方をご説明しましょう。
まずは普通の尿取りパッドを使用しましょう。
色々とご紹介しましたが、ノーマルタイプがあれば基本的に困りません。
昼用と夜用で使い分ける

尿取りパッドは、吸収量が多いものほど価格も高いです。
「昼用(小さめ)」「夜用(大きめ)」と2種類用意した方が経済的。
排尿が多くなるタイミングを見て、使い分けましょう。
尿の吸収量(大きさ)については、下記表を参考にしてみて下さい。
| 尿量や失禁の少ない方 | 尿量や失禁の多い方 | |
|---|---|---|
| 日中 | 150~400ml程度 | 400~600ml程度 |
| 夜間 | 200ml程度~ | 1000ml程度~ |
長く介護士として働いてますが、大体こんな感じでしょうか。
夜間は交換しないものとして想定してます。
日中でも長く交換できそうにない時は、少し大きめの物を使用しましょう。
他にも、軽い尿漏れがある方へ50cc前後のパッドもあります。
ほぼ失禁がない方が備えに使うなら、こうした商品も選べます。
必要なサイズを上手く調整する事で、経済的にも肌トラブル改善にも効果的。
排尿ペースや交換頻度も見て選ぶ
.jpg)
尿取りパッドを選ぶ際は、下記ポイントを意識すると良いでしょう。
- 排尿量や排尿ペース
- オムツ・リハパンによる使い分け
- オムツ交換の頻度
基本的には、オムツカバーを使用してる方は吸水量の多い物。
オムツ交換頻度が少なくなる夜間は、特に吸水量の多いパッドを選ぶと良いですね。
対しリハパンを使用しトイレに行ける方は、比較し小さいパッドが選ばれます。
またトイレでの着脱も多くなるので、「ずれ防止テープ付」のパッドがずれにくくオススメ。
日中想定だと、ご本人の状況により下記サイズを目安にしても良いかと。
- 布パンツ使用(失禁量少なめ)…100~300cc (ずれ止め防止テープ付)
- リハビリパンツを使う…150~500cc
- オムツを使っている…500cc~

ただその人により、排尿ペースや量は異なります。
交換頻度など、ご家族の介護力などによっても選ぶべき種類は違ってきます。
オススメの介護用尿取りパッドは?

ここからは、介護でオススメしたい尿取りパッドを紹介します。
「リハパン用」と「オムツ用」に分け紹介しますので、パッド選びの参考にどうぞ。
「リハパン使用時」のオススメ尿取りパッド
リハパン使用時にオススメしたいパッドはこちら。
ライフリー パンツ用 尿とりパッド
こちらはリハパン用の尿取りパッドです。
「ずれ止め防止テープ」が付いてるシリーズですね。
上記は吸水量300mlの日中タイプですが、夜間用もあります。
サイズも豊富に揃ってるので、気に入ったら同じ種類で各サイズも用意できます。
施設の利用者様にも、愛用者が結構いらっしゃいますね。
ズレ止めシール付きの尿取りパッド

自分で尿取りパッドの交換ができる方には、ズレ止め防止テープ付きのモノも人気です。
例えば、下記の様なモノですね。
ポイズ 肌ケアパッド
こちらは女性向けのパッドで、「吸水量が少ない種類」が中心のシリーズ。
シールを剥がすだけなので、自分で簡単に装着できます。
普通の下着にも装着OKです。
多い物だと、300ccぐらいまでの商品も。
男女兼用のリハパン用であれば、こちらもオススメ。
ズレ止めシールを剥がす手間も無く、出してそのまま装着できます。
仕事でよく使いますが、しっかりズレを防止してくれます。
「オムツカバー使用時」のオススメ尿取りパッド

オムツカバーを使用する場合、リハパンに比べ吸水量のある物を選びましょう。
まず日中であれば、500~700ccぐらいから試すのが標準的な範囲かと思います。
今回は、700ccのタイプを紹介します。
アクティ ワイドパッド700
700ccぐらいのタイプから、ひょうたん形のワイドタイプが登場します。
尿漏れだけでなく便漏れにも強く、その点でもオススメです。

夜間の場合は、交換を行っている介護施設での標準が700cc程度。
交換の難しいご家庭では、「夜間用」と表記されたさらに吸水量の多いパッドがオススメです。
サルバ 朝まで1枚ぐっすりパッド強力吸収
こちらは1,800ccと、かなりの吸水量があるパッドです。
口コミでも「夜間も漏れない」と好評、使用者も安心して寝れているという声が多くありました。
大きすぎる方もいるでしょうが、夜間用としてまず試してみてはどうでしょう?
パッドの尿漏れ原因と対処方法

ここからは、尿とりパッド使用時の尿漏れ対策を紹介します。
パッドの使い方や尿漏れ防止の為に出来る事など…
よくあるシチュエーションをまとめ、Q&A方式で解説していきます。
大きいパッドを使用してるのに漏れる

大きいパッドを使用していても、尿漏れしてしまう事はあります。
大きいパッドで尿漏れするのは何故?
- 吸収量以上に排尿がある
- 排尿の勢いが強い
- 横を向いてたり、パッドが上手く当たっていない
まずは「パッドのどこが濡れているか」をよく確認して下さい。
濡れてない部分があれば、当て方に問題がある可能性もあります。

尿取りパッドは尿を吸収した後、内部を通って全体で吸収出来る仕組みになってます。
一部分しか濡れてないのに漏れてしまう場合、隙間が出来ている可能性が高いですね。
- 立体ギャザーが立っていない
- パンツやオムツサイズが大きすぎる
- あてる時に隙間ができ、ズレてしまっている
パッドサイズの見直し前に、これらの問題が無いかもう一度見直してみましょう。
オムツによるサイズの違いは、ウエストだけでなく「丈」も違います。
大き過ぎるオムツは陰部とパッドを密着させにくく、漏れの原因となります。
「大きいパッドの使用」か「交換回数を増やす」事を検討しましょう。
「排尿の勢いが強い時」も尿漏れが発生しやすい

一気に排尿があった場合、パッドの吸収が間に合わず漏れてしまう事があります。
横を向いて寝てる時も、尿漏れが発生しやすい場面です。
隙間が発生しないよう注意し、お肌と密着させましょう。
一気に排尿がある方向けに、高速吸収のパッドがあるので紹介しておきます。
パッドの重ねあては効果がある?

尿取りパッドを2枚重ねるような使い方は効果がありません。
パッドの裏面は尿を通さず、横に漏れていくので吸収量は変わりません。
間違ったパッドの使い方なので、注意しましょう。
あるいは、両面吸収パッドを使用するのも良いですね。
また交換が楽という理由で、2枚あてをする方も稀にいます。
パッドを引き抜いて交換すると、摩擦で高齢者の肌を傷つけてしまいます。
オムツやパッドを引っ張るのも間違ったオムツ交換方法なので、しないようにして下さい。
尿量による尿漏れが多くなるタイミング
介護度が高く、失禁の多い方を中心に見てきましたが…、
「寝ている時」が尿量も失禁回数も多いですね。
これは夜に限った事ではなく、昼間にちょっと横になって休んだ時も当てはまります。

また下記のような時も、尿漏れしやすいので注意しましょう。
尿漏れが多くなる時
- 過剰に水分を摂った
- トイレやオムツ交換の間隔が開いた
- 排便コントロールの為、下剤を増やした
ご本人の「排尿パターン」と「トイレ(オムツ交換)の間隔」を見て、使用するパッドを選ぶと良いです。
普段より下剤を増やした時も、水様便による漏れが予想されます。
大きめのパッドを使用する等して対策しましょう。
衣類やシーツを汚してしまいがちなので、防水シーツや介助方法の工夫等で防ぎましょう。
トイレでの排尿も促してみる

パッドから逸れますが、トイレやオムツ交換時に排尿を促すのも尿漏れ防止に繋がります。
また座った姿勢は排尿・排便を促すのに効果的。
失禁がある方でも、トイレで排尿できるようアプローチしていくと失禁量を減らせる事があります。
家の環境などでトイレを諦めているなら、ポータブルトイレ等の使用も検討しましょう。
まとめ

今回は「介護用の尿とりパッドの種類と使い方」をご説明しました。
基本的には、通常の男女共用でギャザー付きタイプを用意すれば良いです。
最後に要点をまとめておきます。
記事の要点
- 尿とりパッドは、オムツやリハビリパンツのギャザー内側に装着
- 「昼用」と「夜用(大きめ)」の2種類あると便利
- 尿量に対し丁度良いサイズを選ぶと、肌にも経済的にも優しい
- 排尿リズムを掴み、トイレでの排尿を促す等で尿漏れ防止を
尿とりパッドは、大きければ良いワケではありません。
その人の尿量に合ったサイズを使うのが、総合的にメリットがあります。
ご本人について理解を深め、ケアの改善に役立てて頂ければ幸いです。

またオムツ交換の際には、パッドをはじめ排泄用品を整理しておくと便利です。
オムツ類は場所も取りますし、毎日の交換も負担となります。
関連用品をまとめておく事で、介護負担の軽減にも繋がりますよ。

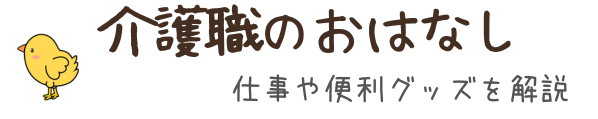
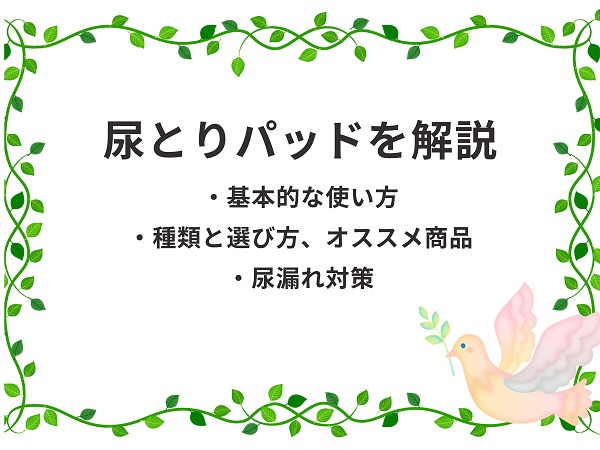

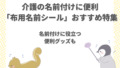
コメント