介護職の仕事は、利用者とのコミュニケーションが大事な仕事です。
利用者が安心し、気分よくサービスを利用できるかは介護職にかかっています。
また信頼関係を築く事で、自分の「働きやすさ」や「仕事の質」を高める効果もあります。
介護福祉士の経験を活かし、現場重視の実践的なコツを紹介します。
職員同士の人間関係にも、使える内容と思いますよ。
介護職における「コミュニケーションの必要性と効果」

介護職を経験して思うのは、やはりコミュニケーション能力は必要だという事。
もっと言えば、「利用者様からの信頼」ですね。
何故かというと、利用者と自分の為です。
利用者様の信頼を得る事で、仕事のしやすさや質を大きく高める事ができます。
苦手意識がある方も、ちょっとしたコツを意識するだけで改善可能です。
信頼関係が仕事の質を高める

介護ではコミュニケーションの取り方により、相手の反応が異なる事があります。
コミュニケーション上手になる事で、利用者様に快適に過ごしてもらう。
さらには、自分も気持ちよく働く事が可能になります。
- お互いに気分よく接する事が出来る(介護拒否が減る)
- 仕事の質と相手の満足度が高まる
- 自分の評価が高まる
介護職(特に介護士)は、現実として時に相手の望まぬ事もせねばなりません。
例えば、「水分を摂って欲しい」「入浴して欲しい」など

そんな時、返ってくる言葉は「嫌だ」です。
…ところが、利用者との関係によっては、「そうね」と笑顔が返ってきます。
不思議なもので、人が変われば対応が180度変わる事もあるんです。
信頼関係の構築、言葉選び、それらで「相手の満足度」「働きやすさ」が激変します。
職員同士の人間関係にも影響

信頼の積み重ねで、利用者の生活の質が高まれば、仕事の質も高まります。
利用者からの評価は、いずれ介護職としての評価にも繋がります。
関わった人が皆、自然と穏やかな表情になる。
こんな人が評価を受けるのは、想像できると思います。
また職員も利用者も同じ人間です。
利用者に好かれる術が分かれば、職員間の信頼関係も構築できるはず。
仕事での人間関係は、自分の為にも意識すべきでしょう。

当記事でお話ししたいのは、難しい事ではありません。
「介護職が利用者に気分よく生活してもらう方法」ですね。
もっと言えば、自分がスムーズに気分よく働く為の方法でもあります。
介護職に「利用者とのコミュニケーションの基本とコツ」

介護職が利用者に信頼されるには、安心・安全な存在であることです。
味方であり共感してくれる人、不安を拭ってくれる存在ですね。
その為には、無害な存在だと認識してもらう事も大切です。
その為の具体的な方法や理想像は、利用者により異なります。
…なので介護職には、観察力も大切ですね。
「相手の立場で考える事」が出来ればOKです。
介護職が覚えたい便利な言葉3つ

10年近く介護士として勤務した中で、特によく使うのが下記3つの言葉。
- 大丈夫
- ありがとう(感謝)
- ごめんなさい(謝罪)
高齢者とのコミュニケーションにおいて、かなり便利な言葉達です。
他職員と良好な関係を築くのにも必須です

感謝と謝罪は、言わずもがなですね。
ちょっと多いくらいでちょうど良いです。
これらの言葉は、不快な気持ちを緩和し、承認欲求も満たします。
口にしてみると、自分でもちょっと「まぁいいか」という気持ちになりませんか?
利用者だけでなく、自分の感情コントロールの為にも口にすべきです。
大丈夫は万能!

上記3つの中で、特に万能なのが「大丈夫」という声掛け。
ちょっと言い方を工夫するだけで、色々な役目を果たせます。
- 相手への気遣い(大丈夫?)
- 安心させる(大丈夫!)
この他にも、「貴方の存在をちゃんと気にしてるよ」というアピールにも使えます。
介護施設の高齢者は、その多くが孤独や不安を抱えています。
多くの時間や言葉は無くとも、ちょっとした一言で救われるのです。

これは「職員への気遣い」にも便利。
ズルい言い方ですが、これだけで好感度アップに期待できます。
ぜひ仕事の中に取り入れて頂ければと思います。
利用者主体の会話をする

利用者との会話では、下記の事を意識しましょう。
これは私が、利用者・職員に対して意識してる事です。
- 一方的な話はしない
- 自分の個人情報は話さない
- 余計な詮索はしない
- 相手のしたい話はちゃんと聞く
家庭の事など個人の深い話は、自分からは聞きませんし言いません。
相手のタブーに触れそうな話題は、なるべく避けます。
その代わり相手が話したそうな話題は、きちんと聞きます。
ただ聞くだけでなく、適度にこちらから尋ねて話を広げたりもしますね。

ふざけるぐらいがお好きな方なら、冗談も言いますよ。
「ご飯が美味しくない」なんて聞けば、同意してあげたりもあります。
正論が正解とは限らない

相手の感情の前では、正論はあまり意味を持ちません。
- 清潔の為に入浴が必要
- 水分を摂らないと脱水になる
- あなたは失禁してパンツが汚れている
こんな言葉も、相手が「嫌だ」「必要ない」と思ったならそれが真実。
そんな時に介護職は、相手が納得して動ける「理由」を見つける事が求められます。
例えば、「お尻の傷に薬を塗りたい」。
「飲み物作るけど、何が良いですか?」と聞く、などですね。

また失禁があったなど、伝える必要が無い事実もあります。
先述の通り、「大丈夫」とだけ言っておけばよいです。
その為には、「声掛けのバリエーション」を場面毎に持っておくと便利。
本や他人の対応などを参考に、言葉の引き出しを増やすと対応力アップします。
ご本人の精神状態さえ安定してれば、明るく夢を見させてあげる返答も必要かと。
言葉を使わないコミュニケーション方法

高齢者相手の場合、「伝わったかどうか」にも注意しなくてはなりません。
そんな不安を解決するには、言葉以外のコミュニケーション方法も知っておきましょう。
- ジェスチャー
- アイコンタクト
- 筆談
少し例を出しましたが、特に効果的なのが「ジェスチャー」と「アイコンタクト」。
試して貰うと分かりますが、かなり幅広く使える方法ですよ。
先ほどの「大丈夫」もこれらの方法で伝えられます。
表情やジェスチャーを組み合わせれば、色々なことが伝えれらますよ。

高齢者は耳の遠い方も多く、せっかくの言葉がなかなか伝わりません。
無理して言葉で伝えると、語気が荒くなってしまいます。
「目を合わせ微笑むだけでOK」、という場面も結構多いですよ。
ぜひ有効活用して頂ければと思います。
利用者との距離感を意識し平等に接する

もう1つアドバイスとして、「利用者との人間関係的な距離感」も意識する事です。
要するに、構われ過ぎるのも嫌な人がいるという話です。
基本的には、「構って欲しい」「寂しい」という方が多いのですが…
1人の時間を大切にしたい方もいらっしゃいます。
また介護拒否があった場合、「離れる」事でしか解決が難しいこともあります。
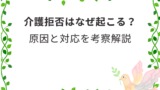
相手が望む距離感を上手く掴む事が大切ですね。

また介護士は、あまり利用者と親密になりすぎるのも良くありません。
あくまで「介護士と利用者」という関係である事を忘れないで下さい。
利用者それぞれに対しても、平等でなくてはなりません。
「必要なケアを気分よく受けられる存在」を目指しましょう。
信頼関係は時間をかけて築くこと

介護職員が利用者と良い関係を築くには、時間が必要です。
信頼関係は、1日や2日では出来ません。
焦らずじっくりと時間をかけましょう。
何事も小さな積み重ねが大切です。
認知症の方も職員を覚えている
認知症で短期記憶が弱い方も、ちゃんと職員を覚えてくれます。
自己主張が出来ない方も同様です。

数分前の事が分からない様な方も、時間をかければちゃんと職員の顔を覚えてくれますよ。
この人は個人を覚えてくれないと思わず、1人1人としっかり向き合って下さい。
認知症による介護拒否の緩和にも繋がりますよ。
苦手な利用者への対応方法
介護職が働きやすくいる為には、苦手な利用者を作らない事です
皆様の職場にも、こんな方がいると思います。
- すぐに怒る
- 介護拒否が強い
- 気難しい
苦手な方の対応方法は、慣れるか逃げるかのどちらかです。
長期的な目線で見ると、「慣れるべき」と思いますね。

積極的に対応してれば、いつかはお互いに慣れる日が来ます。
回数をこなせば、上手く対応できるコツも分かってくるでしょう。
仕事での苦手は、早めに潰しておいた方が自分の為です。
他職員の話を聞くなどして、良い所を取り入れていきましょう。
それで「失敗しても黙っててやっから」と、冗談を言われる程になったりもしたり。
介護拒否には慎重に対応する
注意点すべきなのが、焦って無理に対応しないこと。
時間を置いたり、他職員に任せる事が正解の場合もあります。
時には「退く」事も必要です。

介護拒否は、解決が難しい問題です。
無理して対応すると、事故やケガの原因になるので避けましょう。
そのうえで、引き際も慎重に判断する事が大切ですね。
利用者との関係構築に必要な能力とは
ここまでの内容で、利用者に信頼される介護職の人物像が見えてきたと思います。
最後の総括として、良好な人間関係構築に必要な能力を考えてみましょう。
- 観察力
- 柔軟性や共感性
- 聞く、待つ姿勢
- 積極性
観察力は分かりやすいですね、相手の気持ちや状況を察する力です。
柔軟性や共感性は、「無理でも1度は受け入れる姿勢」と言えばいいでしょうか。
共感し、代替案を出す等の能力ですね。
語彙力もあると、より説得力も増します。

そして相手の話をよく聞き、応じてくれない時も焦らない。
こちらの要望だけを通さず、相手のタイミングを待ってあげる事も大切です。
仕事に飲まれず、気持ちに余裕を持って働く余裕も重要です。

ただこれらをいざ実践すると、結構ストレスも溜まります。
感情コントロールや上手く流す等、ストレスをためない為の技術も必要になります。
最後に
今回は「介護職と利用者のコミュニケーション」についてお話ししました。
- 利用者の信頼は、仕事の評価・やりやすさに影響する
- 良好な関係を築くには、安心・安全な存在であること
- ジェスチャーやアイコンタンクト等、言葉以外のコミュニケーション方法を知る
- 苦手な利用者を作らない様意識し、相手を恐れない
- 関係構築には時間がかかるので焦らない
当記事で述べた振る舞いは、利用者だけでなく自分の仕事も助けます。
これらを意識せずに仕事として自然に出来るようになった時、介護職として自信を持って良いです。
また正しい介護技術・知識も、利用者と自分を守ります。
安心・安全な存在を目指し、併せてスキルアップを図りましょう!
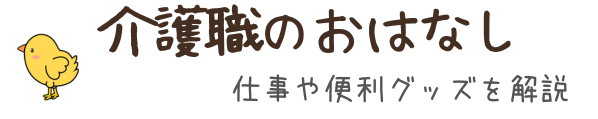
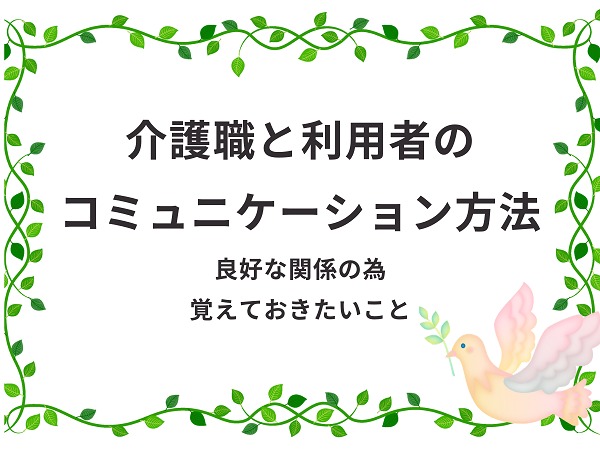

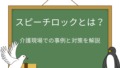
コメント