介護現場では、どうしても避けられない介護事故。
介護事故が起きた時は、家族報告や事故対策の為、その経緯を明らかにする必要があります。
そうした目的の為、必要になるのが介護事故報告書の作成です。
今回は、介護事故報告書の書き方を介護士目線で解説。
報告が必要な時や記入例、事故防止などについてお話していきます。
介護事故報告書とは

介護の事故報告書とは、利用者に関する事故があった時に作成する書類です。
- 転倒や転落
- 誤薬
- 原因不明だが、ケガや骨折等が発覚した
主にこの様な事があった時、事故報告書が必要になります。
介護事故報告書に記入する内容

介護事故報告書には、下記等の内容を記入し作成します。
- 事故のあらまし(事故の発生・発見の経緯)
- 事故発見後の対応
- 原因と再発防止策
- 家族への連絡
事故報告書の書式は職場で異なりますが、およそ上記内容がテンプレとなります。
事故報告書は、事故原因を明らかにし、再発防止の為に作成します。
事故報告書には、事故の発見からその後の対応・必要になった処置等の内容を書きます。
また原因や再発防止策を考え、記入する事も必要です。
家族連絡は相談員やケアマネ等が対応し、記入する事も多いですね。
介護事故発生時の対応の流れ

事故発生時には、医療・看護職への状態報告やご家族様への報告が必要です。
その流れは、職場により決まっているのでよく確認しましょう。
介護士としては、まずは看護師へ報告。
その後、ケアマネや相談員へ報告するのが一般的な流れです。
対策までは難しくとも、事故経緯はその日のうちにまとめてしまいましょう。
記入後は所属のリーダーを通し、各部署へ配布されるのが一般的な流れですね。
事故報告が必要な事例

冒頭で「利用者に関する事故」と述べましたが、これは職員の介助ミス時だけではありません。
利用者様が自分の意志で動き、事故が起きた時も作成します。
現場でよくある事故報告例を挙げると、下記があります。
- 自分で歩いて尻もちをついた
- 配膳ミスで他利用者の食事を提供した
- 介助中にケガをさせてしまった
- 原因不明のケガ、皮下出血を発見した
こんな時も事故報告が必要です。
後述しますが、ケガや異常がない場合も報告書を書きます。
「転んだかもしれない」など、その可能性がある時も報告があるのが望ましいですね。
介護事故の定義

厚生労働省の資料に、介護事故の定義があるので紹介します。
施設内および職員が同行した外出時において、利用者の生命・身体等に実害があった、
または実害がある可能性があって観察を要した事例
(施設側の責任の有無、 過誤か否かは問わない)
つまり「事故が発生したが無事だった」という時も、事故報告書が必要という事。
- 「尻もちをついたが、ケガや異常はない」
- 「落薬があったが、何も問題は起きていない」
「転倒したが無事なので報告しない」のは、NGなので注意。
「薬が落ちてた(落薬)」など、事業所により対応が分かれる事もあるみたいです。
※私の知る限りでは事故扱いが多いですね
内出血の発見について

高齢者に多いのが内出血です。
血液の薬を飲んでいる方もおり、日常生活動作の中でも簡単に出来てしまう方もいます。
原因や対策を立てる必要もありますが、そのつど事故報告書を書いていてはキリがない事も。
そこで職場によっては、より記入しやすいよう内出血発見報告書を用意されたりします。
- 内出血の場所、大きさ
- 原因(推測含)と対策
内出血に特化した簡易報告書といった感じですね。
事故報告書は誰が書く?

事故報告書を作成するのは、基本的に事故の第一発見者です。
他職員のミスが原因だとしても、発見者が記入します。
職種関係なく作成せねばなりませんが、実際は介護士が書く事がほとんどですね。
介護事故報告書の書き方

事故報告書の書き方をご紹介します。
事故報告書には、下記の様な記入欄が用意されています。
- 利用者の情報(名前や年齢、介護度など)
- 発見者名、発生日時、発見場所
- 事故内容(文章)
- 必要になった処置や家族連絡
- 原因や再発防止策
事業所で内容や書式が異なりますが、こんな感じです。
現在はPCの介護ソフト上で作成する事が増えてます。
職場によってはエクセル等の使用、あるい原紙に記入する事もあります。
事故時の様子を図で書いて示す事もあります。
事故内容は分かりやすく端的に

報告書を作成する時、頭を悩ませるのは事故内容の説明文。
限られたスペースで、事故の様子を分かりやすく書かねばなりません。
その為には、次のような事を意識しましょう。
- 5W1Hを意識
- 不必要な情報は捨てる
- 適度に区切る
これを見たまま、ありのまま書くのがコツ。
特に「いつ・どこで・誰が・どうした」という情報を必ず含めましょう。
職員の感情など、不必要な情報は書きません。
難しい専門用語も不要ですので、必要な情報を書きつつ、なるべく短くまとめましょう。
「分からない事」は無理に特定しない

介護事故の発生時には、その詳細が分からない事がよくあります。
- 転倒していたが、経緯が不明
- 落薬があったが、誰の薬か分からない
- 皮下出血があったが、原因が不明
原因や経緯が分からない時は、それをそのまま書いて良いです。
憶測で物事を断言するぐらいであれば、詳細不明として構いません。
事故内容の記入例

実際の記入例をいくつか見てみましょう
介護現場で多い、「転倒」と「薬」の事故で紹介します。
せっかくなので、内容だけでなく原因と対策も書いてみました。
※雰囲気を伝えたいので、対策等が適切かは無視して下さい
転倒事故の例

利用者様の転倒は、現場で特に多い事故。
下記は、利用者が移乗中に尻もちをついた転倒事故例。
| 事故内容 | 13:00頃、〇様の居室より物音聞こえ訪室、ベッド側で尻もちをついている〇様を発見。 |
| 対応 | 看護師に連絡し共にボディチェック、バイタル測定。 |
原因 |
|
| 対策 |
|
こんな感じですね。
実際には、バイタルチェックも行うので、血圧等の数値記入が必要な事も。
省きましたが、相談員等からご家族への連絡もします。
詳細が分からない時は、それも書いて良いです。
「経緯は不明。周囲の様子から、車イスからベッドに移る際、尻もちをついたと思われる」など
誤薬事故の例
薬の事故も、現場ではよくあります。
下記は、薬を違う人に飲ませた(誤薬)例。
| 事故内容 | 8:20 A様の服薬介助を終え薬袋をみると、B様の薬を飲ませてしまった事に気が付く。 バイタル測定実施、バイタル・気分不快共になし。 8:30 看護師による様子観察、そのまま経過観察となる 事故時、職員は早番のみ。 |
原因 |
|
| 対策 |
|
血圧や血液など、大事な薬を飲んでいる方も多く、特に注意が必要です。
「拒否があり飲めなかった」という時は、事故扱いにはならないかと。
※ただし看護師への連絡など、大半の職場では業務ルールがあるので注意!
何にせよ、薬に関しては敏感・慎重に対応しましょう。

拒否も含め、事故対策はすぐ立てる事が難しい事もあります。
他職員も巻き込み、一緒に考えましょう。
事故時には介護記録にも記入

介護事故があった時には、介護(ケア)記録にも内容を書きます。
先ほどの事故内容と同じような内容で大丈夫です。
問題が無くとも、その後の経過についても記入しましょう。
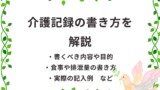
日誌などにも書き、他職員と共有しましょう。

たとえ事故で無くとも、様子や変化はマメに「記録・申し送り」するのが望ましいです。
その際には、見た人がすぐ理解できる文章で書きましょう。
事故報告だけでなく、普段の記録でも必要な事ですね。
介護記録の書き方も、この機会に学んでおきましょう。
介護事故を防止するには?

介護事故をゼロにする事は、はっきり言って難しいです。
どんなに注意していても、どこかでミスはしてしまいます。
利用者様の生活の場である以上、転倒する事だってあります。
しかし介護職としては、できる限り事故を減らす為に取り組まねばなりません。
多くの職員に事故の可能性を知らせ、危険への意識を広めていく必要があります。
忙しい時ほど慎重に
職員個人で出来る事としては、危険へのアンテナを張り、気持ちに余裕を持つ事。
特に重要なのが「気持ちの余裕」、焦りはミスの元です。
経験上、自分のミスで事故を起こす時は、気持ちに余裕のない時です。

「時間が無い、急がなきゃ!」、こんな時にミスをします。
介護では、よくある場面ですよね。
スピード命みたいな職場もあるので、焦ると思いますが…
そんな時ほど慎重になりましょう。
動じずに、焦らずじっくりやるのも、出来る人の動き方です。
ヒヤリハットを書く

説明中に少し話しましたが、ヒヤリハットを書く習慣をつけましょう。
これは事故を防げた時、その可能性を感じた時に書く書類です。
ヒヤッとした、ハッとした時に書く
言い換えれば、事故や危険への気付き。
活用すれば危険意識を高めたり、事故対策を立てる事が出来ます。
「記録」「申し送り」で情報共有する

介護では、事故には至らずとも危険を覚える状態は多々あります。
なかには個々の職員では防止が難しく、医務や相談援助職の協力。
または、職員全体での意思決定が必要な場面も出てきます。
もし危険を感じたら、職員全体に問題を共有する取り組みをしてみましょう。
- 介護記録や日誌に内容を残す
- 朝礼などで申し送りする
- 上司などに問題提起する
事故防止に関し、個人で出来る事は限られています。
先のヒヤリもそうですが、危険だと思った事はチーム全体に共有しましょう。
日頃から危険をチームに認識させる事で、いざという時に身を守る事にも繋がります。
事故の原因や対策も、1人で考える事はありません。
職場全体の問題として、積極的に共有するようにしましょう。
犯人探しはしない

また事故発生時に注意したいのが、犯人探しや職員を責める風潮を作らないこと。
そうした雰囲気があると、事故報告もしにくくなり、モチベーション低下にも繋がります。
意に反して、隠蔽気質な職場になる可能性もあります。
職員にストレスを与えるだけですし、働きにくい環境になってしまうので気をつけましょう。
そういった職場は、個人的に見切りをつけても良いと思います。

何故起きたか、どう防ぐのかという点に注力しましょう。
まとめ

今回は「介護事故報告書の書き方」をお話ししました。
介護職として働く以上、介護事故と無縁でいる事は難しいです。
事故報告書の書き方だけでなく、事故時の対応や事故対策も日頃から考えていきましょう。
私もそうした経験を何度もしてきました。
ですが、必要以上に落ち込まなくても大丈夫です。
皆そういう失敗を繰り返し、成長していきます。
その気持ちを忘れず、次に活かせる様頑張りましょう。
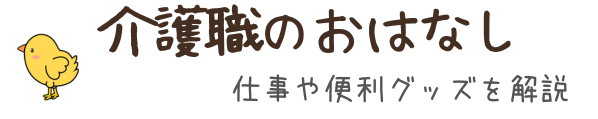
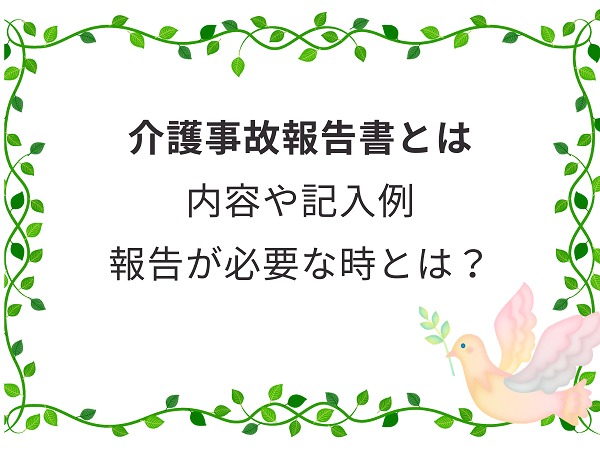


コメント