ユニット型の介護施設でよく作成される「24時間シート」。
これは利用者の生活スタイル、必要なサポート等を時間ごとにまとめた資料。
現場の介護士が、個人にあわせたケアを行うのに役立てています。
今回は「24時間シートの書き方」を中心に解説します。
書き方や目的、実際の記入例や介護施設の実態も交え、お話しします。
24時間シートとは

24時間シートは、介護を受ける利用者の情報を記載するツール。
個別(ユニット)ケアを重視するユニット型施設で、主に導入されます。
その名の通り、24時間の生活にそって「好み」「必要な介助」を記入します。
※ケアプラン等とも違う資料です
主に介護職員が記入し、利用者の理解を深める為に使用します。
24時間シートの記入内容

24時間シートは、時間毎にそって本人の意向や必要なサポートを記入します。
- 日課や習慣
- 意向や好み
- 自分で出来ること
- サポートが必要な事
食事やトイレなど、様々な生活場面において上記内容を書いていきます。
例えば、「7時に起床したい、声掛けをして着替えを渡せば後は自分でできる」等ですね。
これを各利用者、24時間ベースで作成します。
24時間シートの内容は、介護職員が記入します。
介護職員が日常を観察し、情報整理した資料という事ですね。
24時間シートの目的と活用方法

24時間シートは、主にユニット型施設で導入される資料です。
これら施設で行われるユニットケアは、一人ひとりを尊重した個別ケアを目標としてます。

完成したシートを見れば、その人の生活習慣や好み、必要な介助などが明確になります。
24時間シートは、個別ケアを実現する為の資料という事ですね。

さらに24時間シートには、職員の業務マニュアルとしての面もあります。
- 誰に何時に何をすべきか
- 介助を行う際の注意点
- 本人の嗜好
この様に、介護士が「いつに誰に何をすべきか」も記載されます。
利用者毎の注意点なども分かり、新入職員も利用者を理解しやすくなります。
ケア方法の統一、改善を行う際にも役立つ資料ですね。
利用者の心身も日々変化していくので、定期的な更新も大切です。
シートの必要性や活用方法

ユニットケアでは、必ずしも24時間シート通りに仕事をするワケではありません。
あくまで利用者を理解する為のツールであり、その時々で必要な対応は異なります。
ただ普段の生活習慣が分かっていれば、「いつもと違う」という変化にも気付く事ができます。
必要な人員や安全性など、業務の問題・改善点を考える際にも役立てる事も可能になります。
24時間シートの書き方・作り方

24時間シートは、介護職員が担当利用者について記入します。
日課や必要サポートまで、全て職員が利用者を観察し書いていきます。
データに直接書き込んだり、印刷して手書きしたりします。
24シートの書き方を実際に見てみましょう。
24時間シートの記入例
朝の起床時から朝食までの内容を、簡単に書いてみました。
24シートの記入例
| 24時間シート 〇〇様(担当△) 作成日:R2.2.17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 日課 | 意向や好み | 自分で出来る事 | サポートが必要な事 |
| 6:30 | 起床 整容 | 6:30には起こして欲しい 暖かいタオルで顔を拭きたい | 自分で顔を拭ける 職員に掴まれば立てる | 起床の声かけ 車イスへの移乗 タオルをお湯で濡らし渡す |
| 7:00 | トイレ | 朝食前にトイレに行きたい | 車イスの自走 コールボタンを押す 手すりにつかまれば立てる | ズボンの上げ下ろし 座る時に腰を支える |
| 7:20 | お茶を飲む | フロアで熱いお茶が飲みたい | 熱いお茶も安全に飲める 自分で席まで動ける | テーブルにお茶を提供する |
| 8:00 | 朝食 | スプーンとフォークを使う ご飯はお粥が良い 手持ちの梅干しを食べたい | 自分で食事が食べられる 梅干しの種を避けられる | 食事を配膳する 梅干しをお粥の上に乗せる |
こんな感じですね。
施設により異なる可能性はありますが、概ねこうした書式になります。
もし何を書くべきか分からない時は、ケース記録の書き方から勉強してみましょう。
日々の記録の確認にも活用でき、シート作成の役に立ちます。
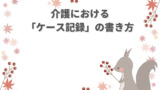
「全介助」「認知症」の方の記入例
全介助や認知症の人、寝たきりの状態でも、同じく24シートを作成します。
ただ自分出来る事が少なく、意思の疎通が難しい方も多いので、記入に困ると思います。
しかしよく注目すれば、「意向」や「出来る事」に記入できる内容もあります。

例えば、自分で出来る事。
食事にしても、「刻み食なら食べられる」「介助に合わせ口を開けられる」など色々あります。
「食べたくない時は口を開けない」等の拒否も、意思表示の1つですね。
本人の意向に関しては、職員がご本人に代わりその意思を汲み取る必要があります。
ショートステイの人にも必要?

私自身ショートへの関わりは少ないのですが…、
調べたところ、ショートステイ(短期入所)の方にも作成してる施設はあるみたいですね。
ショートステイは、繰り返し利用される方も多くいます。
利用しつつ入居を待っている方もいますので、長期的な目線で見ても役に立つと思います。
24時間シートはいらない?

さて24時間シートですが、有効利用できている施設は少ない印象です。
私も仕事で作成しましたが、ほぼ活用される事はありませんでした。
それにはこんな理由があるからだと思います。
- 24時間シートの使用場面が無い
- 更新・作成には手間がかかる
利用者様の変化もあるので、24シートは定期更新するのが理想ですが…
できている施設は、現状少ないのでは?
仕事だから書くという、業務負担を増やしてるだけの施設が多い気がします。
なぜ活用が難しいのか?

24シートが仕事に必須ではない、というのもあると思います。
ユニットケアでは、職員配置も少数でほぼ固定です。
日々の情報伝達や連携が出来ているユニットは、会議や申し送り等で十分情報共有が出来てます。
人手不足で業務も忙しいですし、更新作業も手間です。
利用者の状態変化も、別の方法で共有した方が楽という事でしょう。
個人的には、職員の能力や意識次第では必須でもないと思います。
日頃から利用者をよく観察し、個人に合わせたケアを作る流れが出来てれば、それで良いかと。
24時間シートの必要性を考えてみる

だからと言って、24シートが不要とも思ってません。
考察し文章化する事で見える生活情報もあるし、業務やケアの統一にも役立ちます。
ユニットケアを理解する為の研修、意識づけの意味で使用するのも良いと思います。

メリットを得るには、作成や更新で得た情報をどう活かすかですね。
利用者のケア方法や業務改善への活かし方が、鍵となるでしょう。
それが出来なかったり、別の方法で上手くやれてるなら、
無理して活用しなくても良いのかな、と思います。
活かすアテがないなら、省いて効率化を目指すのもアリだと思ってます。
24時間シートの書き方を理解しておく事は、大切ですよ。
職員都合で動かねば、仕事が回らない施設も多いのでは?
まとめ

今回は、24時間シートの目的や書き方を紹介しました。
職員によるケアのばらつきを防ぎ、皆で情報共有する事が出来ます。
24時間シートは、簡単に完成するものではありません。
利用者との関りや観察の積み重ねにより、作られていきます。
グループホームや特養など、ユニット型施設にお勤めの方は、記入機会もあると思いますよ。
また「事故報告書の書き方」も解説してますので、良かったらどうぞ。
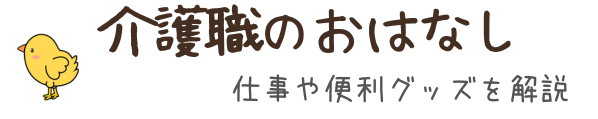

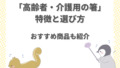

コメント