介護現場では、記録の作成も毎日の仕事の1つです。
介護記録は、チームケアの連携を高めるにあたり大切な資料となります。
しかし記録の書き方が分からず、負担になってる介護士も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、介護施設においての「介護記録の書き方」を解説します。
- ケア記録や文章
- 食事や水分量
- 排泄チェック
- 事故報告や日誌
こうした介護記録、チェック表などの書き方を総合解説。
「介護職員の記録業務」を詳しく紹介します。
介護記録とは

介護現場では、利用者様についての様々な記録を毎日つけています。
「どんな介助を行ったか」といった記録の事ですね。
これらを総称し、介護記録と呼びます。
介護記録の内容

介護職員つけてる介護記録には、下記の様なモノがあります。
- 食事、水分量
- 入浴、排泄、服薬の状況
- バイタル測定の結果
(血圧、体温、脈拍、血中酸素濃度) - 介助や支援、生活状況(ケース記録)
- 介護日誌
介護現場では、こうした記録を毎日つけています。
食事量や血圧などの数値、入浴や服薬のチェック。
文章での生活記録など、内容も書き方も様々です。

現在は、介護ソフトを使ったパソコン入力が主流ですね。
内容により、「紙面でのチェック表」と「PC入力」を使い分け記録しています。
近年はタブレットの導入も進んでおり、より円滑な記録業務が可能になりました。
介護記録の目的

介護施設は、介護保険法により「介護記録等の整備」が義務付けられています。
しかし決まり云々は別としても、介護記録は介護サービスを提供するにあたり大切な資料です。
介護施設では、下記の様な目的に活かされてます。
介護記録を書く目的
- 職員の情報共有や利用者様の体調管理
- ケアプランへの反映
- 身を守る法的な証拠
現場目線では、情報の共有。
事業所としては、適切なケアを行った法的証拠ですね。
例えば、ケース記録で「巡視や体調観察を行った証明を残す」。
排泄チェック表の内容をみて、「使用パットや介助の時間を変更する」という具合です。

また介護記録は、介護士だけが使う物ではありません。
看護師や栄養士、相談員等、様々な職種が連携して働く為にも役立てられます。
- 往診や受診での情報提供
- ケアプランへの反映、家族様への報告など
- 食事量を見て、食事形態や栄養食の検討をする
介護記録を確認すれば、こうした動きもスムーズになります。
介護記録の具体的な書き方

それでは、介護記録の基本的な書き方をご説明します。
- ケース記録
- 食事、水分
- 排泄
- 事故報告書、ヒヤリハット
- 日誌
上記項目ごとに、具体的な書き方・チェック方法を解説していきます。
これを見れば、何となく介護記録の事が理解できると思います。
ケース記録の書き方

ケース記録とは、サービス内容や生活状況の文章記録です。
※ケア記録とも呼ばれます。
食事量や入浴可否などの数値やチェックとは別の、具体的な生活記録ですね。
- 不調の訴えがあり、本日の入浴は中止とした
- 声掛けにて、トイレ誘導を実施
- 巡視、良眠中
こうした文章記録の事です。
ケース記録は、主に下記の様な時に記入します。
- 介助・支援を行った時
- 体調不良や事故があった時
- ご家族とのやりとり
- いつもと違う特変、気づきがあった時
ケース記録があれば、数字やチェックでは見えない具体的な情報が分かります。
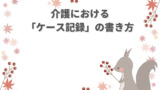
「なぜ食事量が少ないか」「入浴の様子はどうだったか?」。
「微熱があるが、体調は?」など、情報共有するうえで特に重要な役割を果たす記録ですね。
食事・水分量の書き方

食事・水分量は、基本的に下記時間の内容を記録します。
- 食事(朝・昼・夕食+おやつ)
- 水分(3食+10時+15時)
※夜間分を記録する事もある
「朝昼夕の3食」と「10時・15時(おやつ含む)」の内容ですね。
上記以外の内容を記録する事もありますが、施設生活の特性上コレが基本となります。
これらの記録には、介護独特の表現が使われるので注意です。
食事量の表し方

介護施設での食事量の書き方は、主に「全体の何割を食べたか?」で表現します。
完食であれば「10」、一口も食べなければ「0」です。
※完食を5とする職場もある
※味噌汁やスープを「汁物」としてカウントする事も
例えば、【主食10・副食5】といった形。
これは主食は完食、おかずは半分食べたという意味になります。
水分量の書き方

水分の場合は、「〇ml」など飲んだ量をその都度書きます。
3食の他、10時と15時にも水分提供を行います。
なので、基本的には1日5回分の記入を行う事になります。
多くの介護施設では、1,000mlや800mlなど「1日の目標摂取量」も決まってます。
夜勤者が1日のトータル水分量を計算し、不足者は朝礼等で報告する事が多いですね。
副食とする事が多いですが、職場ルールを確認しておきましょう。
排泄記録の書き方

排泄量は、「排尿」と「排便」に分け記録します。
主に下記について、時間・利用者毎に記録します。
- 「尿量」と「便量」
- 「トイレ」か「パット内(失禁)」か
具体的な書き方は職場で異なりますが、「尿と便の区別は記号」。
「トイレか失禁かは色」で区別し、記録するのがポピュラーですね。
例えば、「トイレは黒」で「失禁は赤」。
「尿は〇」で「便は△」といった形ですね。
尿・便量の書き方

排便の際は、「軟・硬」といった形状。
「小・普・多」といった量も記録します。
便の形状については、ブリストルスケールを採用してる職場もあります。
該当数字を記入する事で、排泄表で分かりやすく記録する事ができます。
※参考「排泄ケアナビ(ブリストルスケールによる便の性状分類)」
さらには「何日排便がないか」もカウントし、これを元に看護師と下剤調整も行います。
このカウントにはKOT-〇日といった表現をよく使います。
KOT-3であれば、3日排便がない事を意味します。
.jpg)
尿量については、バルーン使用の方の尿破棄量。
看取りの方のパット内排尿の記録等が主です。
その他の場合だと、あまり細かく量を記録する事は少なめ。
「事故報告書」と「ヒヤリハット」

下記の様に、転倒やケガがあった際は事故報告書を作成します。
- 転倒や服薬ミスが発覚した
- 原因不明だが、ケガがあった
- 実害はなかったが、観察を要する
介助ミスだけでなく、利用者様が自分で動いた時も対象です。
「転んだけど何もケガはない」という様な時も、報告書が必要です。
事故報告書の書式は施設で異なりますが、下記内容が定番です。
- 事故の経緯
- 外傷等の程度や対応
- 原因と対策
- 家族連絡の内容
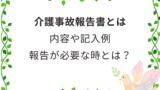

また事故が起こりそうだったが、未然に防げた時はヒヤリハットを作成します。
ヒヤリハットの場合、より簡易的な内容となるのが一般的。
主に「経緯」と「原因・対策」について記入します。
介護日誌の書き方

毎日の業務日誌も、職場により書き方が大きく異なります。
さらには、入居施設や通所、訪問など、事業所種類でも大きく変わってきます。
下記は、「入居介護施設の業務日誌例」です。
| 日付 | R4/11/3 |
|---|---|
| 出勤職員 | 〇〇、△△、×× |
| 予定 | □様 〇病院受診(9:30発) |
| 日勤帯 申し送り事項 |
|
| 夜間帯 申し送り事項 |
|
簡潔ですが、雰囲気はこんな感じですね。
介護施設の場合、日勤帯と夜勤帯で分ける事が多め。
業務日誌は介護ソフト内に入ってる事もあり、そちらで記録する事もよくあります。
介護記録をより良く効率的に残すには?

ここまで述べたように、介護記録はより良いケアに必須となる物です。
一方で、記録業務が介護職員の負担になってる現実もあります。
介護記録をより良く、効率的に書く事には下記能力も必要になってきます。
- 必要情報を拾う観察力
- 効率よく分かりやすく書く文章作成力
- 介護ソフトを使いこなす

難しいかもですが、意外と経験や慣れで何とかなります。
同じ利用者を毎日見ていれば、「コレはこの人にとって普通の事」。
「今日はいつもと違う」など、自然と変化にも気付けるようになります。
まずは他職員の記録を読む事から始めると、参考になる事が多いですよ。
下記の様な書籍でも、使える言葉や表現が学べるので活用して下さい。

また「介護ソフト」や「タブレット」など、記録の作業環境も大切です。
円滑な作業環境が整ってる環境、そのツールを上手く使いこなす事も効率に関わります。
こちらも触って慣れる部分が多いので、恐れずに色々触ってみて下さい。
介護記録への苦手意識がなくなれば、働きやすさも向上します。
この機会にちょっと意識してみてはいかがでしょうか?
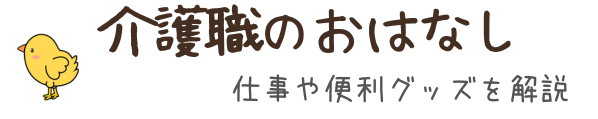
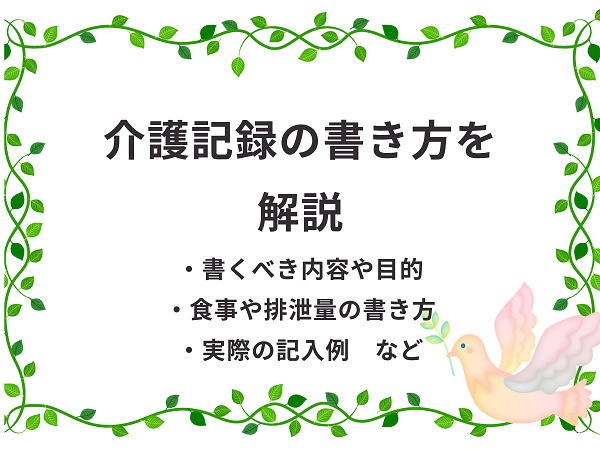


コメント