コロナ禍以降、介護施設の面会方法にも変化がありました。
以前は自由に出入りが出来ていましたが、現在は何かしらの制限が増えています。
そのぶん面会の方法にも、オンライン面会等のバリエーションが増えました。
今回は、「近年における介護施設の面会方法」というテーマで記事を作成しました。
- 今も介護施設では対面面会ができない?
- 現在可能な面会方法と注意点
- 「物品の差し入れ」や「その他連絡手段」
上記情報について、利用者様ご家族向けにご説明します。
私自身も利用者家族であり、施設で働く介護職員でもあります。
家族や職員目線での情報も併せ、お伝えしていきます。
コロナ禍で介護施設の面会ができなくなった?

コロナの影響により、介護施設の面会方法はそれ以前と大きく変化しました。
一時は緊急の場合を除き中止となったのも、記憶に新しいですね。
コロナの影響が落ち着きつつある現在でも、施設側の感染症対策への意識は高く保たれています。
その為、コロナ前の様な自由な出入りが難しい施設もまだあります。
あるいはline等のビデオ通話によるオンライン面会が多い印象を受けます。
コロナにおける介護施設での面会現状

冒頭の通り、介護施設では自由な面会ができない介護施設が多いです。
対面面会の状況については、下記いずれかに該当するケースが多数ですね。
- 対面面会は行ってない
- 居室や生活スペースには入れず、面会は決まった場所で行う
- 面会の時間や回数に制限がある

ピーク時に比べ、面会自体は行われている介護施設が増えてます。
ただ面会可能でも、コロナ以前のような自由さは無くなってます。
ご家族様の入れる場所も制限され、居室や共有フロア等の生活スペースには入れない事が大半。
見ている感じ、共有スペースには自由に入れず、「居室のみで面会を行う」。
「30分程度の時間制限の時間制限がある」という形の介護施設が多く見受けられます。
現在でも、厳しい時はそうした施設もあるかもしれません。
看取りケア中は例外もある

例外として、「看取り介護中」の利用者様は居室での制限少なく面会が出来る事があります。
施設側が必要な段階だと判断すれば、居室での面会許可が可能です。
そうした事態も考慮し、対象者の居室は施設の入り口近くに置かれる事が多くなります。
面会の方法と可否は「管理者」が判断する

面会の可否は各介護施設で異なり、その判断は管理者に任されています。
下記は「厚生労働省による施設向け通知」から一部抜粋・要約したものです。
- 「地域の発生状況」や「都道府県等の方針」「入所者や面会者の体調・ワクチン接種歴等」を考慮し、管理者が面会の実施方法を判断
- 入所者及び面会者がワクチン接種済み
または検査陰性を確認できた場合は、対面での面会の実施を検討する事 - 対面での面会を制限せざるを得ない場合、オンライン面会も検討する事
※参考「厚生労働省(高齢者施設における面会の実施に関する取組について)」より
地域の感染者数や面会者等の体調、ワクチン接種歴などを考慮し、施設管理者が判断します。
その際は、対面面会の可否だけでなく、時間や回数、場所なども決められる事となります。

私も施設で介護職として働き、介護施設に入居してる家族もいます。
そしてそのどちらでも、対面面会の実現はできてません。
感染者数が少なくなった時に面会再開された時もありましたが、その後は中止となりました。
高齢者という事もあり、施設側としても慎重にならざるを得ない事情もあります。
もしこれから老人ホームを選ぶのであれば、面会の実施状況を事前によく確認しましょう。
近年の介護施設における面会方法

ここからは、コロナ禍における「介護施設の具体的な面会方法」を説明します。
現状、面会方法は大きく下記2種類。
- 予約制の対面面会
- オンライン面会
先の通り、コロナピーク時はオンライン面会が主流でしたが…
現在は予約制の対面面会が多くなっています。
いずれにしても、面会を申し込むには電話連絡による予約が一般的です。
「対面面会」の方法と注意点

介護施設で「対面面会」を希望する場合、事前の予約が必要です。
面会状況の確認も兼ね、電話連絡してみると良いでしょう。
日中の9~18時位であれば、事務所の職員と連絡がつくかと思います。
面会可能な曜日を指定してる施設もある為、事前に確認しておきましょう。

また濃厚接触者は不可など、面会者の状況にも確認・制限があります。
先の厚生労働省の資料を参考にしつつ、ご説明します。
「過去2週間以内に感染の疑いがある症状がなく、そうした人との接触がない事」。
加え「入国後の観察期間を必要とされる国・地域への渡航歴がないこと」等を求められます。
面会時の注意点
.jpg)
対面面会の際は、ご家族様は下記点にご注意下さい。
- 飲食は可能な限り控え、大声での会話は控えること
- 施設内のトイレの使用を必要最小限とする
- 面会者は人数を必要最小限とすること
- 面会時間を通じてマスク着用、面会前後は手指消毒をする
- 手指や飛沫等が、入居者に触れないように配慮する
上記内容は、日常生活でも注意されてる方は多いと思います。

介護施設で特に注意すべき点は、「飲食」や「面会者の人数」ですね。
親族など、人数が多くなる時には後述のオンライン面会を検討しましょう。
飲食物をはじめ、物品の差し入れは事務所へ預けるようにして下さい。
多くの場合、事務所で受け取りをしてくれるので確認してみて下さい。
トイレも事前に済ませておくと良いですね。
「オンライン面会」の方法

もう1つの面会方法は、オンライン面会。
オンライン面会とは、Line等のビデオ通話による面会方法ですね。
ピーク時ほどではないにせよ、こちらも未だ使用される方法です。
実施状況は施設で異なりますが、電話などで予約申し込みする事で行えます。
- 施設へ連絡し、オンライン面会の予約をする
(お互いに連絡先の交換・登録をする) - 当日は時間になると、施設側からLINEによるビデオ通話の着信がある
(あるいは、コチラから指定の連絡先にビデオ通話をかける) - 時間が来たら、挨拶をして終了
高齢者に配慮し、施設側は職員付き添いで画面の大きいタブレットを使用。
ご家族にはスマホ等で対応してもらう形です。
午前中は入浴がある関係で、午後13~15時に受け付けてる事が多いかと。

職員付き添いする事も多く、ご家族だけの時間が作りにくい事。
通信環境の問題でスムーズに進まない事もある等、欠点はあるも安心して行える面会方法です。
遠方の方にもお話できるチャンスも生まれるので、有効に活用しましょう。
対面面会が無理な時は、オンライン面会ができないか相談してみて下さい。
スマホ等の操作やネット環境の用意が難しい方は、相談すると良いかもしれません。
その他「家族が施設入居者と話す方法」

ご家族としては、面会以外で入居者様と話せる機会は下記でしょうか。
- 病院受診の付き添い
- 電話連絡
介護施設では、協力機関以外の病院付き添いはご家族にお願いする事が多いです。
ただ家族や受診先を通し、感染するリスクも高く、実際そうした方も多くいます。
加え、外出中は受診先以外への移動は制限され、帰施後は数日居室で過ごして頂く事もあります。
不必要な受診は控え、リスクを最小限に抑えた方が得策です。
「携帯電話」を持つ利用者様も増えている

もう1つは、ご利用者様にスマホ(携帯電話)を持ってもらう方法ですね。
「有料老人ホーム」や「サ高住」など、民間企業の介護施設の多くは携帯の持ち込みが可能です。
有料老人ホーム等の自立度の高い利用者様は、携帯電話を持ってる方がかなり多いです。
もし問題なく使えるのであれば、貴重な連絡手段として重宝します。

認知症の症状が少なく、自立度が高めの方にオススメしたい方法です。
さいごに

今回は「介護施設の面会方法」についてお伝えしました。
ご家族様としては、フロアや居室に入れる機会が減り、生活状況の把握が難しい現状です。
連絡の際には、衣服や物品などの必要物をご本人や職員に積極的に確認しましょう。

また外出やイベントなど、利用者様の楽しみも少なくなってしまいましたね。
雑誌や脳トレ本、テレビなどの娯楽用品の需要は、利用者様の間でさらに高まってます。
この機会にご本人に合いそうな娯楽をご家族から提供してみてはいかがでしょうか?
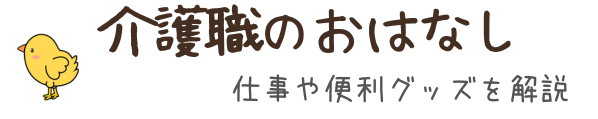

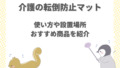

コメント