職員不足もあり、介護現場では「休憩時間がない」という声がよくあります。
皆さんの職場ではどうでしょうか?
- 忙しくて休憩がとれない
- 休憩室がなく、ゆっくり休みにくい
- 休憩中に食事介助等をさせられる
これらは介護士によくある休憩に関する悩み。
私も同様で、自主的に休憩を削る事もあれば、休憩中の労働を強要された経験もあります。
今回はそのような問題に向き合うべく、「介護士の休憩」を語ります。
注意すべき職場、休憩確保の為に出来る事などをお話ししていきます。
介護職が休憩時間を取れない「原因と現状」

介護の仕事は忙しく、ゆっくり休憩を取りにくい場面もよくあります。
休憩が取れない場面としては、下記の様な理由があります。
- 仕事が終わらず、自主的に休憩を取らない
- 休憩中の見守り職員がいない
- 休憩中に労働を強要される
大抵の職場では、「休憩時間の確保が難しい」のが理由になると思います。
しかしそれが当たり前になり、労働環境への意識が低下した職場には要注意です。
人手不足で仕事が終わらない

介護職が休憩を取れない原因の多くは、人手不足です。
業務が忙しく、つい休憩を削って働いてしまった経験も多いと思います。
残業をするくらいなら、休憩時間を使ってカバーしようと考える方もよくいます。
下記は、介護職が忙しくなる要因となる業務。
- 入浴介助
- 食事介助
- 記録業務
休憩は、食事介助などの時間と被る事が多いです。
介助人数が多く、休憩時間を削り手伝ってしまった経験も多い事でしょう。
他職員が大変そうだ、と自主的に休憩を削ってしまう事もよくありますね。
忙しさによる「労働意識の低下」
こうした介護の忙しさは、労働意識の低下も招きます。
最初は善意で行っていた内容も、行き過ぎると当たり前になってしまいます。
- 休憩はしっかり取る
- 定時で勤務終了する

人員の確保や業務改善が進まず、こうした普通の事が出来てない職場も多くあります。
悪質なところになると、休憩中の労働を強要するところもあります。
そうでなくとも、その現状解決に何も動けてない職場が大半でしょう。
そして職員間でも、「休憩なし」や「残業」が当たり前の風潮になりつつあります。
介護施設の夜勤では「休憩なし」の職場も

介護で、特に休憩時間が取れないのは夜間帯です。
多くの介護施設では、夜間は数人の介護士のみが配置されます。
ユニット型施設の夜勤におけるワンオペ体制です。

介護施設では、24時間体制で介護サービスを提供します。
それなのに1人体制で働かなくてはなりません。
休憩中でも、利用者に何かあれば対応する必要があります。
ワンオペ夜勤では、休憩は「暇なときに自主的に」取る必要があります。
忙しければ休むことは出来ず、休憩時間が保証されていないんですね。
要注意「介護士に休憩を取らせない職場」も

介護士として最も警戒すべきなのが、休憩を取らせない職場です。
何だか休みにくいではなく、「そもそも休憩が無い」「休むと怒られる」という環境。
ここまで述べた様な環境が行き過ぎると、こうした風潮が蔓延するようになります。
介護業界には、こんな思考に陥ってる職員・管理者は一定数います。
他にも「休憩室が無い」、「利用者と一緒に食事」などといった職場も存在します。
休憩が取りにくいだけでなく、休憩中の労働を強要する職場もあるので要注意です。
休憩中に「食事介助等の労働」を強要される

「利用者と一緒に食事を摂る事」をルール化し、それを休憩時間と見なす職場もあります。
例えば、昔私が勤めてたグループホームでは、利用者の食事中が休憩時間でした。
一緒に食事を摂る事を強要され、現場を離れる事も出来ず、休憩室もありませんでした。
内部で働いていると、意外に違和感に気づきにくいのが恐いですね。
会社全体で「労働規則への意識欠如」が進んでると、個人での改善は非常に困難。
職場にこれといった魅力が無いのであれば、早々に離れた方が賢明です。
休憩室が無い職場には注意

休憩時間が取れない介護現場に共通する特徴として、「休憩室が無い事」があります。
休憩室が無い職場では、利用者の生活フロアの隅等で休憩を取る事になります。
現場のヘルプも頼まれやすく、仕事から離れる時間を作りにくい環境。
休憩室がない職場は小規模施設に多い印象ですが、特養とかでも普通にあるので注意。
休憩時間を守ってるのに注意される

行き過ぎた職場では、「休憩をきっちり一時間とっただけ」で注意される事も…。
休憩返上での労働が当たり前になってる施設ですね。
こうした職場では、勤務開始前の労働も強要されがち。
自主的に休憩を削る事があっても、それを他人に強要するのは絶対にNG。
リーダーや管理者等、立場のある人間がそれを注意せず、率先して行う事もあります。
ブラック施設の特徴の1つですね。
休憩時間と労働基準法

働くうえで知っておいて欲しいのが、労働者は休憩を取る権利があるという事。
労働基準法では、下記の様に定めています。
また「休憩時間は一斉に与えなければならず、自由に利用させなければならない」ともあります。

使用者は休憩を与える義務があり、労働者は休憩を取る権利があります。
間違っても「休憩をとらせず、労働を強要」する行為は、認められるモノではありません。
間違った職場ルールに流されないよう、覚えておきましょう。
介護士が休憩を取る為の「働き方」「転職アドバイス」

介護士が休憩時間を守り、健全に働くにはどうすれば良いか。
介護現場での労働問題は人手不足を原因としたモノが多く、休憩の確保も例外ではありません。
しかし、そんな中でも個人で出来る取り組みもあります。
休憩が出来る雰囲気作り

一職員として出来る事に「休憩しやすい雰囲気作り」があります。
他職員の休憩時間が少ない事に気づいたら、「互いに声を掛け合う」などですね。
些細な事ですが、細かな気遣いの積み重ねが働きやすい職場が作ります。
もし自主的に休憩を取らない習慣があるなら、この機会に見直して下さい。
1人で忙しそうにいていては、他職員も休憩をとりにくくなります。
自分の気遣いも「楽しやがって」という気持ちに変わらないとも言い切れません。
悪気なく同調圧力を生んでしまう事もあるので気を付けましょう。
業務内容や効率を改善する

限られた職員数の中、気兼ねなく休憩できる環境を作るには「時間の確保」も必要です。
介護の仕事は、時間毎に決まったスケジュールが割り当てられます。
何かが遅れれば、その後の業務ももたついてしまいます。
利用者様を第一としたケアが前提ですが、時間を見て働く事も大切です。
業務内容や人員配置、自身の効率など、出来る事から見直してみましょう。
「休憩が取れない職場」は辞めて良い

休憩を正しく取らせない、休憩中の労働を強要する職場は問題外。
また、休憩を削って働くのが当たり前になってる職場も危ないです。
休憩を削ってまで働く事はありません。
他に働き続ける理由が無いなら、辞めてしまってOKです。
ブラック気質が全体に染みついた職場は、残念ながら改善の見込みが薄いです。
「転職する」「そういった職場を選ばない」等、こちらから回避する方が賢明です。
ブラック気質な職場を避けるには?

働きにくい職場を避ける為にも、転職活動は慎重に行いましょう。
休憩時間に着目すると、下記の内容を確認すると良いでしょう。
休憩が取りやすい職場を探すには?
- 休憩室の有無を確認
- ユニット型(1人夜勤)施設等を避ける
- 職員の定着率

面接等での職場見学時に、「休憩室の有無」「職員体制」等を確認しましょう。
自分からも、「職員の休憩場所はどちらですか?」と聞いてしまってOKです。
1人体制の施設は避け、仮眠時間をしっかり設けてる職場を選ぶ事を推奨します。
自分も休憩が無いのがキツくて、過去の職場をいくつか退職しました。
今の職場は昼間も休憩が取れるし、夜勤中も2時間の仮眠があります。
転職サービスを活用する

介護士の働きやすさは、職場の職員数次第といっても過言ではないです。
給料や休日など、「総合的にみて魅力ある職場を選ぶ事」が働きやすさに繋がります。
少しでも健全な職場を選ぶには、転職支援サービスの活用も有効。
アドバイザーに相談すれば、職場見学の調整や内部情報の提供なども行ってくれます。
退職トラブルにも要注意!

モラルの低い職場、職員不足が深刻な職場では、退職時に引き留めが発生する事もあります。
「辞めさせてもらえない」など、悪質な管理者もいるので警戒しましょう。
⇒介護職に多い退職引き止め!仕事を辞められない時の断り方とは?
引き留め時には、小手先の理由付けより、明確な意思表示が大切です。
個人での解決が難しい時は、「退職代行」など第3者の力も頼ってください。
まとめ

今回は「介護士の休憩時間」のお話でした。
同じ「休憩が取れない職場」でも、その良し悪しには大きな差があります。
特に休憩中の介助を強要するような職場には、注意が必要です。
悪質な会社ルールを敷く現場もあれば、業務を優先する意識が歪ませた職員もいます。
この様な職場で無理しても、結局は自分が潰れるだけです。
自分を大切に出来なければ、利用者様や他職員にも優しく出来なくなります。
せめて介護職員同士は仲間となり、支えあえる環境を作っていきましょう。
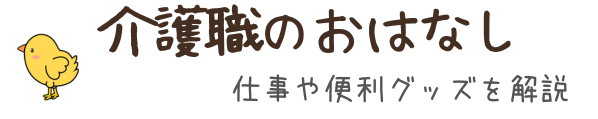
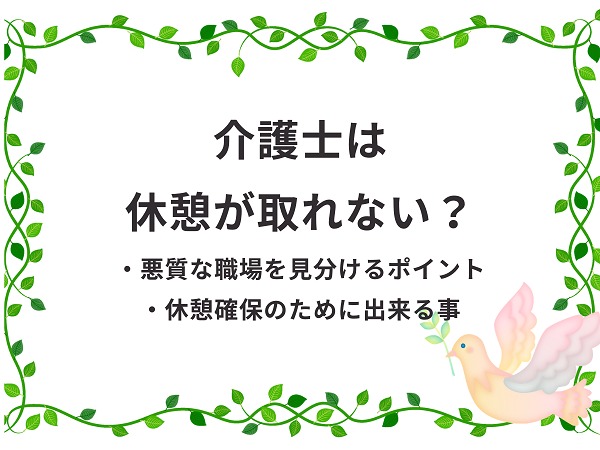


コメント