介護施設のお風呂には、「リフト浴」「機械浴」といった種類があります。
介護でよく使う入浴設備ですが、一般の方は聞き慣れないかと思います。
家庭のお風呂と同様な「一般浴」はもちろん、介護施設には色んな入浴設備があります。
施設を利用している方は、足腰の元気な方ばかりではありません。
身体に不自由がある人でも、安全に入浴が楽しめるよう色んな入浴方法が用意されています。
リフト浴や機械浴、パンジー浴など、各種入浴方法を紹介します。
介護施設の「お風呂の種類と使い方」

介護施設のお風呂は、下記の様な種類があります。
- 一般浴(個浴)
- リフト浴
- チェアー浴、ソファー浴
- ストレッチャー浴
- シャワー浴、足浴
これらを利用者の状態に応じ、使い分けます。
まずは、入浴方法の違いや手順を見ていきましょう。
一般浴(個浴)

「一般浴(個浴)」とは、家庭のお風呂と同じ物です。
一般家庭にもある「普通の浴槽」での入浴ですね。
自力歩行(独歩)が可能で、立位や歩行が安定した方に利用されます。

元気な方向けの入浴方法だけに、下記の様に危険場面も多くあります。
- 浴槽を跨ぐ
- 浴室を歩く
その為、介護施設では「滑り止めマット」や「浴槽手すり」を使い事故に備えます。
また一般浴を利用される方は、様々な方がいます。
- 自立しており、介助を必要としない
- 洗身、洗髪など介助を要し、手すりがあれば浴槽を跨げる
介護職員としても、相手に合わせた介助・対応が必要ですね。
いずれにしても基本的に職員は側で付き添い、見守りします。
リフト浴

リフト浴とは、浴槽に入浴用のリフト付き椅子があるお風呂です。
椅子に座ったまま入浴できるので、浴槽を跨げない方も安全に入浴出来ます。
「歩行は難しいけど、座位は保てる」という方に適してます。
パンジー浴

パンジー浴とは、浴槽に回転式のリフトイスが付いてるタイプです。
リフト椅子に座った後、椅子を回転させつつ浴槽をまたぎ浴槽内へ。
その後は、リフト椅子をボタンで昇降させ入浴できる仕組みです。
- シャワーチェアで、洗髪・洗身
- 浴槽のイスに移乗、安全ベルトを締める
- イスを浴槽へ回転スライドしつつ、利用者様に浴槽をまたいでもらう
- 昇降ボタンで椅子を下げ、入浴
介護用品でいうと、回転式のバスボードにリフトが付いた様なイメージです。
座ったまま、椅子を回転させて浴槽跨ぎができるのが特徴ですね。
浴槽高さも低く設定できます。
出入り時は浴槽の高さを下げ、入浴中は高さを上げ蓋をします。
これにより低い高さでスライドし、入浴中は肩までお湯につかる事が可能です。
ストレッチャー浴と同様、掴まれる手すりや安全ベルトもあります。
ホーミー浴

ホーミー浴とは、浴槽をまたぐ必要のないリフト浴です。
先述のパンジー浴より、椅子リフトがより高く上がるのが特徴。
これにより、リフト操作のみで浴槽またぎを行う事が出来ます。
またフットレストも付いており、移動中は「長座位の姿勢」を保持できます。

長座位とはこの様な姿勢です。
足をのばしたまま、一度高くリフトを上げ、イスごと浴槽を跨ぎます。
スライド後は、そのまま高さを下げ、浴槽につかる事が出来ます。

浴槽をまたがなくて良いので便利ですが、怖いと感じる利用者さんも結構います。
椅子が高く上がるので、介護側も昇降中は特に安全に気を配る必要があります。
チェアー浴(チェアーインバス)
チェアー浴も、椅子に座ったまま入れるお風呂です。
リフト浴と違い、開閉式の浴槽に専用の椅子を正面等から差し込めるのが特徴ですね。
車椅子のまま浴槽に入り、その後にお風呂のフタを閉める感じですね。
椅子を差し込んで浴槽を閉め、お湯を張ります。

雰囲気としては、この様な大型シャワーチェアを浴槽に差し込む感じですね。
入浴用の椅子は、そのままシャワーチェアとして使えます。
イスからイスへの移乗介助が少なく、介助者・利用者共に負担が少なく済みます。
リフト昇降もないので、危険が少なく安心感のある入浴方法ですね。
ソファー浴
ソファー浴とは、浴槽の片面が開閉式の扉になっている入浴設備の事です。
普通の浴槽を底上げしたような形が特徴。
浴槽が深くならない為、ソファーに腰掛ける感覚で入浴できます。

普通のお風呂での再現画像になりますが、赤線部が上下に開閉するイメージです。
お風呂に入る際は、浴槽の扉を下げて浴槽内へ。
その後は扉を上げ、お湯を入れる事で入浴できます。
椅子から椅子へ移る感覚で、入浴が行えます。
ストレッチャー浴(機械浴)
機械浴(ストレッチャー浴)とは、寝たまま入れるお風呂の事です。
寝台浴や特浴とも呼ばれますね。

ストレッチャーとは、車輪付きの簡易ベッドの様な物です。
入浴時にはこちらを使用し、洗髪・洗身を行います。
ストレッチャー浴の入浴手順
- 浴槽にお湯を張っておく
- 利用者様をストレッチャー上に移乗(脱衣)
- 浴室で洗身・洗髪
- 浴槽の横からストレッチャーを差し込み、浴槽を閉めます。
- 昇降ボタンを押し、入浴
ストレッチャーは「高さ調整機能」があります。
入浴時は高さを上げ浴槽へスライド、浴槽内で高さを下げお湯につかります。
※リフト浴に似てますが、寝たまま行える点が異なります。
入浴時には安全ベルトを装着し、すべり落ちないよう掴める手すりも付いています。
浴槽を閉めてからお湯張りを始めるタイプ等があります。

要介護者の中には、座った姿勢が保持できない方も多くいます。
座位が保持できないと、椅子からの転落や浴槽内でずってしまい溺れる危険があります。
ストレッチャー浴は、そうした方の為の入浴方法ですね。
機械浴やリフト浴の違い
ここで機械浴について補足します。
機械浴とは、その名の通り下記の様な機械を使った入浴方法です。
- ストレッチャー浴
- リフト浴
- チェアー浴

介護施設により、各入浴設備の有無は異なります。
それもあって、職場や施設で入浴設備の表現方法は異なる面もある様子。
先述の通り、現場では主にストレッチャー浴を指す事が多めです。
ストレッチャーは特浴とも言われますし、色々な呼ばれ方がされますね。
【番外編】足浴・シャワー浴
入浴とは別に、皮膚の清潔や血行促進など、足の健康状態次第で足浴も行います。

足浴用のバケツにお湯を張り、足を温めるという方法ですね。
必要に応じ、足の状態観察や薬の塗布などの処置も行います。
加えて、ご本人の体調や希望次第では「シャワー浴」という形をとる事もあります。
本来であれば、浴槽につかり温まってもらいたいのですが…、
体調が悪い場合時などは、ご本人の負担も考慮し、シャワーのみで済ます場合もあります。
入浴方法は誰がどう決める?
入浴方法は、基本的に現場の介護士・看護師が中心となって決めます。
高齢者の身体状況は変化が大きいので、その時々でその方のADL(日常生活動作)に合わせた入浴方法を選択していきます。

入浴設備の関係もあり、入浴方法の決定は下記の様な事が出来るかがポイントです。
- 歩行が安定しているか(浴槽が跨げるか)
- 座位が保てるか
歩行が安定し、浴槽を跨げれば一般浴。
座位が保てればリフト浴、難しければストレッチャー浴、というのが一般的です。
入浴方法は「介護職」「看護職」が中心に決める
入浴介助は、基本的に介護士の仕事です。
「個浴じゃ危険」「座位が保てなくなってきた」などの”気づき”も、介護士からあがる事が多め。
また入浴時には、看護師による観察や処置も行います。

基本的には、現場で直接介助をする機会の多い介護職が中心ですね。
実際には、介護職員のリーダーが判断する機会が多め。
看護職員に提案し、アドバイスを受けるという事もよくあります。
入浴介助は危険が多い
介護では、入浴は特に事故の危険が多い場面です。
- 転倒や転落
- 機械による挟み込み
- 脱水や温度差による体調悪化
介護職員としては、慎重かつ安全に介助を行う必要があります。
入浴方法だけでなく、その人の体調を見て慎重に入浴判断をしなくてはなりません。

またお風呂は、しっかり身体の観察ができる貴重な機会です。
皮膚状態などの異変に気付けるよう、観察力も必要になります。
非常に重要かつ、難しい仕事ですね。
この機会に、入浴介助について学んでみるのも良いと思いますよ。
入浴設備でみる介護施設選び

最後に、入浴設備に注目した介護施設選びを解説します。
ここまで紹介してきた入浴設備は、全ての介護施設に備わっている訳ではありません。
元気な方を利用対象としている施設では、あまり充実してない事もあり得るでしょう。
入浴方法が充実してる介護施設は?
特に機械浴は、主に介護度が高い人向けの施設で充実してます。

例えば「特養」や「老健」、「介護付き有料」などですね。
一般的な個浴も備えてますので、豊富な入浴方法が用意されてます。
逆にグループホームやサ高住など、自立度が高い人向けの施設では比較的少なめ。
リフトやチェアーなどはあっても、特浴はない施設もよくあります。

介護施設の見学時には、入浴設備にも注目してみると良いでしょう。
介護施設も、種類により想定してる利用者が異なります。
入居条件にもその特徴が色濃く出てますので、注目してみると良いですね。
「入浴の自由度が高い」施設もある
より自立している方向けの施設では、入浴設備は充実してない傾向です。
介護というより、住宅の提供を主とした施設ですね。
例えば、シニア向け分譲マンションや住宅型と呼ばれるような施設です。

ただ自立度の高い人の施設では、その代わり生活の自由度が比較的高め。
一部の施設では、毎日入浴出来たり、居室に浴室が付いてる事もあります。
中には、温泉設備をアピールする施設も見られます。
安全に楽しく入浴できる施設を選ぼう

施設で入浴設備が異なる様に、本人状態により適した入浴方法は異なります。
いずれにしても、安全に楽しく入浴できる方法ができる施設選びをしたいものですね。
介護職員としても、利用者に適した入浴設備があった方が安心です。
施設によるので、見学の際はよくチェックしてみましょう。
介護施設は、種類により提供できるサービスも異なります。
入浴設備だけでなく、その人に合った暮らしが出来る施設選びを心がけましょう。
さいごに
代表的な入浴設備を紹介したつもりですが…、
設備開発も進んでいる事もあり、現在も新しい機能が色々と生み出されています。
新しい介護施設では、そんな入浴設備を見る機会もあるかもしれません。
介護施設を知る1つの知識としてお役立て頂ければ幸いです。

その他にも、「入浴介助」や「介護施設」に関する記事を用意してます。
良かったら、ご覧になってみて下さいね。
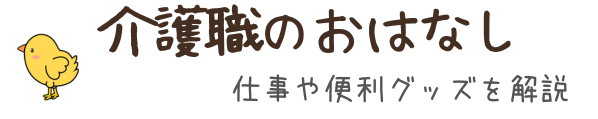
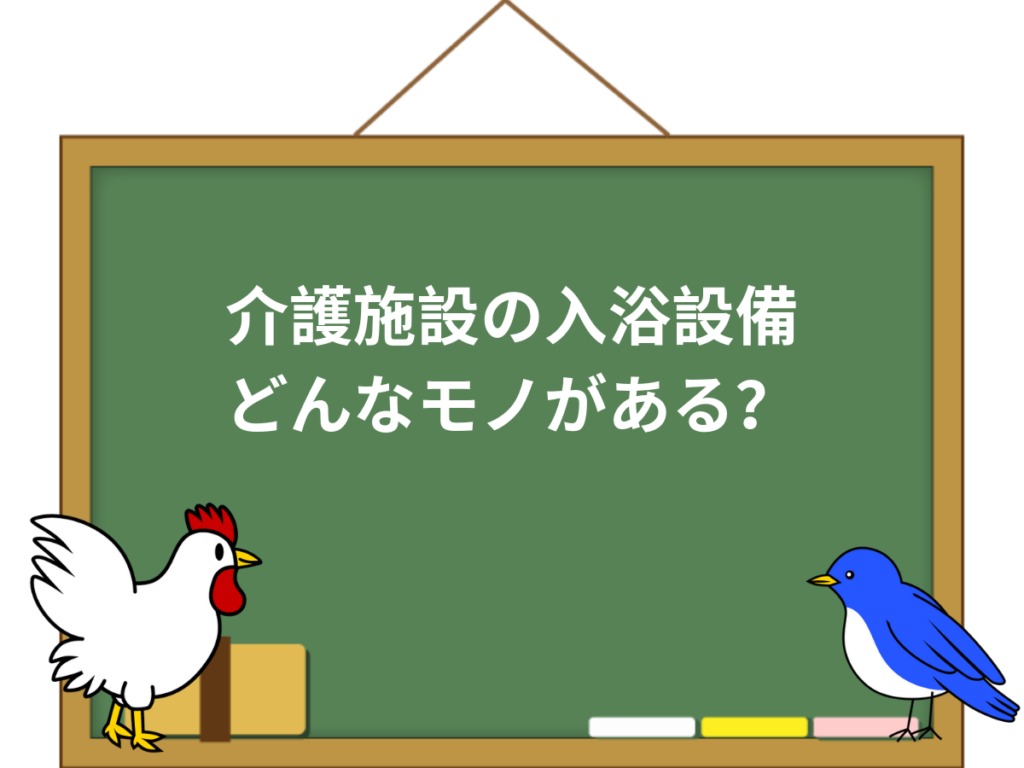

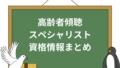
コメント