介護では、たびたび「見守り」という言葉が使用されます。
見守りとは、相手の安全状態について注意を払う事を意味します。
大まかな意味や目的は同じものの、「仕事内容」や「家電の機能」など…、
使用場面により細かなニュアンスが異なる事も多々あります。
今回は「介護における見守り」について、業務内容を中心に総合解説します。
介護での見守りの内容を解説
- 介護方法や業務など仕事での注意点
- 見守りサービスや活動
- 家電や介護機器の機能(見守りシステム)
仕事での見守り業務を中心に、上記についてそれぞれご紹介します。
目次から知りたい内容をご覧ください。
介護施設における「見守り業務」とは

まずは、介護施設等の仕事における見守りを解説します。
介護士が行う見守りとは、「いつでも安全確保やサポートできるよう、側で付き添う事」。
介護士業務の中では、下記の様な場面で見守りが必要です。
- 転倒リスクがある方が動いた時、すぐ付き添える状態でいる
- 食事や更衣など、出来ないところを付き添いつつサポート
- 自立動作に危険がないか、側で見守る
介護施設では、事故回避の為に行われる事が多いですね。
ただ近年では、自分で出来る事を大切にする「自立支援」への重要性が見直されてます。
それに伴い、ケア方法としての見守り介護も広まってきました。
具体的に見ていきましょう。
「事故リスク」「危険」への備え

介護士の間では、よく「フロアの見守りお願い」なんて指示があります。
これはざっくり言うと、「利用者様の安全や様子を見て、上手く対応して」という事。
具体的な内容を述べると、こんな感じです。
見守りの業務の内容例
- トイレ訴え等への対応
- 転倒リスクのある人への付き添い
- 危険リスクへの配慮
見守り業務は、見てるだけではいけません。
危険があれば付き添い、必要なら介助に入る必要があります。
例えば、「転倒リスクのある方が動いたら付き添う」。
「トイレ訴えがあれば付き添い、必要な介助や排泄量チェックを行う」等ですね。
ある程度の業務知識、利用者様の情報理解を必要とする業務ですね。
「見守り業務」での注意点

介護のお仕事は、常にこうした見守り業務をしつつ進めていきます。
時間で決められた業務以外にも、こうした目配りや対応を同時に行う必要があります。
フロア見守りの際は、下記の様な点に注意しましょう。
見守り業務のポイント
- 徘徊や転倒など、危険リスクのある方を優先
- なるべく多くの利用者を視界に入れる
- 1人の介助に集中しすぎない
基本的に、全員の所在や状態を把握してるのがベスト。
「フロア」と呼ばれる共有スペースは離れず、居室等にこもらない様にしましょう。
ただ現実的には難しいので、上記の様なポイントを押さえながら動いて下さい。
トイレや居室での介助中も、1つに集中しすぎずちらちらフロアを確認しましょう。
日頃から利用者毎の対応方法を把握しておく事が大切ですね。

特に注意が必要なのが、転倒事故です。
介護施設では、「見守り=転倒リスクの高い方への対応」みたいな面もあります。
トイレ中や歩き出し等、リスクの高い人や場面にいる方は要チェックです。
1度に対応できる方は限りがあります。
危険リスクを見て「対応の優先順位」を考えておきましょう。
そんな時は、「注意が必要な方はいますか?」など指示を仰ぐと良いですよ。
自立支援のための「見守り介護」

もう1つは、ケア方法としての見守りですね。
「見守り援助」、「見守り介護」などとも言われます。
これはやってあげるのでなく、共に行う支援方法を指します。
介護の仕事は、「何かをやってあげる」だけではありません。
時には側で見守り、自立を支援する動きも大切です。
見守り介護の例
- 着替えの方法を指示し、サポートする
- トイレや食事を促す
- 移動や入浴時に危険が無いよう付き添う

いつでも援助に入れるよう付き添いつつ、「声掛け」や「指示出し」等で自立支援する方法ですね。
自分で出来る事を大切にし、出来ない事のサポートを重視する考え方です。
ただ「やって欲しい」という気持ちが強い方もいますし、相手の状態や負担を見て、臨機応変に対応する必要もあります。考え方もそれぞれですので、介護方法で正解を見出すのは非常に難しいですね。
「見守り」に関するサービスやシステム

見守りという言葉が使われるのは、介護職内だけではありません。
介護や高齢者を意識したサービスや商品でも、見守りという言葉が使われます。
例えば、こんな感じの内容があります。
商品機能やサービスでの見守り
- 高齢者の見守りサービス
- 「見守りカメラ」などの見守り家電
- 介護機器の「見守り機能(システム)」
これらは、いずれも「様子確認」や「機器検知」目的のサービスや機能ですね。
順にご説明します。
高齢者の見守りサービス

高齢者の見守りサービスとは、高齢者の異変や危機を知らせてくれるサービスです。
主に、外出中や離れた家族の危機確認などに使用されます。
下記の様に、サービスによって見守り方法は異なります。
見守りサービスの内容例
- 職員による訪問
- 見守りカメラや家電による異変検知
- 認知症による徘徊対応
サービスの実施団体も、企業から自治体まで多様です。
電気や防犯などのサービスに付随する形が多いのも特徴ですね。
家族の危機管理に使用したり、職員による定期訪問など見守り方法も様々。
また高齢者が自発的に危機を知らせる事ができる物もあります。

また自治体を主体とし、地域規模での見守りもあります。
※認知症の徘徊防止のため、「名前や住所が分かるステッカーを配布する」など
介護で使える「見守り家電」

また介護を意識した家電などにも、見守り機能が搭載された物があります。
ここでいう見守りも、様子観察や危機感知などの意味合いを持ちます。
認知症等も含め、様々な危険を感知し、介護をしやすくする為のグッズが中心です。
例えばこんな見守り用品がある
- 見守りカメラ
- ワイヤレスチャイム
- 介護機器(センサー付きのマットやベッド等)
ご家庭で使われるのは、「見守りカメラ」や「ワイヤレスチャイム」等ですね。

見守りカメラとは、互いの様子を映像や通話で確認したり、異常検知などが出来るカメラ。
見守りサービスの1つとして設置される事もありますが、個人で購入しても使用できます。
ワイヤレスチャイムは、いわば家庭用のナースコールですね。
下記記事でそれぞれ解説してるので、興味があればご覧ください。
施設の介護機器にある「見守り機能」

老人ホームで使われる介護機器にも、色々な見守り機能が搭載されてます。
「様子観察」や「危機確認」の意味では、ナースコールやPHSなどもその1つですね。
代表的なモノや特徴的な内容をご紹介します。
見守りに使える介護機器
- ナースコール
- センサーマット(離床・起き上がり検知)
- 眠り、スリープスキャン(心拍・睡眠状況確認)

中でも代表的なのは、マットやベッドによるセンサー機能でしょうか。
これは起き上がりや離床を検知し、職員に知らせてくれる介護機器です。
主に転倒リスクのある方に使用し、職員が駆け付け付き添う為の機械です。
「睡眠状態」や「呼吸状態」が分かる見守りシステム
近年では、介護機器も進化しており、職員の負担軽減を意識した見守り機器も登場してます。

例え「眠りスキャン」「スリープスキャン」と呼ばれる見守りシステムがあります。
これらはベッドにセンサーを敷く事で、下記状態を把握できる機械です。
眠りスキャン等で分かる事
- 心拍や呼吸数
- 覚醒状況
- 体動や起き上がりの検知
これらを個別に把握し、PCやスマホなどでモニター管理できます。こうした見守りシステムの登場で、利用者様の生活に合わせたケアや状態の分析などが可能になりました。
介護職員の負担軽減だけでなく、利用者様の生活満足度を高める為にも使用されます。

近年では、膀胱内の尿を測定するセンサーも登場しました。
これにも、起き上がり検知等の見守りセンサー機能が搭載されてます。
介護機器の見守り機能も日々進化しており、なかなか面白いですよ。
見守りの目的はどれも「安全や健康を守る」こと
今回は、介護における「見守りの内容や意味」を幅広くお伝えしました。
色々書きましたが、結局のところ見守りの意味は「相手の安全や健康に注意を払う事」です。
その為の業務やケア、家電や機器の機能など、見守りの方法は様々です。

介護をしていると、介護事故を防ぐ難しさを実感させられます。
転倒による骨折、ベッドからの転落など、高齢者介護ではあらゆる所に危険が潜んでいます。
また見守りで重要となるのは、相手を観察し理解や気付きを増やす姿勢です。
そうする事で介護機器の便利機能も、さらに活かす事が出来ます。
安全を守る意味では、「介護記録」や「ヒヤリハット」も重要です。
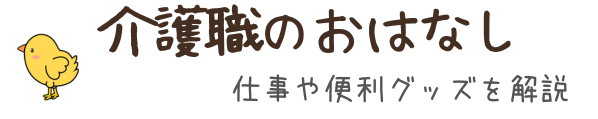
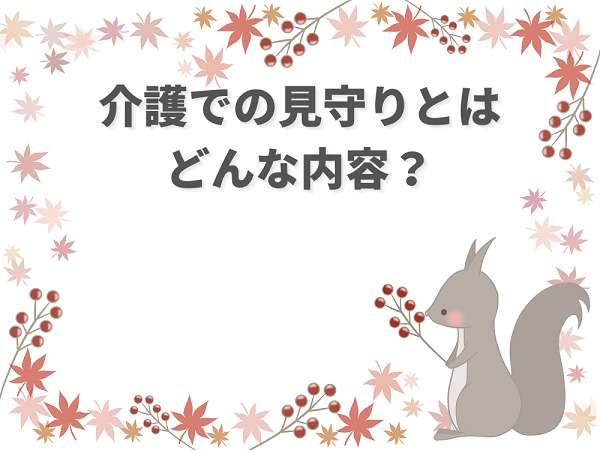
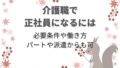

コメント
応援の村ぽちです。
往復でポチッ!!
IN 30
OUT 20
介護ブログ(6,103サイト)194位