「介護の勉強をしたいけど、何をすべきか分からない」という事はないでしょうか?
「仕事で介護を始めたい」「親の介護の為に勉強したい」など、事情も様々でしょう。
当記事では介護初心者の為、介護の勉強は何からすべきかを解説。
自分の介護職経験を活かし、仕事で必要な資格や覚えるべき知識をお伝えします。
- 介護を始める時にまず勉強したい事
- 介護士が最初に取るべき資格、資格を取る順番
- 介護の勉強に役立つ本や情報
今回は上記について、順に紹介します。
「介護資格を取る順番」や「最初に介護の何を勉強すべきか」など…
介護の勉強方法のヒントになれば幸いです。
介護初心者の勉強は何から始めるべき?【必要知識】

まずは、介護を行ううえで必要な知識を簡単に紹介します。
今回は下記3つに分け、お話しします。
- 身体介助の基本技術・知識
- 福祉用具・介護用品の使い方
- 高齢者コミュニケーション、認知症対応
どんな人と関わってるかでも、必要な介護知識は異なります。
自分が介護をしてる相手をイメージしつつ、何を学習すべきか考えましょう。
身体介助の技術・知識

介護を始めるにあたり、多くの方が「難しい」と口にするのが身体介助。
特に下記は「3大介護(3大介助)」と呼ばれ、介護業務の基本となります。
- 食事介助
- 排泄介助
- 入浴介助
言い換えると、「食事を食べさせる」「トイレ介助やオムツ交換の仕方」。
「お風呂に入るのを手伝う」といった技術です。
これから「介護の勉強をしたい」のであれば、こうした身体介助から学ぶと良いでしょう。
観察ポイントなど、必要な事も自然と身につきます。

介護が必要な高齢者には、日常動作にも多くの危険があります。
「きちんと食事を呑み込めたか」「安全に衣服が着脱させられるか」など…。
これらを安全に行う為のモノが介護技術です。
歩行時の付き添いや車椅子の操作など、安全に移動する為の技術・知識も必要ですね。
福祉用具・介護用品の使い方
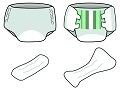
介護現場では、介護用品や福祉用具の使用も多くあります。
介護を行うのならば、これらの扱い方も覚えておきたいところ。
例えば、下記の様な物ですね。
- リハビリパンツ、オムツカバー
- 介護ベッドや車椅子、手すり
- 食器やエプロン
介護用品は便利ですが、正しく使用しないと危険なモノもあります。
例えば、「車椅子に乗る時はブレーキをかける」といった事等ですね。
正しい介護用品の使用方法を学ぶのも、介護を行うにあたり必要な事です。
他にも、「尿取りパッドの選び方」や「オムツの正しくあて方」も学んでおくと便利です。
介護初心者が勉強したい知識の1つですね。
⇒「介護用オムツカバーの使い方」と「漏れない為のサイズ選び」

便利な事の例を少し出してみます。
- ポータブルトイレを使い、「ベッドの側でトイレを使う」
- 浴槽用の手すりで「楽に浴槽をまたぐ」
- 介護ベッドの高さ調整で「移乗を楽に行う」
こんな感じで、介助者・要介護者の双方の負担を減らす事ができます。
ただ正しい使い方を理解しないと、かえって危険もあります。
「車椅子のブレーキをかけず移乗介助をする」なんかが、分かりやすい例ですね。
在宅介護での便利グッズ

介護に関する商品には、在宅介護でこそ役に立つ品もあります。
例えば、高齢者向けの家電ですね。
- 見守り用のカメラ
- 家庭用ナースコール(ワイヤレスチャイム)
- 徘徊対策用のセンサー・GPS
介護保険の対象でない物にも、高齢者介護に役立つグッズがあります。
特に在宅における親の介護では、施設等に比べ他者から知識を得る機会が少ないです。
介護用品の事も含め、この機会に知識として持っておくと良いと思います。
高齢者とのコミュニケーション

介護は人間相手に行うモノであり、感情労働とも言われる仕事です。
人との関わりは避けられず、コミュニケーションの方法も考えなくてはなりません。
尊厳を守り不快にさせないのはもちろん、良好な関係は介護のしやすさにも関わります。
信頼を得られれば、「あなたが言うなら間違いない」と協力を得られます。
いくら技術や知識があろうと、拒否をされれば何もできません。
お互いに気持ちの好循環を作るためにも、日頃から良好な関係を気付く事が大切ですね。

また高齢になれば「見えない」「聞こえない」など、様々な問題も出てきます。
ジェスチャーや筆談など、相手に応じたコミュニケーション方法を考えてみましょう。
こちらは定型化されてる部分もあるので、介助方法とセットで声掛けも覚えておきましょう。
認知症対応

高齢者介護では、認知症の対応もしなくてはなりません。
加え、様々な要因により気持ちや行動のトラブルが多発します。
そうした時、正しい説明ではかえって混乱を招くことがあります。
認知症対応では、言葉や行動の裏にある原因や感情を読み取る必要があります。
こちらも正解がケースバイケースであり、難しい部分ですね。
そして相手を理解する事から始めると、ヒントが得られると思います。
最初に取る介護資格は「初任者研修」

介護の勉強という事で、「何の資格から取るべき?」悩んでる方も多いでしょう。
初めて介護職に就くならば、「初任者研修」から取得します。
これは旧ヘルパー2級に相当する資格で、初めて介護職で働く際の入門資格です。
介護に必要な知識が詰め込まれた研修ですので、介護を学ぶならこちらを取得しましょう。
介護を仕事にしたいなら、まず最初に取得する資格ですね。
初任者研修で学べる事

初任者研修は業務や評価に関わるほか、下記の様に勉強する内容も有用です。
- 身体介助
- 高齢者とのコミュニケーション
- 高齢者や認知症理解
初任者研修では、介護に必要な基本知識・技術を網羅的に学習。
前項で紹介したような「身体介助」「コミュニケーション」等も学ぶ事が可能です。
身体介助でいえば、車椅子介助やオムツ交換、着替えなどが実技で学べます。
認知症や高齢者の心身、介護に関する制度など、知識も豊富に勉強できます。
介護の勉強がしたかったり、何を勉強すべきか分からない方は、初任者研修の受講がオススメ。
介護資格はどの順番で取る?

介護資格は、主に下記の順番での取得が想定されています。
- 介護職員初任者研修(入門)
- 介護福祉士実務者研修(応用)
- 介護福祉士(国家資格)
- 介護支援専門員
入門となる「初任者」に始まり、経験者向けの「実務者研修」。
そしてベテラン証となる国家資格の「介護福祉士」という順番です。
上記資格は、介護職としての知識や経験を証明できます。
実務経験を積みこれらを順番に取得する事で、自然にステップアップできる仕組みです。
⇒介護職のキャリアアップ方法を「資格」「役職・職種」で解説
介護資格に取得条件はある?

初任者と実務者は、どちらも受講条件はありません。
ただ実務者研修は応用知識の他、初任者研修の内容も含まれます。
免除もあるので、初任者研修から取得してもデメリットはありません。
介護福祉士の受験には、実務経験3年と実務者研修が必要です。
その為実務経験3年を満たすまでに、「初任者⇒実務者」の順で資格取得するのが一般的です。
介護支援専門員とは、利用者のケアプランを考える人ですね。
親の介護に役立つ資格はある?

もし親の介護のため資格が欲しいならば、下記が候補になります。
- 初任者研修
- 准サービス介助士
注意点から先に言うと、介護資格の取得には時間も費用もかかります。
既に介護をされてる方には、大きな負担になりかねません。
資格取得での学習は、将来的な介護に備え勉強したい方向けの方法です。

その点も踏まえ紹介すると、しっかりと学習するなら初任者研修。
介護職向け資格として紹介しましたが、親の介護に向けて取得する方もいます。
介護技術の知識や実技、施設や制度の事まで、総合的に学習できます。
現在介護をされてたり、気軽に資格取得したいなら、准サービス介助士があります。
「准」なら自宅学習のみで取得でき、介護学習の入門として役立つでしょう。
介護の勉強に役立つ本
.jpg)
仕事でも親の介護でも、既に介護を始めてるなら本での学習も有効です。
悩みや疑問がはっきりしてるケースが多く、得るべき介護知識も分かりやすいと思います。
介護の参考書籍を紹介しますので、必要知識に合わせ手に取ってみて下さい。
目で見てわかる最新介護術【身体介護】

身体介助の技術であれば、下記書籍がオススメ。
移乗や着替え、入浴や排泄など、各場面での介護技術が丁寧に解説されてます。
目で見てわかる最新介護術
写真を多く使って解説してるので、初心者にも分かりやすいです。
細かな手順や注意点など、理解が捗る内容となってます。
イラスト図解 いちばんわかりやすい介護術

こちらは図解で介護技術を解説した書籍です。
イラストによる分かりやすさはもちろん、文章での説明もしっかりしてるのが特徴。
イラスト図解 いちばんわかりやすい介護術
介助時の注意点や手順、高齢者の体の事など、基本知識を丁寧に解説してます。
各介助方法について、その理由説明もしっかりしており好印象。
こちらも初心者介護士が身体介助を覚える際、オススメしたい1冊ですね。
介護の現場と業界のしくみ【介護施設の解説】

これから介護職で働きたいけど、「施設や職場が良く分からない」。
そんな方には、コチラの書籍がオススメ。
介護の現場と業界のしくみ
こちらは介護職を目指す方向けの書籍。
各介護施設の特徴、転職アドバイスなど丁寧に書かれています。
施設種類によりどんな特徴があるかなど、仕事のイメージを掴むのに役立ちます。
⇒初心者介護士へオススメしたい本まとめ
親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと

入院をきっかけに介護が始まったり、意識する方も多いと思います。
下記はタイトル通り、親の入退院や介護の知識を解説した書籍。
親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと
介護保険の事、在宅・施設介護の事などを細かく解説されてます。
「親の介護が必要になりそうだが、よく分からない」という方は、得る物があるはず。
親の見守り・介護をラクにする道具・アイデア・考えること

こちらは「在宅での親の介護」に向けた書籍です。
親の見守り・介護をラクにする道具・アイデア・考えること
タイトルの通り、親の見守りや介護について書かれています。
- 介護を意識した家環境や便利な道具
- 介護保険や介護サービスの知識
- 親が心配な時、見守りや自立を助ける便利グッズ
先の書籍と比べ、在宅・遠距離介護に寄った内容ですね。
介護における日常生活の悩み、認知症対策グッズなども紹介されてます。
既に在宅での介護が始まってる方は、参考になる情報が得られると思います。
介護で使える言葉がけ シーン別実例250【コミュニケーション】

コミュニケーションや声掛けを勉強したい場合、こちらがオススメです。
介護で使える言葉かけについて、細かく紹介されてます。
介護で使える言葉がけ シーン別実例250
各種身体介助や認知症対応など、シーン別に実践的な声掛けを学べます。
「高齢者へ声かけが分からない」「介護における言葉の引き出しを増やしたい」。
そんな時は、こちらの書籍が勉強になります。

またより心理的な内容であれば、下記書籍が為になります。
対人援助の現場で使える 聴く・伝える・共感する技術 便利帖
実際の介護現場でも、当てはまる場面が数多く取り上げられてます。
「高齢者の対応や声掛けが上手くいかない」「どう声をかければ良かったのか?」など…
コミュニケーションに悩み、行き詰ってしまった方は、本書からヒントが得られると思います。
介護の勉強の仕方は他にも【介護研修・勉強会】

各種自治体でも、介護に関する研修や勉強会を実施しています。
専門職の他、在宅介護者に向けた内容もあります。
1人で悩んでる不安や疑問があれば、こうしたコミュニティに参加してみるのも有効です。
もし興味があれば、下記等の内容を調べてみると良いでしょう。
- 市区町村の「家族介護者支援事業」
- 各都道府県の「介護実習普及センター」
- 自治体による「専門職向け介護研修」
地域包括支援センターでも、家族介護の様々な相談を受け付けてます。
お住まいの地域で受け付けてるので、調べてみて下さい。
チャンスも多いかと思いますので、機会があれば積極的に参加しましょう。
勉強だけで介護を覚える事は難しい

ここまで「介護の勉強方法」について解説してきました。
何を学ぶべきかは、「どんな人が相手か?」で内容は変わってきます。
元気に動ける人であれば、安全に過ごせる環境づくりや見守り。
介助が中心なら身体介助など…、私達のサポート内容も異なります。
これから介護を始めるなら初任者研修を受けるのが、一応の結論となりますね。

途中でも言いましたが、介護をする相手は人間です。
その人の持病や心身の事情など、何が正しいかもケースバイケースです。
マニュアル化できるものではなく、実際の介護を通し相手への理解を深めねばなりません。
最初のうちは、実際の介護で分からない事を解決しながらの勉強が有効です。
迷った時は、ここで紹介した資格や本での学習が役に立ちます。
下記で、今回解説しきれなかった内容も紹介してます。
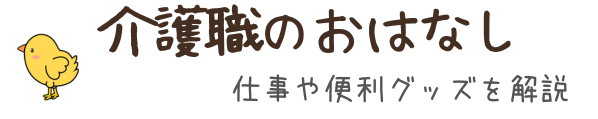
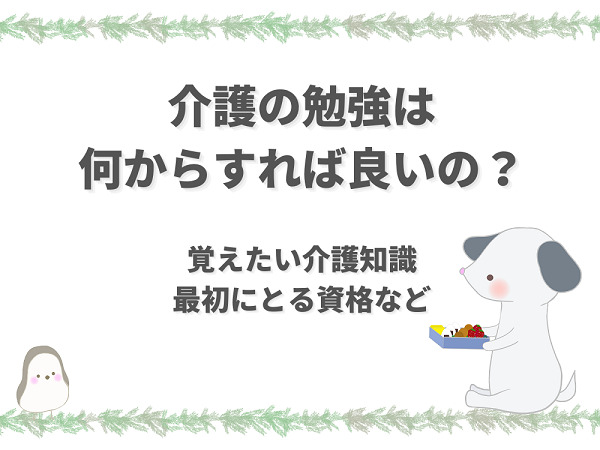


コメント