介護士を中心とした介護職は、年間休日や有休がどれぐらいあるでしょう?
働きやすい職場に転職するには、毎月の休日数も大切なポイント。
「本当に休めるのか」「有給は使えるか」という実態も気になるところ。
当記事は、「介護職(介護士)の平均年間休日と有給の実態」をテーマにまとました。
- 介護職の平均年間休日、有給取得率
- 休みが減らされる職場実態
- 休日数の多い職場への転職方法
これらを中心に解説、改善に成功した優良企業もご紹介します。
主に介護士を中心とした内容ですが、他の介護職にも当てはまると思います。
介護職の年間休日数はどのぐらい?

介護職の休日数は、職場によりいくらか違いがあります。
色々な施設で介護士として勤務しましたが、月休9日が平均的です。
あるいは2月のみ公休8日とし、年間休日107日とするのが一般的です。
職員数に余裕があれば、これに加えて有給取得する余裕が生まれる。
いない場合は、休日出勤が必要になります。
医療・福祉分野の年間休日数
.jpg)
実際の調査データから、介護士の年間休日数を紹介します。
厚生労働省による調査結果に、「医療・福祉分野」の年間休日データがあります。
医療・福祉分野の年間休日
・1企業 平均年間 休日総数【109.4日】
・労働者1人 平均年間 休日総数【111.5日】
※参考:厚生労働省(平成30年就労条件総合調査の概況)
医療分野も加わってますが、平均年間休日数はおよそ「110日」です。
※平成30年のデータですが、産業別の調査データはこちらが最新でした

回答項目別にみると、下記の様になります。
- 「100~ 109日 (40.4%)」
- 「110~ 119日 (24.7%)」
- 「120~ 129日 (19.4%)」
冒頭で述べた「月の公休9日」という職場が多い感じですね。
※9日×12ヵ月=108日
福祉分野の休日数を他業界と比較

この数字は、他業界と比べるとどうなのか?
同調査内容から、「企業全体の平均年間休日数」と比べてみましょう。
※( )内は、医療・福祉分野
- 1企業平均 107.9日(109.4日)
- 労働者 1 人平均 113.7日(111.5日)
医療・福祉分野は、平均と同じぐらいの年間休日数ですね。
ちなみに介護求人においても年間休日100~110日は、よくみられる数字。

「1企業の平均年間休日」で見ると、休日数が少なかった業種は下記2つ。
- 運輸・郵便業 (100.3日)
- 宿泊・飲食サービス業 (97.1日)
休日数が多かったのは、「情報通信業(118.8日)」という結果でした。
介護士の1週間の労働日数

「介護士」に特化したデータも見てみましょう。
介護労働安定センターの資料に「1週間の労働日数」のデータがあります。
『介護職の1週間の労働日数の平均』
介護職員 【4.7日】
・正規職員 【4.8日】
・非正規職員【4.5日】
訪問介護職員 【4.8日】
・正規職員 【4.9日】
・非正規職員 【4.7日】
サービス提供責任者【5.1日】
・正規職員 【5.1日】
・非正規職員 【5.0日】参考:介護労働安定センター(令和4年度 介護労働実態調査結果)より
訪問介護と施設介護では大きな差はなく、週に5日程度の勤務。
すなわち週休2日という事で、平均的な休日数です。

やはり非正規の方が休日数が多いですね。
介護施設では、少しだけ正職との開きが大きくなります。
仕事量の多さもあり、勤務日数は多めという結果に。
介護士は、年間で休日のバラつきも少ない仕事です。
特別休暇もあまりないです
これだけで年間休日を完全には把握できませんが…、
ここまでの内容で考え、介護士の年間休日は105日~110日程度が平均とみて良いでしょう。
希望休はどれぐらい取れる?

介護職は一部を除き、毎日仕事があります。
休みも不定期なシフト制なので、毎月希望休を取る事が出来ます。
希望休に関しては、月に3日程度が一般的です。
シフト作成者や職場ルール次第では、夜勤等の指定が出来る事も。
それとは別に希望を取れる事が多いと思います。
働きながら資格も取れる

介護資格には、初任者研修や実務者研修など、スクーリングが必要な資格もあります。
これらの様な仕事に関する資格を働きながら取る場合、職場の協力を得る事も可能です。
恐らくですが、相談すれば毎週の休日を指定可能できます。
資格取得や研修など、希望を多く出したい時は素直に相談しましょう。
思い切って転職を考えましょう。
ちなみに私が特養で働いてた時は、月の希望休は3日まででした。
年間休日は「107日」、月の公休は9日(2月のみ8日)。
人手不足・人材獲得に苦労している、所謂”並”の施設です。
要注意「休みを少なくされる介護施設」も

介護士の平均休日は「年間107日~109日」「月9日」と話しました。
多いとは言えませんが、全体と比べても平均的な数字です。
ただ介護業界は人手不足にあり、実際にはもっと休みが少ない職場もあります。
休日数は「職員数次第」
介護職、特に介護士の休日数は「職員数」次第によるところがあります。
職員が足りなければ、誰かがその分の穴埋めをしなくてはなりません。
それを担うのは、やはり現場の介護職です。

職員が少ない職場では、こんな勤務が必要になります。
- 休日出勤
- 残業、早出(時間外労働)
- 半休
休日出勤や残業が増え、休日が減り、勤務時間が増えます。
休日出勤分は時間外勤務扱い。
職員不足の環境では、次月に休日が戻る事は期待しにくいです
勤務時間半分での出勤=半分休日ということ
上記3つが増えてきたら、相当人員不足に困っている職場と考えて良いです。
職員不足が「働き方」に与える悪影響

職員の不足や偏りは、働き方にも影響します。
「連勤」や「夜勤数の増加」が、その主な所です。
また職員が少ないと、急用や体調不良でも休みにくさを感じる事もあります。
周りへの気遣いから、休む事が負担になるケースもあるので注意しましょう。

この様に介護職において職員数は、働きやすさを決める重要な要素です。
ここで紹介した様な職場に出会ってしまったら、早めに逃げるのが賢い選択です
休日出勤が多い施設を見破るには
職員が少ない施設の特徴は、職員の定着率が低いこと。
労働環境が悪いため、職員の入れ替わりが激しく、負のスパイラルに陥ってます。

考えられる原因としては、下記の様なモノがあります。
- 労働環境への不満
- 給料が安い
- 人間関係
コレという原因を1つに絞る事は難しいのですが…、
給与や働きやすさなど、職場の魅力が不満に大きく負けてる時でしょうね。
当然働いても満足度が低く、働きやすい職場とは言えないでしょう。
職員数がいると思っても、急に人がいなくなる事もあります。
「人員確保のスピード」は要チェック
現場がピンチの時ほど、職場の改善・対応力が明らかになります。

労働者目線で見ると、下記内容を見ると良いですね。
- 派遣労働者を雇い入れる余裕がある
- 管理者や他職種の助けや関心がある
- 人員確保のスピード(すぐに新規雇用があるか)
とにかく人員確保のスピードですね。
人手不足とはいえ、魅力ある職場には人が集まってきますから。
人がいない状況をどう回避し改善するか、職場の信頼性・運営力を見定める機会です。
「労働環境が改善されない」、「もう自分は限界」と感じたら、迷わず逃げて下さい。

「魅力ある職場」を選ぼう
これから転職するのであれば、上記要素に加え「求人に魅力があるか」も要チェック。
給料や待遇が良く、積極的な募集があればすぐ職員は集まります。
逆に「いつも募集が出され、かつ条件の悪い職場」は、危険なので注意。

転職サイトだと、マイナビ介護職が「職員定着率」にこだわっておりオススメ。
良質な職場紹介に期待できます。
介護士の有給休暇取得状況
介護士の有給休暇についても、ご説明しておきます。

結論を言ってしまうと、「付与はされるが使用が難しい職場」が多いですね。
それでも有給の使いやすいはちゃんとあります。
2極化されてるので、職員の多い職場を選ぼうというのが結局のところですね
他の労働環境に注目しても、優良企業と言って良いでしょう。
「医療・福祉分野」で見る有給取得率
休日と同様に、有給の平均取得率を見てみましょう。
厚生労働省の資料に、「医療・福祉分野」の有給取得状況があります。
『医療・福祉分野の有給取得状況 (労働者1人平均 )』
【有給付与日数】17.0日
【有給取得日数と取得率】8.9日(52.2%)参考:厚生労働省(平成30年就労条件総合調査の概況)
有給の付与は17日、取得日数は約9日。
取得率はおよそ50%です。
上記は介護職に特定するものでなく、あくまで「医療・福祉」のデータです。
同資料より、全体の平均と比べてみます。
【有給付与日数】18.2日
【有給取得日数と取得率】9.3日(51.1%)
医療・福祉分野と大きな差は無い結果ですね。
介護士の有給取得率の実態

前項の結果を受け、「そんなに有給は取れない」と感じた介護士さんも多いでは?
私もその1人ですし、有給はほとんど取れてないです。
※参考:介護労働安定センター(介護労働者調査の統計表)より
ちなみに1番多く回答を集めたのは「人手が足りない(53.0%)」でした。
この様な現状では「有給休暇は取りにくい」と考えるのが妥当でしょう。
2019年に有給取得が義務化されましたが、体感では状況に変わりはありません。
有給取得義務化で介護士はどうなった?
2019年に働き方改革により、有給取得が義務化されました。
※年10日以上有給休暇の権利がある職員従業員は、最低5日以上は取得

これにより介護士が休めるようになったかと言うと、否です。
私の経験上、介護士の有給取得実態は下記。
- 有休を取得すると、他の誰かが休日出勤をする
- 退職前に一気に取得する
これは実際に私の職場で起きてる現状です。
交代で有給取得しつつ、不足分を他職員が休日を削り働いてます。
取得できるだけマシかもしれませんが、休暇の役割は果たせていません。

シフト作成者の「有給への配慮」も取得率に関わるポイントですね。
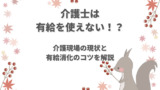
良い職場を見分けるポイントとして使えますね。
「休日数」「有給の確保」には職員数が必須
ここまでの内容をまとめると、休日数も有休取得も「職員数が必要」という事。
職員数が影響するのは、それらだけではありません。
- 忙しさが減る
- 仕事の質を上げる余裕ができ、スキルアップに繋がる
- 残業が減る
良い労働環境を求めると、結局「職員の数が必要」という結論になってしまうのです。
それほどまでに、マンパワーは正義です。
人不足は悪だと思って良いです。

「同業他社との人材獲得競争が厳しい」というのは、多くの事業所が抱える悩みです。
ですが、その競争に勝っている、介護士が魅力を感じ集まる職場もあるワケです。
人材が多いという事は、有給や休日に関しても安定しますから定着率も良いですね。
好循環にある職場です。
転職活動の際は、「休日の多い職場」を選びつつ、働きやすさにも注目です。
介護職が「年間休日数の多い職場」に転職するには?
介護士を中心とした介護職が休日(有給消化)を増やすには、下記の方法があります。
- 転職(職場・雇用形態を変える)
- 職場環境・働き方を変える
「転職」するか「今の職場環境を改善する」か、という事ですね。
後者はそれが出来る立場も限られるし、労力も掛かります。
上手くいく保証もありません。
多くの人にとって、休日を増やす方法は転職になるでしょう。
「年間休日数110日以上」を狙う
介護職が休みの多い職場に転職するなら、「年間休日数110日以上」は最低条件ですね。
そこから給料や有休、施設種類などで好みの職場を探しましょう。

また下記の様な特別休暇がある職場を選ぶのも有効です。
- GWやお盆などの「季節休暇」
- 誕生日月の「アニバーサリー休暇」
これらがある場合、月休9日でも年間休日数はもっと多くなります。
加えて、産休や介護休暇の実績があればなお安心ですね。
⇒介護士は育休・産休は取りにくい?
労働環境への意識が高い職場を選ぶ
もう1つ注意したいのが、しつこく話してる「職員数が多い事」ですね。
公休や有休が多くても、人手が無ければ無理な話です。
職員補充スピードが速く、定着率の良い職場。
即ち、労働環境改善への意識が高い職場を選びましょう。

これは就職してから分かる部分ですが、下記要素はよく確認したいですね。
- 残業を減らす努力があり、残業代はちゃんと出る
- 給料が良く、評価基準も明確
- 雰囲気が良く、職員同士が協力的
面接の際は、管理者に近いポジションの方が面接官を務めます。
上司ともなる存在なので、「面接官が信頼できるか」で考えても良いでしょう。
派遣やパート等の非常勤で働く
介護職が休日を増やしたい時、最も確実な方法は派遣やパートで働くこと。
自分でも希望条件を出せるので、休日数を会社に依存させなくて済みます。
勤務可能な時間帯も指定できるのもポイント。

「正社員でなければ…」という風潮もありますが、介護業界は別です。
人手不足の為、非常勤の時給相場が高い傾向にあります。
需要が高い為、全体的に好条件で働けますよ。
派遣の場合は、時給相場が特に高い傾向です。
総合的には、正社員より働きやすいと言えますね。
長くマイペースに働けるだけでなく、収入面の問題も少ないですよ。
「休日数の多い求人」が探せる転職サイト
休日数に関わらず、良い職場に転職するには「情報収集」が大事です。
介護職であれば、介護系の転職サイトがあるので活用しましょう。
転職エージェントは内部情報も把握してるので、詳しい情報にも期待できます。
求人紹介も行ってるので、条件を伝えれば、マッチングにも期待できます。

まず正社員やパート狙いの時にオススメなのは、マイナビ介護職。
サポート力に優れており、介護系でも定番の転職サービスです。
- 職員定着率があまりに低い職場は掲載しない
- 「職業紹介優良事業者」認定取得
派遣であれば、かいご畑がオススメです。
派遣で働けば、初任者研修などの資格が無料で取得できます。
未経験者向け求人にも強く、自身が無い方にもお勧めです。
【実例】年間休日と有給への取り組む介護施設
最後に、働きやすい介護施設もある事をお伝えしたいと思います。
介護の職場にも、働きやすさの改善に取り組むところがあります。
その施策1つとして「年間休日を増やした」例を紹介しましょう。
「職員を大事に」で雇用改善に成功した特養
紹介する事例モデルは、茨城県石岡市の特別養護老人ホーム。
「利用者を第一に」「職員を大事に」を理念とし運営する施設です。

そこでは、下記の様な取り組みが行われています。
・年間休日は123日(年末年始休暇6日、夏季休暇3日含)
・「年次有給休暇」は時間単位で取得可能、
・年2回の面談で、離職防止や人事面に活用
・EPA(経済連携協定)に基づく外国人受け入れ
・併設病院内に託児所を用意し、労働時間にも配慮
・外部研修、資格取得もその費用を施設負担でバックアップ
※介護労働安定センター 茨城支部
「介護事業所の「魅力ある職場づくり」のための雇用管理改善への取り組み」より
年間休日123日は、介護施設ではトップクラスではないでしょうか?
結果として、過去3年の離職率は全国平均の半分以下。
残業も月平均0.4時間 、有給取得率も74%になりました。
若年層もバランスよく採用でき、定着しているとの事。
面談による「離職防止」効果
この特養では、面談を離職防止や人事に活用しています。
配置の希望を聞いたり、労働時間を考慮するなど…、
職員が「働くうえでの希望・悩み」を伝えられる場として、機能しているのが伺えます。

上司からの話や評価を受けるだけという、一方的な面談ではありません。
名ばかり面談ではなく、きちんと離職防止効果が出せてるのがポイント高いですね。
意外なことに、「ワークライフバランスを意識した施策はしてない」という話。
とにかく職員を大事にし、コミュニケーションを意識してるのが特徴。
職員を大事にしようと考え動いた結果、成功した好例ですね。
外国人実習生も活用
注目したいのが、他よりだいぶ早い段階で外国人実習生を受け入れている事。
介護の仕事を学ぶ為に、日本に実習に来た方達ですね。
これが人員確保に一役買ってると思います。

一緒に働いたことがあるので分かりますが、下手な日本人より働きますよ。
仕事を覚えるのも凄く早い。
コミュニケーションも問題ないし、礼儀正しいです。
介護にも良い職場は沢山ある!
介護の職場と言うとネガティブな話が多いですが、良い職場もちゃんとありますよ。
ポジティブな転職活動の原動力になればと思い、ちょっと長くなってしまいました。
また良い事例が見つかったら、別の機会にご紹介できればと思います。
他の実例も、下記記事で紹介してますので良かったら。
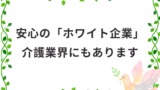
こんな職場を見つけるには、「転職サイト」のエージェントに相談するのも手です。
色んな職場を知っているので、意外な情報が見つかるかもしれません。
諦めずに、理想の職場に出会えるよう動いてみましょう!
まとめ
今回は、「介護職の休日数と有給の実態」をテーマにお話ししました。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
- 介護職は平均年間休日110日、有給取得率52%ぐらい
- 職員不足の職場では、もっと数字が低くなる
- 休日を増やすには、「職場改善意識の高い職場への転職」
「派遣やパート等の雇用形態で働く」方法等がある。
要点をまとめると、こんなところでしょうか。
色々な記事で言ってますが、介護業界は職場による環境差が大きいです。
休日だけでなく、給料等も該当します
どうしても辛い時は、身体や精神に支障が出る前に逃げて下さい。
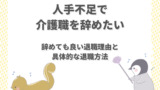
介護職の休日数、働き方に関しては思う所があり、下記記事も執筆してます。
ワークライフバランスに関心があれば、ご覧頂けると嬉しいです。
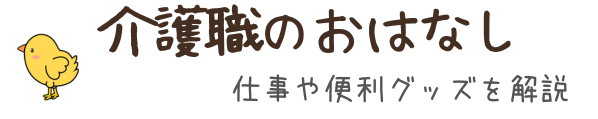



コメント