介護士として初めての職場、未経験・経験者も不安がいっぱいです。
本当に一人前になれるのか、心配になりますよね。
そこで今回は、「新人介護士が独り立ちするまでの期間と流れ」を解説します。
- 介護士が独り立ちする流れ、仕事に慣れるまでの期間
- 新入職員が仕事へよく躓くポイント
- 仕事が覚えられない、放置等、指導トラブル
介護士としての転職・指導経験をもとに、上記内容をお話しします。
新人介護士が独り立ちするまでの流れ

始めに、「新人介護士が仕事で独り立ちするまでの流れ」をお話しします。
- 先輩職員の付き添いのもと、各利用者の対応を覚える
- 利用者対応は基本1人でするが、他職員と一緒にシフトに入る
(完全1人の時間はない、日勤などが中心) - 担当シフトや仕事を1人で出来る、他職員の付き添いを必要としない
職場により人員配置が違いますが、大体こんな感じです。
当記事では独り立ちとは、③の「他職員の付き添いを必要としない状態」として説明します。

入職直後などに研修を行う職場もありますが、その限りではありません。
私の経験上、すぐに現場で働きながら指導を受ける事がほとんど。
ほとんどの場合、ここで説明する流れになると思います。
大手の新卒採用、オープニング施設なんかだと、研修時間が充実してる事が多いです。
入職から独り立ちまでの各プロセス

それでは、独り立ちまでの各プロセスを詳しく確認します。
未経験者も経験者も、基本的には同じ流れで独り立ちします。
入職直後に覚えること

入職直後に覚えるのは、利用者や職場内ルールなどが中心。
先輩職員の完全付き添いのもと、仕事の流れを学びます。
「他職員の仕事を見て覚える」「自分の動きが正しいか確認してもらう」という段階ですね。
- 利用者の名前と顔、特徴など
- 職場のルール
- 仕事の流れ
これらを覚えつつ、簡単な介助から少しずつ出来るようになるのが目標です。
覚える事が多く、1番しんどい時期ですね。

対応が簡単な方から始め、少しずつ出来る仕事を増やしていく事になります。
職場の雰囲気、同僚の職員にも徐々に慣れていきましょう。
自分で動き覚える段階

少し仕事に慣れてきたら、徐々に1人で任される仕事内容も出てきます。
「全部の仕事は出来ないが、出来る事はいくつかある状態」ですね。
自分で動き覚えるのが中心の段階です。
- 基本的な仕事の流れ、職場ルールは理解してる
- 1人で出来る仕事、利用者対応がある
見てもらいながらや指示を受けつつ、仕事を覚えていきます。
1人で対応できる利用者も、少しずつ増えてくると思います。
まだ他職員の手も必要ですので、誰かと一緒に働けるよう配慮されます。
入居施設だと、日勤が多いかと

利用者の特徴や介助方法を覚えてしまえば、後は苦労も少ないです。
この調子で対応できる利用者・介助を増やしましょう。
他時間帯の勤務も、流れを覚えればすぐ対応できる様になりますよ。
独り立ち開始に向けた準備
必要な利用者対応を覚えてしまえば、後は色んな時間帯の流れを学ぶだけです。
入居施設であれば、最後に夜勤を学び、完全な独り立ちとなります。
※時間指定の非常勤等は、自分の出勤時間の事のみでOK

夜勤の付き添いは、2~4回ぐらいの職場が多いです。
自身が無い時は素直に伝え、付き添い回数を増やして貰いましょう。
夜勤専従の場合、指導機会が夜勤のみなのでもっと回数は多いです。


独り立ちまでの期間は3ヶ月程度

未経験から始め、夜勤を1人でこなせるまでと考えると…
独り立ちまでの期間は、およそ3ヶ月程度が目安です。
ただしその期間は、その人の経験や適性、出勤ペースにより違いが出ます。
その他にも、下記の様な要因も独り立ち期間に関わります。
- 身体介助量や仕事の忙しさ
- 介護拒否など、対応が難しい利用者がいる
上記のような、「仕事の難しさ」「大変さ」も独り立ちを妨げる原因です。
気難しい利用者様もおり、職員に慣れるまで時間のかかる方もいます。

介護の仕事は、現場により内容がかなり違います。
利用者との相性などもありますので、あまり他と比べてはいけません。
自分のペースで、少しずつ確実に成長する事が大切です。
未経験と経験者で期間に違いはある?

未経験者と経験者では、独り立ちまでの期間に違いはあります。
経験者は、基本的な介助方法など、仕事のベースがあり必要な指導も少ないです。
利用者の事や業務の流れに集中できる
どちらにしても個人により、仕事を覚えるペースは違います。
仕事内容や利用者、職員の指導方法など、色々な要因もあります。
新入職員・指導者共に焦りは禁物、出来ない事を1つずつ減らすのが大事です。

仕事を覚えるには、やはり慣れが1番効果があります。
続ける事でちゃんと成長しているので、心配しすぎずとも大丈夫ですよ。
分からない事や不安な事は、素直に指導者へ伝えて下さい。
また新入職員は、「分からない事が分からない」事も多いです。
指導者の方も、よく動きを見て的確なアドバイスを伝えられるよう配慮しましょう。
介護職の仕事はどのぐらいで慣れる?

新人介護職の方には、独り立ち関係なく「いつ仕事に慣れるのか」と焦りもあると思います。
職場に慣れるのには、経験者でも早くて1~2カ月。
私が初めて介護で働いた時は、3カ月たっても不安だらけでした。
仕事に対しての自信がついてきたのは3年目ぐらいからです。

10年近く働いても、分からない事や不安はあります。
介護の仕事になかなか慣れないという方も、普通ですので焦らず大丈夫です。
幸い介護はチームプレーの仕事です。
不安や疑問は他職員と確認をし、周囲に頼りつつ進めていきましょう。
自分を守り、自信を持って働くのに大切な事ですので、今から習慣化しておきましょう。
独り立ちが不安な介護職へのアドバイス

新人介護士にとって、独り立ちに不安はつきもの。
ここからは、未経験者が独り立ちを迎えるにあたってのアドバイスを送ります。
- 独り立ちが近いが仕事に不安がある
- 独り立ちさせてもらえない時の原因
仕事が覚えられない時はどうする?

独り立ちといっても、全ての仕事を完璧にこなせる必要はないです。
何時に何をするのか、各利用者に必要な介助。
介助や業務で意識すべき特に注意すべきポイントなど…。
やるべき事や危険なポイントを大まかに理解していれば十分です。
早さばかりに意識をとられず、安全重視で少しずつ自信をつけていきましょう。
新人介護士が苦労しがちなポイント

下記は、新人介護士が躓きがちなポイント。
独り立ち前にもう一度確認をしておきましょう。
- 業務の流れ
- 身体介助の方法(移乗や排泄介助)
- 認知症の対応
利用者の生活は24時間続いており、介護の仕事は時間でやるべき事が決まってます。
スムーズに業務を行えるよう、1日の生活スケジュールと仕事内容はしっかり覚えておきましょう。
また認知症の方への言葉かけも、人や場面で正解が異なり難しところ。
困っている場面を他職員に聞き、効果的な声掛けや対応を尋ねておくと良いですね。
「身体介助の方法」も学びなおす

身体介助では、特に移乗が難しいという声が多くあります。
もし良かったら、下記書籍を参考にしてみて下さい。
身体介助の方法を写真付きで詳しく解説されてます。
介助方法は、何故かという理由もセットで覚えると理解しやすいです。
覚えにくいところは、指導者に確認して利用者への理解を深めていきましょう。
職場で資料の用意がなければ、見ながら働けるようメモを作成しましょう。
「独り立ちまでの期間」は延ばせる?

「まだ独り立ちは待って欲しい」と思ったら、正直に上司へ伝えて良いです。
場合により、独り立ちを遅らせてもらえる可能性があります。
こうしたケースは、1人夜勤の職場でよくあります。
日中と違い聞ける相手もいない為、不安を感じる新人介護士が多いですね。

1人夜勤は勤務も過酷ですので、無理して慣れる必要はありません。
無理だと思ったら、日勤のみで働いたり2人夜勤の職場に転職を検討しましょう。
上記ケースと関係なくとも、仕事への不安は素直に打ち明けてOK。
特に未経験者の方は、焦らず指導者へ相談して下さい。
異動で不安解消する事も

介護では、新人職員の異動もよくあります。
…というのも、新入職員は適性が分からず、とりあえず人員不足のフロアに配置されてしまう為。
フロアにより仕事の質や大変さが違うので、ミスマッチがよくおきます。
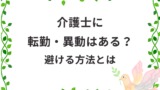
他にも、「指導力のある職員がいるか」という問題もありますね。
何にせよ新人の異動はよくあるし、恥ずかしい事でもないです。
異動で解決した例もたくさん見てきたので、「辛い」と思ったら相談してみると良いですよ。
新人指導に関して要注意な介護施設

ここまででもチラッと話しましたが、独り立ちを急かす職場は危険です。
少しブラック気質な場合もあるので、注意しましょう。
本当はそんな時ほど、職員を大事に育てる必要があります。
人手不足で即独り立ちとなる事も

介護職に多いのが、人手不足で独り立ちを急かされるケース。
シフトが組めないという事情により、「次からは1人で」と言われてしまう場合もあります。
特に未経験の不慣れな職員には、時間をかけ指導する必要があります。

そんな環境で無理をしてしまい、介護事故を起こしているケースもあります。
自分だけでなく、利用者の為にも無理をしてはいけません。
独り立ちするにしても、「人員配置の厚いなかで仕事が出来ないか」掛け合ってみましょう。
「放置」「新人いびり」など、注意すべき指導トラブル

他にも、新人教育にはこんなトラブルが付き物です。
- 入職してから十分な指導もなく、すぐ即戦力扱いされた
- 「こんな事も分からないの?」などの高圧的な指導
- 忙しいからと放置された
これらは経験者もよく遭遇するトラブルです。
即戦力を期待されがちなので余計多いかも
悪気は無くても、こういった態度をしてしまう職員もいます。
まともに教わった経験が無い為、教え方が分からず自分の業務に逃げてしまうワケです。
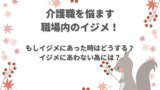
介護が出来るのと、教育指導が出来るのは別の話。
2つは全く別の仕事ですので、よくこうしたトラブルも起こります。
「何をして良いか分からない」時の対処方法

新人として配属になったが、皆忙しそうで何をすべきか分からない。
そんな時は「何かやりますか?」と指示を促したり、「○○が分からない」と尋ねましょう。
話しやすそうな人に、「一緒に見させてもらって良いですか」と付いてくのもアリ。
仕事の不安や疑問は、どんどん吐き出してOK。
…改善されず、自分も限界にきているなら、早めに環境を変えるべきかもしれません。

転職サイトでは、新人職員向けの相談も受け付けてます。
指導力のある職場を選び紹介してくれるので、活用してみて下さいね。
マイナビ介護職が、求人の質と職員定着率にこだわっておりオススメ。
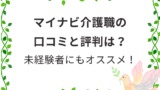
まとめ

今回は、「介護士の独り立ち」についてお話ししました。
最後に、新人介護士の独り立ちの流れを簡単にまとめます。
- 利用者や職場の事を「見て聞いて覚える」
- 介助方法や仕事の流れを「動いて覚える」
- 不安点を解消しつつ、独り立ちを目指す
夜勤に入る場合、最後に付き添いでの夜勤に入る
独り立ちまでは3カ月程度が目安ですが、人によるので気にする必要はありません
焦らず自分のペースで、出来る事を少しずつ増やす事が大切です。
不安な時は「独り立ちを遅らせられないか?」と、指導者に相談しましょう。

独り立ちしたからといって、仕事が全て出来る必要はありません。
未経験者が介護の仕事に慣れるまでは、もっと多くの時間を必要とします。
忙しい環境で焦りも多いと思いますが、そんな時こそ慎重に安全に働きましょう。
職場や仕事に慣れるまでは、1番しんどい期間。
それまでは周囲のサポートを上手く使い、乗り切っていきましょう。
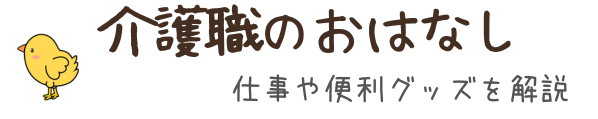
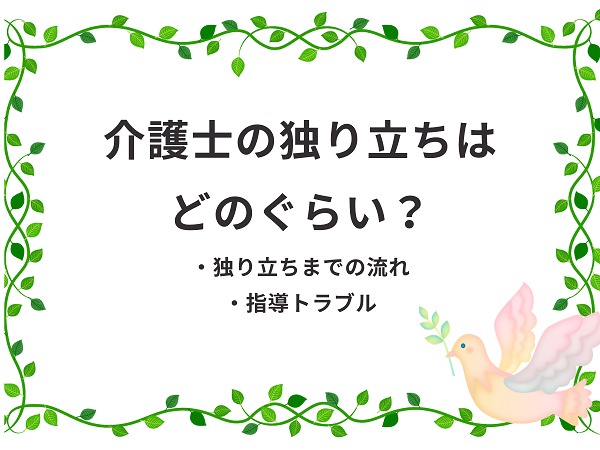
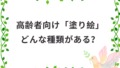
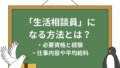
コメント