介護施設の夜勤は、職員も少なく事故も多い時間帯。
一人で動く場面も多く、職員同士でもお互いの仕事が分からなかったりします。
そこで今回は、老人ホーム等の「介護施設の夜勤の仕事内容」を解説。
- 巡視の注意点
- 排泄介助の方法
- 起床、就寝介助の方法
上記内容や仕事スケジュールなど、介護夜勤の内容をご説明します。
これから夜勤に入るため、仕事内容を知りたい人。
現在夜勤で働いていて不安な人、それぞれご参考下さい。
介護施設のに夜勤業務を細かく解説します。
介護施設における夜勤の仕事内容
.jpg)
それでは、夜勤の仕事内容を解説してます。
巡視でのチェックポイント、オムツ交換やトイレなどの排泄介助を紹介します。
夜勤者の「主な仕事の流れ」
下記は、介護施設における夜勤者の仕事スケジュールです。

介護夜勤の仕事は「夕食や就寝介助」に始まり、「起床や朝食の介助」で終わる形です。
上記図は、16時間夜勤の例です。
8時間夜勤の場合は、就寝後に出勤し、起床介助前に退勤となります。
これらを定時でこなしつつ、細かな仕事や利用者対応を行います。
介護夜勤における「巡視の方法とポイント」

巡視とは、利用者様の安否確認の事です。
介護施設での巡視は、入居者様を1人ずつ様子を見に行く業務です。
※ラウンドや巡回とも呼ばれます
巡視を行う時間は、主に22時~翌朝5時までの間。
施設により細かな時間は異なりますが、巡視間隔は2~3時間である事が多めです。
巡視時の観察チェックポイント

巡視では利用者様の状態について、下記の様な事を確認します。
巡視での観察チェックポイント
- 覚醒状況
- 呼吸や健康状態
- 居室温度や安全確認
基本的には、「寝てる」「起きてる」の覚醒状況ですね。
起きてる場合は、どう過ごされてるかも確認します。
よく寝ている様でも、意外と体調不良等の変化がある事もあります。
巡視は相手の異変に気付く為、とても重要な業務です。
自分を守る事にも繋がりますので、意識を持って行いましょう。

巡視を行う際は、呼吸状態の確認まで行えるとベストですね。
最低でも、姿の目視は行うようにして下さい。
自分で動けない方には、寝返り介助(体位交換)も行います
居室の温度、転落の危険が無いかなど、環境や事故の危険も注意して見ましょう。
夜間の巡視には、ペンライトがあると仕事が捗ります。
⇒オススメ介護士用品を特集!必需品や便利グッズなど仕事の持ち物紹介
巡視を楽にする「介護機器」

介護機器の発達により、ベッドセンサーの機能も進化してます。
近年では、離床だけでなく下記の健康状態の把握もできる様になりました。
- 呼吸
- 心拍
- 覚醒状況
離床や起き上がりも含め、各状況をPCやスマホで確認できます。
これにより、安眠を妨げず、その人のリズムに合った介助も可能となりました。
介護職としても、仕事の安心に繋がりますね。
ただ転職活動中なら、こうした機器の有無にも注目すべきですね。
「安眠」「様子確認」どちらを優先すべき?
巡視に伺うと、「誰?」「何よ!」と驚かれる方もいます。
巡視も大切ですが、人の気配に敏感な方もおり、どうしても安眠を阻害してしまう事も。

「どこまで巡視するのか」は、やはりケースバイケース。
日頃から「誰にどんな対応をすべきか」を職員間で情報交換しておきましょう。
個人的には、安眠を阻害しない範囲で良いと思ってます。
普段から不安点の情報交換をするクセをつけておくと、仕事がしやすくなります。
夜勤帯の「排泄介助(オムツ交換)方法」

巡視と同じく、排泄介助も定時で行う仕事です。
オムツ交換やトイレ誘導といった内容ですね。
回数については、「施設の考え」や「利用者様の尿量」により異なります。
夜間帯の合計では、3回ぐらいが目安。
しかし、3回排泄介助に入るとして、入居者全員を毎回介助するワケではありません。
概説介助の回数は、その人の「尿量」や「トイレのペース」を考慮し、決定します。
トイレ誘導と見守り
ご自分でトイレに動かれる方は、基本的にご本人のペースに任せます。
失禁がある場合、トイレ間隔を見てこちらから声掛けもします。
その人が行きたい時に付き添い・確認をする形が多いですね。

転倒リスクの高い方は、ベッドやフットセンサーで動きをキャッチし付き添いします。
歩行が安定しない方は、夜間のみポータブルトイレを設置する事も。
こんな方が多くなると、夜勤者も忙しくなります。
付き添いも必要ない方の場合、トイレ間隔の記録のみ行います。
コール・センサー対応
夜間帯は、利用者のセンサー・コール対応も多くなる時間です。
- 転倒リスクの高い方が、目を覚まして動き出しセンサーが鳴った
- ナースコールを受け、利用者の困り事に対応する
こうした対応も、夜勤者の重要な仕事です。
トイレの話でもありましたが、介護施設には転倒リスクの高い方も多くいます。
また認知症により、自分の危険を理解できない方も沢山います。
しっかりしてる方からも、自分の不調を相談されたりもします。
夜勤者は、こうした方々の安心や安全を守るのも仕事です。
暇な時間でも、センサーやコール反応に備えておく必要があります。
正直言ってしまうと、夜勤の忙しさはセンサーコールの多さ次第。
老人ホームの夜勤について、「暇」「忙しい」と意見が分かれるのはそんな理由があります。
就寝介助と起床介助
16時間夜勤の場合、起床・就寝介助も加わります。
※今回は、食事介助は割愛
夕食を終えたら、歯磨きや排泄を済ませ、お部屋で着替えて寝る。
朝起きたら、着替えて顔や髪をキレイにして、フロアへご飯を食べに行く。
こういった内容のお手伝いですね。

生活スタイルは利用者や施設で異なり、パジャマ更衣も必須ではありません。
業務や個人の十分な理解が必要な仕事ですね。
加えて、夜勤者はよく下記業務も担当します。
- 就寝前や起床時の薬内服
- 衣類の更衣
- 血圧などのバイタル測定
どの人にどんな対応するのか、しっかり理解しておきましょう。
朝と夕は職員が少ないのもあり、夜勤者にとって忙しい時間帯です。
事故が起こりやすい時間でもあるので、焦らず安全に動きましょう。
「食事準備」「書類」などの雑務
ここからの話は施設による違いが大きいですが、洗濯物や掃除などの仕事もする施設もあります。
食器やお茶の準備などの食事の準備もそうですね。
厨房がある施設では、ご飯の炊飯やお茶の準備のみ介護士が行う

特変なく平和な時間が続けば、夜間は昼間より時間の余裕があったりします。
そんな時間を利用して、昼間出来ない「記録・書類仕事」を進める事もあります。
カンファレンスやモニタリング等、介護の仕事って記録や書類仕事も多いんですね。
もちろん利用者さんについての記録は、昼間と同じく行う必要があります。
夜勤の勤務時間による「仕事内容・休憩等の違い」
.jpg)
夜勤の勤務時間には、「16時間」と「8時間」があります。
先の説明で少し触れましたが、仕事内容等も異なる為、この違いをもう少し解説します。
勤務時間による夜勤業務の違い

夜勤の出退勤の時間は、主に下記2種類に分けられます。
- 16時間夜勤
⇒ 16:30~翌9:30 - 8時間夜勤
⇒ 22:00~翌7:00
細かな違いはありますが、大体の時間はこんな感じ。
8時間夜勤は、就寝介助を終えた所に出勤、起床介助前には帰る事が出来ます。
16時間夜勤は、朝・夕の食事介助と就寝・起床介助も仕事です。
8時間夜勤は、定時のオムツ交換や巡視、コール対応等のみが仕事。
起床・就寝介助は忙しく、夜勤業務の1つの山場とも言える仕事。
8時間夜勤は夜間業務のみで終えられる為、業務面でも楽ですね。
一部施設では準夜勤も

一部の介護施設では、準夜勤というシフトも設定されてます。
これは夕方から出勤し、深夜に退勤する勤務。
勤務時間が異なるのみで、通常の夜勤と仕事は大きく変わりません。
ちなみに他職員の勤務時間は、早番が起床時から出勤。
遅番が就寝介助後までの勤務です。
夜勤者の勤務時間に合わせ、遅番者の勤務時間も施設で異なるので注意。
休憩時間や休日の違い

夜勤の8時間と16時間では、休日や休憩時間にも違いがあります。
簡単に言うと、8時間夜勤は勤務日数1日分。
16時間は2日分と扱われます。
つまり8時間夜勤は、「夜勤(入)」「公休(明け)」というシフトです。
| 1日目(夜勤入り) | 2日目(明け) | |
|---|---|---|
| 16時間夜勤 | 夜勤 | 明け |
| 8時間夜勤 | 夜勤 | 公休 |
2日にまたがって勤務しているが、勤務時間は1日分。
だから入りの日は出勤、もう1日は公休扱いという事です。
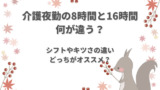
「勤務時間」「人員配置」で休憩時間も異なる

また休憩時間は、施設により異なります。
労働基準法では「8時間を超える場合は1時間の休憩を付与すべき」とあり、夜勤中は少なくとも1時間の休憩時間があります。
ただ16時間夜勤の場合、2時間程度の休憩時間がある事も珍しくありません。
8時間夜勤の場合、休憩は1時間で仮眠時間の確保は難しい面があります。
転職活動においては、時間の細かな違いもチェックする事をオススメします。
実際の話をすると、休憩の内容は「夜間帯の職員配置」でも異なります。
グループホームや特養など、ユニット型施設では夜間の介護職員は1人。
空いた時間で自主的に休憩します。
⇒介護の1人夜勤はキツイ!休憩が取れないワンオペ夜勤の実態
夜間の緊急対応について

夜勤中に「利用者様の体調が悪化」「転倒でケガをした」。
こんな事はよく起こります。
施設ごとに緊急時の対応マニュアルがあるので、確認しておきましょう。
多くの場合、在籍する看護師や責任者に連絡を取り、指示を仰ぐ事が可能です。
他職種に対応を任せる事も多いですが、人員配置次第では介護士が同乗する事も。

夜勤の仕事を教えてもらう時は、夜間1人の施設でも先輩職員の付き添いがあります。
事前に緊急時の対応・連絡先について、確認を取っておきましょう。
「〇〇だったらこうする」という様に事前に対応を話し合っておく事も重要です。
介護士にとって大きな不安要素ですので、自信がつくまで夜勤をしない働き方を選ぶのもアリですよ。

オンコール体制とは
看護師等が在籍している施設では、夜間の緊急連絡を担当する看護職員が交代でつきます。
これをオンコール体制と言い、夜間帯に体調悪化があった場合、連絡して指示を仰ぐことが出来ます。
必要があれば、駆け付けてもらい救急搬送や受診、状態確認なども行います。

職場を選ぶ際は、「夜間でも安心して働ける体制」が整っている施設を選びたいですね。
看護師がいない場合でも、緊急時の対応や連絡先、誰に指示を仰ぐかなど…
しっかりマニュアル化されている施設を選びましょう。
オンコール時の連絡基準も定まっていると、なお良いですね。
どんな介護施設での夜勤がオススメ?

どんな介護施設を選んでも、大まかな仕事内容は変わりません。
細かな違いは、下記になります。
- 職員と利用者の数
- 勤務時間や仮眠の有無
- 夜勤手当
- 緊急時の連絡体制
勤務時間については、冒頭でお話しした通り。
公休の取り方にも関わる要素です。
他の要素は、施設形態により傾向があったります。
働きやすい職場を選ぶポイントが分かるよう、解説していきますね。
「ユニット型」と「従来型」で職員配置が違う
まずは、担当利用者の人数と夜間の職員配置。
仕事の忙しさや休憩、仕事への不安感に関わる要素ですね。

夜勤は職員人数が少なく、1人~2人という施設がほとんどです。
多い施設でも、3人まででしょう。
この配置は、ユニット型施設か従来型かで異なります。
- ユニット型
⇒「職員は1人、担当利用者は少ない」 - 従来型
⇒「職員は複数、担当利用者は多い」
ユニット型というのは、施設の利用者様をグループ分けしてる施設です。
大規模施設の中に、小規模施設が複数存在してるようなイメージですね。

一方従来型は、施設の利用者全員を職員全体でみていく施設です。
職員配置が多い従来型の方が、休憩や仮眠は取りやすいですが…、
担当利用者が多く、楽と言い切る事は難しいです。
ここでいう職員数は総数で、その場にいる職員数ではありません。
未経験での夜勤なら「有料老人ホーム」

未経験者が夜勤をするのに、個人的には介護付き有料老人ホームがオススメ。
有料老人ホームは介護度が低めの傾向ですし、オンコール体制も整ってます。
複数人で夜勤に入れる職場を選べば、仮眠もしっかりとれます。
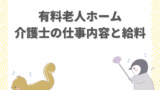
また担当入居者数だけなら、グループホームが少ないです。
夜勤者は1ユニットに1人つくので、担当人数は9人ですね。
※1ユニット9人、2ユニットまでという小規模施設
逆にしんどかったのはユニット型の特養。
オムツ交換や就寝起床介助は大変だし、1人で休憩は取れないという感じでした。
他施設へ転職し、仕事量の差に驚いたぐらいです。

介護系の転職サイトを使えば、そうした詳細を調べながら求人を検索できます。
「日勤のみ」「夜間のみ」といった条件でも、絞込検索できます。
アドバイザーへの相談も出来るので、連絡体制がしっかりしてる職場を聞くのも有効です。
夜勤手当や働き方もこだわれる
夜勤手当が目当てで、介護施設での夜勤をしたい方も多くいます。
額は5,000円~1万円程度と、施設により差がありますが、給料を支える大事な収入源です。

介護施設での働き方の1つに「夜勤専従」というモノがあります。
詳しくは下記記事をご覧になって欲しいのですが、夜勤専門で働くという事です。

逆に日勤のみという働き方もあります。
正社員(常勤)ばかりに目がいきがちですが…、
そうした選択が出来るのは、パートや派遣の強みです。
介護施設での仕事は、勤務時間も不定期です。
マイペースに働く事も選択できるので、働き方の1つとして覚えて置きましょう。
夜勤者の残業が増えてきたら注意

夜勤者目線でみると、夜勤明けで残業がある職場は要注意。
ちょっとぐらいであれば良いですが…
職員不足で「入浴介助を手伝って!」ぐらいになると、だいぶよろしくない状況。
職員不足により、夜勤者の業務負担が増えてきたら、転職を考えても良い時期にあると思います。
真面目な話、夜勤明けでの帰り道は危険です。
事故を起こしても面白くないですし、心身に悪影響がある場合、職場を変えるべきだと思います。

また職員不足により、夜勤回数が極端に増えた時も危険。
身体への負担が強い時は、逃げる事も考えましょう。
まとめ

今回は、介護施設の夜間業務について解説しました。
慣れてくると忘れてしまう時がありますが、特に巡視は重要です。
私自身も、「寝ている様に見えたけど、急変状態にあった」という事も経験してます。
夜間帯は、高齢者の体調変化も多い時間帯です。
初心を忘れず、早めに気付いてあげられるよう観察をしていきましょう。

また当記事では、介護度が高めの施設を想定した内容を書かせて頂きました。
「何だか大変そう」と心配な方は、下記記事も参考になるかと思います。
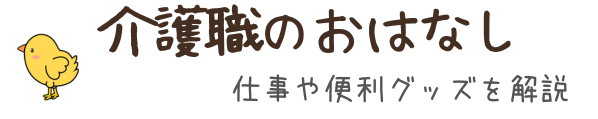


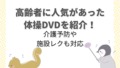
コメント